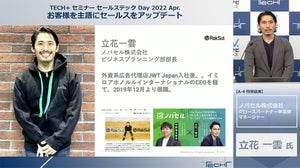DXは、デジタル化に止まらない潜在性を持つ。中でも、AIとクラウドの組み合わせにより、これまでのハードウエアはデータの端末に過ぎなくなる――こう話すのは作家・ジャーナリストの佐々木俊尚氏だ。
6月23日、24日にオンラインで開催された「TECH+ EXPO 2022 Summer for データ活用 データから導く次の一手」では、この佐々木氏が『AIとDXによって全面移行していく新たな「産業構造」の世界』と題した基調講演に登壇。これからの産業構造がどう変わるのかについて、展望した。
「TECH+ EXPO 2022 Summer for データ活用」その他の講演レポートはこちら
DXの誤解を解く
冒頭、佐々木氏はまず「DXとは何か」について言及した。
DXとはデジタルトランスフォーメーションの略語だが、2000年代のIT化、その前のOA化とどう違うのだろうか?
「これまでのプロセスはそのままに、デジタルツールを使うのであればIT化に過ぎない」と佐々木氏。その意味でペーパーレスもDXとは言い切れないと指摘する。
ではDXの本質とは何か? 佐々木氏は「データとAIこそが産業の本質だ」と述べ、モノづくりの日本が得意とするハードについては「データの端末に過ぎないと認識する必要がある」と説く。こうしたことを踏まえた上で、「その構造を基に、産業を組み替える必要がある」(佐々木氏)のだ。
「(DXは)プロセスをIT化するだけではなく、プロセスそのものが変わっていくのです。構造自体が変わっているということを理解しなければなりません」(佐々木氏)
AIの能力は”特徴の発見”
そのためにはまず、AIを理解することが最初のステップとなる。
佐々木氏はAIについて、「現状のAIは深層学習ができます。これにより、人間には到底見つけられない特徴を見つけてくれるのです」と説明。例として、日立製作所が行ったヒューマンビッグデータの実験を紹介した。
これは、赤外線センサーや加速度計、Bluetoothなどが内蔵された電子デバイスを社員に装着してもらうという実験で、業務成績の良い部署のデータを見ると、チームの中に活発にコミュニケーションをとっている社員がいることが分かった。この社員の活動によりチーム全体が活発化し、成果として現れたということが判明したのだ。
同じヒューマンビッグデータの例として、同氏は、あるホームセンターでの実験も紹介した。同実験は、ホームセンターのスタッフ、顧客にデバイスを装着してもらい、スタッフがどういう行動をしていた時に顧客単価が上がったのかをAIに計算させるというもの。そこでAIが導き出した答えは意外なものだった。
「“あるポイント”にスタッフが立っていると顧客単価は上がる」というのだ。そのポイントは、レジの前でも、店の入り口でもない、これといった特徴のない角だったという。これがどの程度有効なマーケティング施策になるのか、マーケティングの専門家が考えた施策との比較が行われた。店舗で10日間データを収集し、その後1カ月間、専門家考案の施策を実施したところ、結果はAIの“圧勝”。「ある角にスタッフを立たせる」場合は顧客単価が15%増加したそうだ。
こうした例を紹介した佐々木氏は、AIについて「人間には決して分からない特徴を見いだしてくれて、しかもそれが大体当たっている」と評価する。
ここで、「なぜAIには、そんなことができるのか」という疑問が湧く。佐々木氏も「ロジックは分からない」と認める。現在の深層学習は単純な方程式の積み重ねだが、億単位の数字を当てはめて計算していることもあり、人間がロジックを理解するのは難しい。
それでも、AIのパワーは無視できない。「このような”特徴を発見する”AIの能力は、今後あらゆる産業に導入されていくだろう」と、佐々木氏は予想する。さらに、「同業他社がAIを導入しているのに、自社が導入しないとなると、特徴が発見できないが故に競争に負けるということになりかねない」と続け、「これこそがDXの本質だ」と断言した。