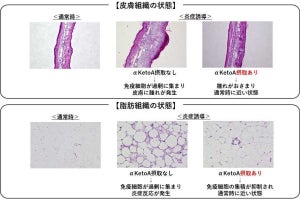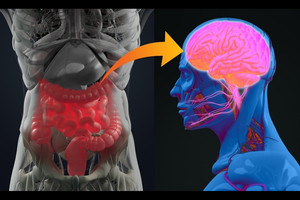近畿大学(近大)は5月30日、日本人女性を対象に、月経前症候群(PMS)と腸内フローラ(腸内細菌叢とも)の関連性を研究し、抗うつ作用への関与が期待できる「酪酸産生菌」や、脳内神経伝達物質を産み出す「GABA産生菌」が減少していることを確認したと発表した。
同成果は、近大 東洋医学研究所の武田卓所長らの研究チームによるもの。詳細は、米オンライン科学誌「PLOS ONE」に掲載された。
PMSは、月経前に3~10日において、イライラや落ち込み、不安感といった精神症状と、腹部膨満感・乳房症状といった身体症状を特徴とする。女性のパフォーマンスを妨げることから、女性の活躍促進が求められる現在、注目されるようになっている。
しかし、標準治療である「低用量ピル」や抗うつ薬である「選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)」が、一般的にあまり受け入れられていない現状もあり、十分な治療が行われていない。そのため、簡便で身体への負担が少ない治療法の開発が期待される状況となっている。
一方、腸内フローラは近年、さまざまな疾患との関連性が研究対象となっており、個数で100兆から1000兆、種類数では約1000種類といわれる多種多様な腸内細菌は、ヒトの疾患や体調などに関与しているとされ、新たな治療ターゲット候補として研究が進められている。
また、PMSはうつ病と多くの共通点が見られるため、うつ病などの精神疾患の分野において脳との関連性も注目されるようになってきているものの、その詳細な原因は明らかでなく、PMS患者における腸内フローラの検討はこれまで実施されていなかったという。
そこで研究チームは今回、PMS患者における腸内フローラの特徴を明らかにするため、中等度以上のPMS患者とPMS症状の自覚がない健常者を対象に調査を実施することにしたという。