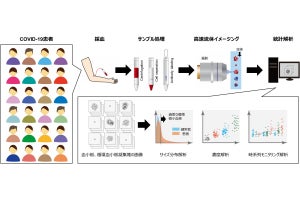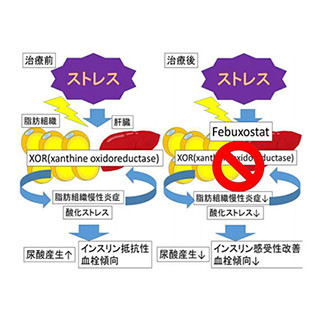東京医科大学(東京医科大)は3月1日、若い健康な人でも、8時間の座位姿勢保持で血栓症発症リスクが上昇すること、ならびに着圧の低い弾性ストッキングの着用によって、血栓症発症リスクが軽減する可能性を見出したことなどを発表した。
同成果は、東京医科大 健康増進スポーツ医学分野の黒澤裕子講師らの研究チームによるもの。詳細は、スポーツ医学と運動科学を扱う米スポーツ医学会の公式学術誌「Medicine & Science in Sports & Exercise」に掲載された。
長時間にわたる座位姿勢の保持は、下肢の深部静脈に血栓が生じる「深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)」につながるだけでなく、最悪の場合、命にかかわる「肺塞栓症」を併発することが知られるようになってきた。しかし、長時間の座位姿勢保持が生体にどのような影響を及ぼすのか、また時間経過に伴う詳細な変化については、良く分かっていなかったという。
また、そうした長時間座位姿勢保持による生体への悪影響を予防する方法について、その有効性を検証したエビデンスが不足していることもあり、今回、研究チームは、平均年齢22.6歳の健康な男性9名を対象に、飛行機のエコノミークラスシートに近い形状の椅子に、8時間連続で座ってもらい、1時間ごとに下肢の周径囲、動脈血流、筋酸素化レベルの測定を実施し、長時間座位姿勢保持が生体に及ぼす影響の調査を行ったほか、座位時に左右無作為に片肢のみ、低い着圧の弾性ストッキングを鼠径部から足首まで着用してもらうことによる効果検証を行うことにしたという。
実験の結果、ふくらはぎと足首の周径囲は増大し、下肢の浮腫(腫れ・むくみ)が認められたほか、下肢浮腫の変化率と、ふくらはぎ周径囲の変化率との間には、有意な正の相関関係があることが判明。この結果は、下肢周径囲の座位姿勢保持による増大が、下肢浮腫に由来するものであることが示されているとする。
-

下肢周径囲および浮腫の変化。(A)ふくらはぎ周径囲の変化率。〇弾性ストッキング非着用肢、●弾性ストッキング着用肢。(B)足首周径囲の変化率。〇弾性ストッキング非着用肢、●弾性ストッキング着用肢。(C)浮腫の指標下肢骨格筋細胞外水分量の変化率。□弾性ストッキング非着用肢、■弾性ストッキング着用肢。(D)下肢骨格筋細胞外水分量の変化率と、ふくらはぎ周径囲の変化率の関係。〇弾性ストッキング非着用肢、●弾性ストッキング着用肢 (出所:東京医科大プレスリリースPDF)
また、実験後の下肢の動脈血流は約40%低下し、ずり応力も、弾性ストッキング着用肢に比べ、非着用肢では有意な低値が示されたとするほか、動脈血流の変化率とふくらはぎ周径囲変化率、および足首周径囲変化率との間には、有意な負の相関関係が認められたともした。この結果は、座位姿勢保持による下肢動脈血流の低下が下肢周径囲の増大につながったことを示すものだとする。
-

下肢動脈血流、ずり応力、下肢動脈血流変化率と下肢周径囲変化率との関係。(A)動脈血流。〇弾性ストッキング非着用肢、●弾性ストッキング着用肢。(B)ずり応力。〇弾性ストッキング非着用肢、●弾性ストッキング着用肢。(C)下肢動脈血流変化率と、ふくらはぎ周径囲変化率との関係。〇弾性ストッキング非着用肢、●弾性ストッキング着用肢。(D)下肢動脈血流変化率と、足首周径囲変化率との関係。〇弾性ストッキング非着用肢、●弾性ストッキング着用肢 (出所:東京医科大プレスリリースPDF)
さらに、腓腹筋の酸素化レベルも、座位開始前と比べ、座位後には低下していることも判明。これらの結果は、座位姿勢保持による下肢の血行動態の悪化を示すもので、血栓症発症リスクの上昇を示唆するものだと研究チームでは説明している。
一方で、現在医療現場で推奨されている着圧よりも低い着圧の弾性ストッキングを片肢に着用した場合では、8時間の座位後でも、ふくらはぎと足首の周径囲は増加せず、下肢の動脈血流の低下も約15%に抑えられていることが確認されたほか、腓腹筋の酸素化レベルも、実験開始前と比べて変化しておらず、悪化を示さなかったことが確認されたとする。
これらの結果について研究チームでは、日常生活での長時間座位姿勢の保持は、特に下肢の血行動態を悪化させ、血栓症発症リスクを増大させる可能性を示唆する一方、着圧が低くて着用しやすい弾性ストッキングを利用することは、血栓症発症リスクの軽減につながることを示すものだとしている。
そのため研究チームでは今後、妊婦や高齢者のような、血栓症発症リスクがより高い人々を対象とした研究を行うことにより、高リスク者の座位姿勢保持に伴う生体変化の解明ならびに低い着圧の弾性ストッキング着用効果の調査を行っていきたいとしているほか、座位姿勢保持に伴う生体への悪影響を予防する方法として、座位中の運動実施効果も検証していくとしている。