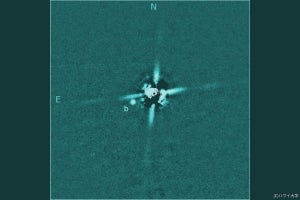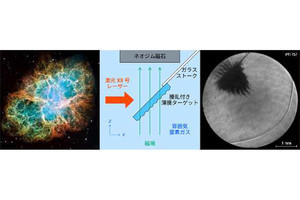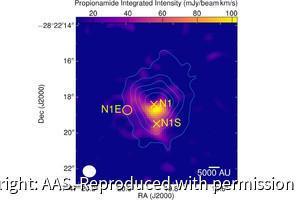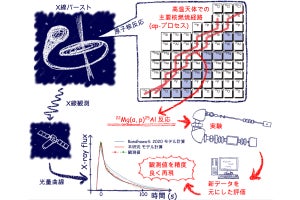京都産業大学(京産大)は10月26日、標準的な宇宙論において仮定されている「一様等方モデル」の妥当性に関する理論的基礎を確立したことを発表した。
同成果は、京産大大学院 理学研究科 物理学専攻の朝永真法大学院生、京産大 理学部の二間瀬敏史教授らの研究チームによるもの。詳細は、日本物理学会が発行する理論物理と実験物理を扱うオンラインオンリーの英文オープンアクセスジャーナル「Progress of Theoretical and Experimental Physics」に掲載された。
標準的な宇宙論の理論モデルは、「宇宙には中心も端もなく、宇宙のどこにおいても本質的に同等である」という「一様等方」の仮定のもとに構築されている。
しかし、現実の宇宙はさまざまなスケールで物質の濃度に差がある(物質の分布に非一様性が存在している)ことが分かっている。これは、「一様等方宇宙モデル」は、非一様な時空を何らかの意味で平均化して得られるべきものであることを意味し、これまでは平均化によって一様等方宇宙モデルを導くには、ある特定の座標系を仮定していた。そのため、その結果が仮定した座標に依存するかどうかが問題となっていたという。
そこで研究チームは今回は、「時空の3+1分解」と呼ばれる方法を用いて、従来とは異なる座標系においてアインシュタイン方程式(一般相対性理論の基礎方程式)を平均化することを試みることにしたという。その結果、従来と同じ一様等方宇宙モデルが導かれることが示されたとしており、これにより現在宇宙論で「ハッブル定数問題」として知られる、宇宙マイクロ波背景放射の観測から得られる大域的な膨張則と、超新星の観測から得られる局所的膨張則との間にある約10%ほどの不一致を、時空の非一様性から説明する理論的基礎が確立されたとする。
なお研究チームでは、宇宙の加速膨張の理解に新たな光を当てることで、今後、ダークエネルギーの存在も含めて、宇宙論研究に新たな展開や進展が期待されるとしている。