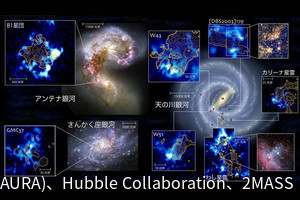ヨーロッパ南天文台(ESO)は現地時間3月18日、1994年に起きたシューメーカー・レビー第9彗星の衝突によってもたらされた分子をアルマ望遠鏡を使って観測することで、木星の極付近の成層圏に時速約1440kmという強風が吹いていることを明らかにしたと発表した。
-

木星の極域の成層圏に吹くジェットの想像図。青い線でジェットの風速が表されている。木星の画像は、NASAの木星探査機「Juno(ジュノー)」により撮影されたもの (c) ESO/L.Calçada & NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS (出所:ESO Webサイト)
同成果は、仏・ボルドー天体物理学研究所のティボー・キャバリエ氏、同ビラル・ベンマヒ氏、米・サウスウェスト研究所のトーマス・グレートハウス氏らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、欧州の天文学専門誌「Astronomy & Astrophysics」に掲載された。
木星では、複数の高度において帯状の雲が存在しており、それが遠目に見たときの白と茶色の縞模様に見える。縞模様をなす雲は木星の自転とは異なる速度で移動しており(向きも縞模様によって自転と同じ方向と反対方向と両方がある)、天文学者たちはこの雲の動きを手がかりにして木星の低層大気の風を観測してきた。また、木星の極域にはオーロラが見られるが、それらは上層大気に吹く強風と関連があると考察されている。しかし、それらの中間に位置する成層圏における風を直接調べることは、これまでできていなかった。
成層圏における風の研究が難しいのは、調べる手がかりとなる雲が発生しないからだ。そうした中、成層圏の風を調べやすくなる、都合のいいビッグイベントが1994年に発生した。シューメーカー・レビー第9彗星が木星に衝突したのだ。
彗星の木星(惑星)への衝突というイベント自体が貴重な天文現象だったが、シューメーカー・レビー第9彗星はそれだけでは終わらず、木星成層圏の風を調べるためのトレーサーともいうべき分子を残すことになった。現在でも、衝突時に同彗星によってもたらされた分子が成層圏の風に乗って移動し続けている。今回の観測では、アルマ望遠鏡を駆使して、その1つであるシアン化水素(HCN)分子が放つ電波を観測し、成層圏に吹く「ジェット」の速度の計測に成功した。
ジェットとは、いわゆる地球の大気圏で吹いているジェット気流のようなもので、幅の狭い帯状に伸びる風のことをいう。そのジェットに乗って電波を出す分子が移動している場合、移動によってその分子から放たれる電波の周波数がわずかに変化する。この変動とはドップラー効果のことで、それを測定することでジェットに乗って流されるHCN分子の移動速度を推定することが可能となるのである。
そして今回発見されたのが、木星の極域の成層圏(木星オーロラの下辺り)に吹く秒速約400m、時速にすれば約1440km/hという強風だ。地球の標準大気での音速(マッハ1)が時速約1225kmであることを考えると、どれだけとてつもない風速であるかがわかる。木星には、地球すら飲み込むほど巨大な台風として有名な大赤斑があるが、その最大風速と比較しても2倍以上になる。地球で最も強い竜巻と比較した場合は、3倍以上となる(ただし、太陽系の惑星大気中の風としてはさらに速いものも存在しており、最速は海王星の時速2000kmオーバーの大暴風)。
またこの時速約1440kmのジェットは、高度約900kmにおいてぐるっと木星を1周しており、地球の4倍とう巨大サイズの渦を作っていることを示しているという。国際共同研究チームでは、このジェットを「太陽系でもユニークな気象の怪物」と表現しているとした。
木星の極域の成層圏において約1440km/hもの速度で吹く強風のアニメーション (c) ESO/L. Calçada & NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
これまでの研究から、木星の極域には強風が存在することは知られていたが、それは今回のジェットが吹く成層圏よりも数百km上空のことだった。これまでは、その高層大気の強風は高度が下がるにつれて速度が低下し、成層圏では消失しているものと考えられてきた。しかし、今回の観測結果はそれを大きく覆すものであったことから、多くの研究者を驚かしたという。
さらに、この極域の強風ほどではないが、成層圏の赤道域でも強風が確認された。赤道域では、時速約600kmの風が吹いているとしている。
ちなみに今回の観測時間の短さも驚異的で、極域と赤道域合わせてわずか30分足らず。短時間でジェットに乗って流されるHCN分子のドップラー変動が検出されたのである。ひとえに、アップデートが続けられてきたアルマ望遠鏡の高い性能に寄るところが大きいという。
なお論文の筆頭著者であるキャバリエ氏は、今回の観測結果は数ヶ月前には想像もつかなかったことであり、木星の極域の研究に新たな扉を開いたとしている。また共同著者のひとりであるグレートハウス氏は、2022年に打ち上げ予定の木星衛星探査計画(ガニメデ周回衛星)「JUICE(JUpiter ICy moons Explorer)」と、そこに搭載されるサブミリ波観測装置による詳細な測定の基礎となるだろうとしている。
JUICEはESA(欧州宇宙機関)の主導で進められている史上最大級の国際探査計画で、JAXAやNASAも参加して探査機の開発が進められている。JUICEは現在のところ、2022年9月にアリアン5ロケットで打ち上げられ、金星→地球→火星→地球とスイングバイを重ねて2029年1月に木星に到着するスケジュールだ。
木星圏に到着後は、まずカリスト(2029年1月~2030年10月)を、続いてエウロパ(~2031年1月)をフライバイ観測したあと、2032年9月に最終目的地のガニメデに到着し、周回軌道に投入される(計画は2033年6月まで続けられる)。カリストでは表面や内部などの探査、エウロパでは地下海における生命存在可能性の探査などが行われ、ガニメデでは内部構造の精査や地下海の存否の解明などの観測が行われる計画だ。