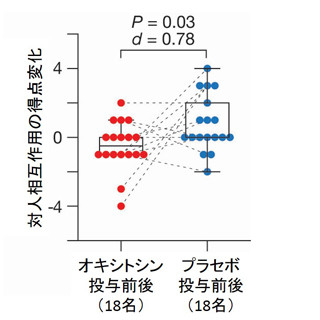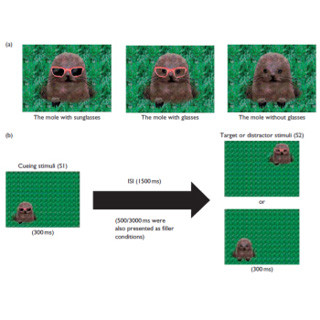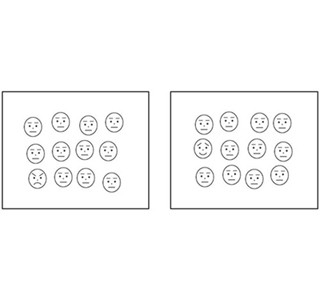弘前大学は、子供のインターネット依存状態の推移とその推移のパターンと状態の変化に関わる神経発達障害特性の関与の調査から、調査開始時点でインターネット依存状態の子供が、その後2年間インターネット依存の状態が維持される確率は47%との結果を得たことを発表した。
同大 医学部心理支援科学科の髙橋芳雄 准教授、足立匡基 准教授(いずれも医学研究科附属子どものこころの発達研究センター兼任)、ならびに同大 医学研究科神経精神医学講座の廣田智也 客員研究員(カリフォルニア大学サンフランシスコ校 助教授)らによるもの。詳細は学術誌「Journal of Autism and Developmental Disorders」に掲載された。
今回の研究は、子供のインターネット依存の状態が長期的にみてどのように変化するのかについて調査したもの。弘前市の小学4年生から中学1年生の児童生徒、5483名を対象にインターネット依存の状態が2年間でどのように変化するのか、また神経発達障害と関連した特性がインターネット依存の状態の長期的な変化に対してどのように影響するかについてを調べたという。
その結果、調査開始時点でインターネット依存の状態の子供の中で、2年後もインターネット依存の状態が維持される確率は47%ということが判明したほか、高学年の方がインターネット依存の状態が比較的維持されやすいことが明らかになったという。
また、調査開始時点でインターネット依存でなかった子供が、調査期間内にインターネット依存の状態になる確率は11%程度であることも判明したという。
さらに、インターネット依存状態の推移と発達障害特性の関連を調べたところ、自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症(ADHD)と関連した特性、中でも不注意特性がインターネット依存状態の維持や調査期間内での新たな発生に関連していることも分かったとしている。
これらの知見について研究チームでは、インターネット依存問題を持つ子供の発達特性を評価することの重要性を示唆したものであり、発達特性に関連した困難にアプローチすることが子供のインターネット依存を改善したり、その発生を予防したりすることに役立つ可能性があるとしており、今後も調査を続け、子供のこころの問題の発生メカニズムを明らかにしていきたいとしている。