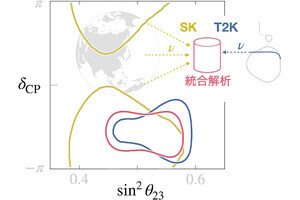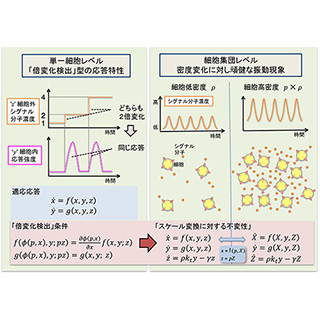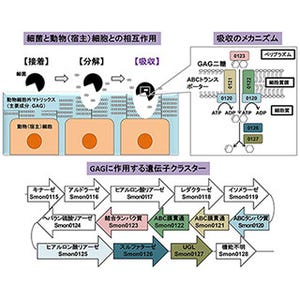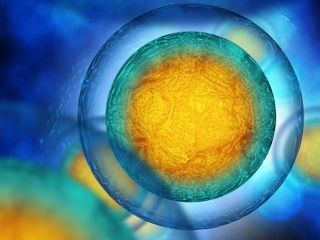筑波大学は、カビの有用性と病原性を特徴付ける菌糸の伸びる仕組みを、超解像顕微鏡注を含む蛍光イメージング技術により明らかにしたと発表した。

|
カビ(糸状菌)は大量の酵素を分泌し、菌糸を伸ばし続けることで成長する。同研究では、カビが伸びる仕組みを解明した。周期的なCa2+の一時的な流入が、アクチン重合とエキソサイトーシスを同調させることで、周期的・段階的に細胞を徐々に伸ばし続けている。 |
同研究は、筑波大学生命環境系国際テニュアトラックの竹下典男助教(研究実施時、ドイツのカールスルーエ工科大学 応用微生物学科グループリーダー兼任)、カールスルーエ工科大学応用微生物学科のReinhard Fischer教授、同大学応用物理学科のUlrich Nienhaus教授、筑波大学生命環境系の高谷直樹教授らの研究グループによるもので、同研究の成果は、米国東部時間5月15日に米国科学アカデミー紀要(PNAS)オンライン版で公開された。
カビ(糸状菌)を構成している糸状の菌糸は、その先端を伸長させることで成長している。一般に細胞は、均一な球体ではなく不均等な形状をしているが、これは細胞の極性と呼ばれており、極性に従った成長により、機能に適した細胞の形が作られる。カビの菌糸は常に極性をその先端に維持して伸びることから、極性と細胞の形との関わりを解析するのに適したモデルだという。また、カビの高い酵素分泌能や病原性は、菌糸の生育と密接に関連しているため、菌糸が伸び続ける仕組みの解明を目指したということだ。
同研究では、古くから遺伝学の研究対象とされ、分子生物学的手法が整備されたカビ(糸状菌)のモデル生物であるAspergillus nidulans(アスペルギルス ニドゥランス)を用いて、菌糸が伸びる仕組みを解析した。解析によると、菌糸細胞が伸びるために必要な膜の成分やタンパク質は、菌糸先端から合成されるアクチンケーブルに沿った分泌小胞の輸送によって、菌糸先端に供給される。重合化したアクチン、分泌小胞をそれぞれ緑色または赤色蛍光タンパク質で標識し、蛍光顕微鏡で経時的にライブイメージングを行った結果、それぞれの蛍光が菌糸先端で同調して強弱の変化を示した。また、細胞内のカルシウムイオン(Ca2+)を、バイオマーカーであるR-GECOにより可視化することに成功し、カルシウムチャンネル依存的に、細胞内Ca2+の濃度の一時的な増加が周期的に観察された。さらに、Ca2+の流入と菌糸先端におけるアクチン重合と分泌小胞量の増減が、同調して周期的に起きることが明らかとなった。
以上の結果から、菌糸の伸長速度は一定ではなく、早い遅いを周期的に繰り返すことが示された。菌糸伸長が遅い期間、つまり分泌小胞のタンパク質などが細胞外へ放出される"エキソサイトーシス"の活性が低い時は、菌糸先端でアクチンが重合化し、分泌小胞が蓄積する。細胞内のCa2+濃度が上昇すると、菌糸先端のアクチンの脱重合や、分泌小胞と細胞膜の融合が促され、結果的に、エキソサイトーシス活性が上昇し、菌糸が早く伸長するようになる。菌糸が早く伸長した後は、分泌小胞量が減少し、再び菌糸の伸長速度が低下。その後、再びアクチンが重合化し、分泌小胞が蓄積することにより、サイクルが進行すると考えられるということだ。このような周期的・段階的な細胞伸長は、化学・物理的な細胞内外の刺激により素早く応答し、対応することを可能にするという生物学的な意義が考えられているということだ。
今後の展開としては、カビの伸びる仕組みを理解しその制御が可能となれば、醸造・発酵食品分野での品質向上、抗生物質・有用酵素生産などのバイオ産業分野での生産量の向上、バイオマスを利用したバイオエネルギー分野の発展、農業・医学分野における農薬・抗菌剤の開発など、カビが関わる全ての幅広い分野に貢献することが期待されているということだ。