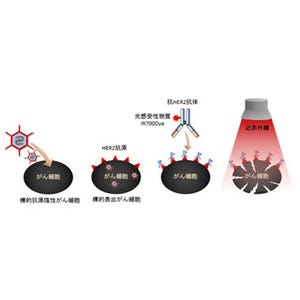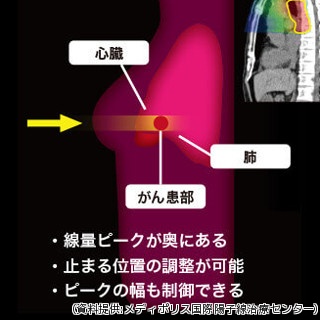期待できる治療効果と注意すべき副作用
治療効果についてはどの程度まで期待できるだろうか? 皮膚がん(悪性黒色腫)のデータを見てみよう。最初に開発された抗CTLA-4抗体は、3週おきに4回投与(点滴静脈注射)までと使用回数に制限があり、限られた患者ではあるものの、明らかなメリットが確認できた。
「これまで進行期の悪性黒色腫では、抗がん剤を使っても、中央値で通常8カ月~1年程度の生存期間とされ、5年生存率がほとんど認められなかった状況が、抗CTLA-4抗体を投与された患者さんでは3年生存率が約21%であり、その後10年たってもこの生存率にほとんど変わりはなく、この薬剤に相性のいい一部の患者さんについては飛躍的に生存期間が伸びていると考えられます(イピリムマブ)。現時点では、このように免疫チェックポイント阻害剤によって長期的に生存曲線が横ばいになるという報告は、進行期の悪性黒色腫に限られた話ではありますが、もしかすると長期生存されている患者さんの中には完治する方も出てくるかもしれません」と北野氏。
興味深いことに、ごく一部の症例だけに限られるものの、いったん腫瘍が大きくなったあとで効果が出始めるという、「遅発性の効果」が認められる点もこの薬剤に特徴的である。また、患者自身の免疫を高めることによって働くため、がんの種類を問わず効果が見込める可能性がある点も挙げられる。
さらに、多くのがん種で有効性が示されている抗PD-1抗体(ニボルマブ)は、悪性黒色腫に続いて、他のがん種にも適応が広がってきており、すでに2015年12月には非小細胞肺がんに対して国内承認を得ており、進行期の悪性黒色腫に対して直接比較で抗PD-1抗体が抗CTLA-4抗体よりも高い臨床効果が報告されたため、免疫チェックポイント阻害剤の主役となっている。
まさに期待の治療法だが、やはり、薬との相性の問題は避けられず、治療効果の有無や副作用についてもしっかり理解しておきたい。
「免疫チェックポイント阻害薬は理論上、がん(抗原)と戦っているリンパ球(T細胞等)を選択的に活性化させるので、その他のがんと戦わないリンパ球にはほとんど関与しません。したがって、抗がん剤と比べて副作用の頻度は少ないのですが、患者さんの中には免疫のブレーキを解除するという性質から誤って自分自身の細胞を認識して攻撃してしまうことがあり、副作用がいつどこにどの程度起こるかは現時点では予測できません。この点は副作用のパターンをある程度予測できる抗がん剤との違いで注意が必要です」(北野氏)
免疫療法という言葉から「身体に優しい治療法」のイメージをなんとなくもつ人が少なくない。しかし、人間の免疫機能は千差万別なだけに、副作用の出方には個人差があり、事前予測が難しい側面があるといえるだろう。多くの場合、副作用はほとんど出ないか、軽微なことが多いが、まれに重篤化する例もあるので、免疫療法を安全なものとして盲信する態度は避けたいものである。特に、内分泌障害(下垂体不全、副腎不全など)、重症筋無力症、劇症1型糖尿病などが発症して全身状態が悪化するケースも報告されており、注意が必要だ。
適応対象拡大への期待
世界中で研究・臨床試験が進められている免疫チェックポイント阻害療法は、「現在、腎細胞がん、膀胱がん、頭頸部がん、胃がん、食道がん、卵巣がんなどの進行がんについて第3相臨床試験が行われています。また、早期の臨床試験では、悪性リンパ腫などで高い奏効率が示されています。今後、適応の対象が拡大していくことが期待されます」と北野氏。
免疫チェックポイント阻害療法の開発は、1990年代から積み重ねられてきた基礎免疫学の知見をベースに、2000年代から盛んになった。その動きを間近に見つめてきた医師の一人が北野氏だ。数々の貴重な出会いから免疫チェックポイント阻害療法の研究に取り組む。
「がん免疫療法といえば、長年にわたって科学的にデザインされた客観的な臨床試験の結果が示されることがなかったため、世間から懐疑的に見られる時代が長く続きました。免疫チェックポイント阻害剤の登場によってようやく誰が見ても本物だと思える薬が登場し、世界的にも注目を集めるようになりました。臨床医たちも手ごたえを感じています」(北野氏)
免疫チェックポイント阻害療法をはじめとするがん免疫療法が抱く夢は、北野氏の夢でもある。