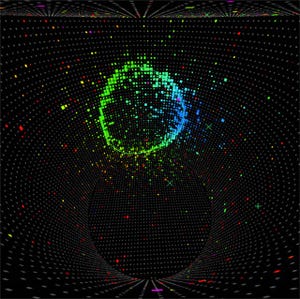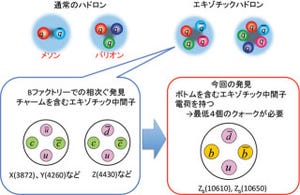理化学研究所(理研)は11月20日、原子より小さい極微スケールで起こるK中間子崩壊における「CP対称性の破れ」のスーパーコンピュータ(スパコン)を用いた計算に成功したと発表した。
同成果は、理研 仁科加速器研究センター 理研BNL研究センター計算物理研究グループの出渕卓グループリーダー、クリストファー・ケリー理研BNLセンター研究員らと、ブルックヘブン国立研究所、コロンビア大学、コネチカット大学、エジンバラ大学、プリマス大学、サウサンプトン大学らで構成される国際共同研究グループによるもの。詳細は米国の科学雑誌「Physical Review Letters」に掲載された。
CP対称性の破れは1964年に初めて実験的に観測され、その後、2000年までに欧州原子核研究所(CERN)と米国のフェルミ国立研究所にて、「中性K中間子が直接的にCP対称性を破り、アップクォークとダウンクォークから成るπ中間子に崩壊する現象」が観測されていた。この結果と、小林・益川理論に基づく理論計算の比較が求められていたが、小林・益川理論は日本の高エネルギー加速器研究機構(KEK)や米国のSLAC国立加速器研究所のB中間子の崩壊実験で検証されていたが、K中間子の崩壊過程の理論的な計算は技術上の困難があり今まで不可能であった。
今回研究グループは、中性K中間子が2つのπ中間子に崩壊する格子量子色力学に基づく大規模数値計算を行ったという。具体的には、自然界ではK中間子の崩壊により、2つのπ中間子が互いに反対方向の運動量を持つが、それをこれまで計算機上で実現する方法がなく、正確な計算ができなかったが今回、計算機上に表した空間格子の境界条件に工夫を加えることで、K中間子が自然界と同じ運動量を持ったπ中間子へ崩壊する状況を実現したとするほか、クォークの運動方程式の解法を大幅に高速化するアルゴリズムを導入し、計算効率を高めたという。
これらをもとに、実際に、理研BNL研究センター、ブルックヘブン国立研究所、アルゴンヌ国立研究所、エジンバラ大学に設置されたスパコン「IBM Blue Gene/Q」を用いて、標準的なノートPCで2000年分の計算量に相当するとされる大規模格子量子色力学計算を行い、小林・益川理論と素粒子の標準理論から導き出されるCP対称性の破れのサイズを計算で示し、実験結果との比較を可能にしたとする。
なお、研究グループは今回の理論計算について、実験結果との比較をするにあたって最終的な結論を出すための精度がまだ不足しているとしているものの、直接的なCP対称性の破れの理論計算が可能であることが証明されたとしており、米国で開発が進められている次世代スパコンを用いることで、より高い計算精度を得られるのではないかとしている。