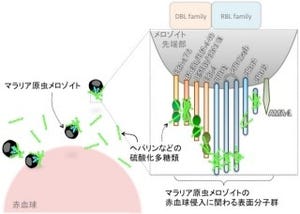大阪大学(阪大)は、脳マラリアの新たな診断と治療のターゲットを発見したと発表した。
同成果は、同大免疫学フロンティア研究センター(IFReC)マラリア免疫学研究室のCevayir Coban准教授らによるもの。詳細は「Cell Host & Microbe」に掲載された。
脳マラリアはマラリアの中でも致命的な合併症であり、血液脳関門(BBB)に破壊、脳の免疫異常に起因して生じると考えられているが、症状が起こる前の最初の現象はわかっておらず、早期診断が困難なため、早期の迅速かつ安価な診断法の確立が求められていた。
今回の研究では、11.7TのMRIおよび多光子顕微鏡法(2光子)を組み合わせることで、脳マラリアにおける脳の組織内で起こるマラリア原虫と免疫細胞の攻防の可視化に挑んだ。具体的には、マウスマラリアのモデルを用いて、マラリア感染後の脳全体をMRIで撮影し、その変化を解析。その結果、嗅覚を司るといわれる「嗅球」に、今まで観察されなかった微細な点状の変化が5~6日目に生じることを確認したという。
さらに2光子顕微鏡を用いてマラリア原虫や免疫細胞の観察を行ったところ、嗅球の微細な血管をマラリア原虫が走り回り、いくつかのマラリア原虫が血管にとどまるような様子が観察されたほか、同じ部位で免疫細胞、特にT細胞の存在も確認すると同時に血管が破れて出血する瞬間を撮影することに成功したという。
この結果について研究チームでは、これまでの考え方を覆す成果であることから、さらなる研究として、嗅球において機能的に障害を受ける状態を定量的に計測する診断法であるburied food testを行って計測したところ、感染赤血球移入後3~4日目に、明らかな嗅覚異常を確認したとのことで、この結果から、嗅覚の簡単なテストを行うことにより、脳マラリアの早期診断の可能性が示されたと説明している。