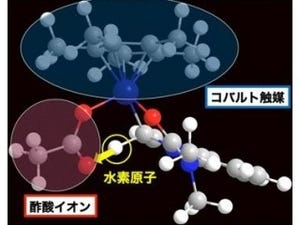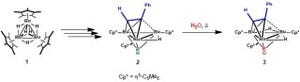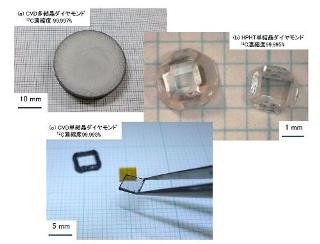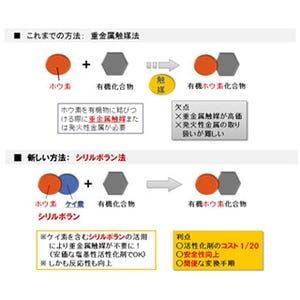東京工業大学(東工大)は5月14日、東京大学との共同研究により、芳香環のみが置換した「結合の手を2本しか持たないホウ素のカチオン化合物」である「ボリニウムイオン」の合成に成功したと発表した。
成果は、東工大 資源化学研究所の庄子良晃 助教、同・福島孝典 教授、東大大学院 薬学系研究科の内山真伸 教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、5月11日付けで英科学誌「Nature Chemistry」電子版に掲載された。
「ホウ素化合物」の性質や反応性は、その電子不足性とホウ素の低い電気陰性度に特徴づけられる。最も典型的なホウ素化合物は、「中性三配位構造」の「ボラン」(水素化ホウ素の総称)だ(画像1)。この状態では、ホウ素は結合の手を3本持っている。この時、ホウ素の電子の軌道には空(電子が存在しない)の「2p軌道」が存在し、ここに「電子対」(軌道を占有する2つの電子)を受け取ることでホウ素は原子として安定化する。すなわち、中性三配位のホウ素化合物は「ルイス酸」(電子対を受け取る物質のこと)として振る舞うというわけだ。このようなボランの反応性は、化学種が「構成する典型元素の価電子の数が8個になるように反応する」という経験則による、化学の基本原理である「オクテット則」により説明することが可能だ(主に、第二周期の典型元素に適用される)。
そしてこの3本の結合の手を持つボランに対し、結合の手を1本取り去ったホウ素のカチオン化合物が、ボリニウムイオンである(画像1)。これまで芳香環のみが置換したボリニウムイオンは安定に存在しないとされてきたが、研究チームは今回、その単離に挑んだ。

|
|
画像1。中性ボラン(左)とボリニウムイオン(右)の構造。ホウ素原子の上下のローブは、空の2p軌道を表す |
研究チームは今回、ボリニウムイオンのデザイン戦略として、まず、ホウ素上の置換基として適度な「立体障害」を持つ芳香環であるメシチル基「2,4,6-トリメチルフェニル基」を用いること、そして対「アニオン」として化学的に安定なアニオン種を用いることによって、芳香環のみが置換したボリニウムイオンの単離に成功した。なお立体障害とは、立体的な「嵩(かさ)高さ」のことをいう。立体障害の大きい置換基が導入された部位は、ほかの分子と反応しにくくなるのである。
ボリニウムイオンの詳細な分子構造は、各種分光分析に加え、単結晶X線構造解析により解明された(画像2)。このボリニウムイオンは熱的に極めて安定であり、「カルボラン塩」の場合、結晶試料を300℃程度まで加熱しても分解しないという。
また、実験結果と理論化学計算の比較により、溶液、固体状態のいずれにおいても、ボリニウムイオンのホウ素中心は対アニオンや溶媒の配位を受けていないことが明らかにされた。さらに、理論化学計算の結果、ボリニウムイオンの「最低非占有軌道」のエネルギー準位は、既存のホウ素化合物のものと比較して低い「-5.41eV」と算出された。以上の検討結果は、今回、合成したボリニウムイオンが熱力学的に安定でありつつも、同時に極めて高いルイス酸性を有していることを示しているとする。なお最低非占有軌道とは、電子によって占有されていない分子軌道の内、最もエネルギーの低い軌道のことをいう。ほかの分子から電子対を受け取る反応などは、この最低非占有軌道が関わる。
このボリニウムイオンの高い反応性を示す結果として、特異な二酸化炭素の活性化反応も見出された。ボリニウムイオンの溶液に二酸化炭素ガスを混合すると、二酸化炭素の炭素原子にボリニウムイオンの「メシチル基」が移り、かつ酸素を1つ失ったカチオン化合物が速やかに生成されたのである(画像3)。すなわちこの反応では、二酸化炭素の酸素原子がホウ素により奪われているというわけだ。
この特異な反応は、強いルイス酸中心であるボリニウムイオンのホウ素原子が、二酸化炭素の酸素原子に配位することから進行すると考えられるという。実際、理論化学計算による考察では、この反応機構がエネルギー的に妥当であることが示されたとした。
この反応は、一般的に「求核剤」を用いて行われる二酸化炭素の活性化反応とはまったく異なるという。ボリニウムイオンを利用することで、今後、さまざまな基質をターゲットとしたユニークな分子活性化が可能になると期待できるとした。ちなみに求核剤とは、化学反応において電子密度が低い原子と反応する化学種のことをいう。二酸化炭素との反応であれば、求核剤は電子密度が最も低い炭素原子に対して反応し(求核攻撃)、結合を生成するという仕組みだ。
今回の研究により、芳香環のみが置換したボリニウムイオンの単離が可能であることが実証され、またボリニウムイオンの特異な反応性も明らかになったわけだが、研究チームは今後、ホウ素上の置換基としてさまざまな「アリール基」や「アルキル基」を導入することで、「単離可能な究極のルイス酸分子」の創製を目指すという。またこれらの研究を推進することで、新たな「超ルイス酸分子化学」の開拓に取り組むとした。