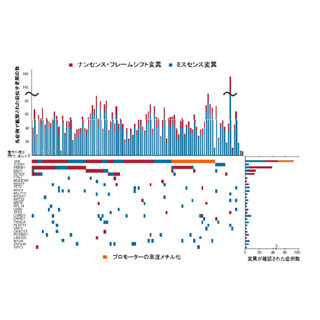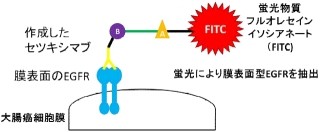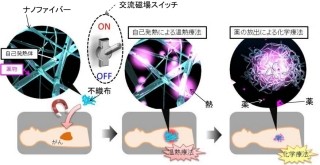がん研究会は、マウスを用いた実験から、肥満になると2次胆汁酸を産生する腸内細菌が増加し、体内の2次胆汁酸の量が増え、これにより肝臓の肝星細胞が細胞老化を起こすこと、ならびに細胞老化を起こした肝星細胞は、発がん促進作用を有する炎症性サイトカインを含む細胞老化関連分泌因子(SASP因子)を分泌することで、周囲に存在する肝細胞のがん化を促進することを明らかにしたと発表した。
同成果はがん研究会 がん研究所 がん生物部の大谷直子 主任研究員、同 原英二 部長らによるもの。詳細は英国の科学雑誌「Nature」オンライン版に掲載された。
近年の研究から、肥満は糖尿病や心筋梗塞のリスクを高めるだけでなく、がんの発症率を高めることも明らかになってきており、肥満抑制の必要性が求められるようになってきた。
これまでの研究から、正常細胞に発がんの危険性があるストレスが生じると、細胞老化が起こり、細胞増殖が不可逆的に停止することが知られている。また近年の研究から、細胞老化を起こした細胞は次第に細胞老化関連分泌因子(SASP因子)を分泌するようになることで、周囲の細胞に炎症反応や発がんを促進することが明らかとなってきており、研究グループではこれらの報告から、肥満に伴う発がんに細胞老化が関与しているのではないかと考え、マウスの生体内で細胞老化反応をリアルタイムに可視化できるシステムを開発し、肥満により細胞老化が誘導されるかどうかについての検討を行った。
その結果、低濃度の化学発がん物質で処理後、高脂肪食を30週間与えてマウスを肥満させたところ、すべてのマウスで肝臓に細胞老化反応が起こると同時に肝がん(hepatocellular carcinoma:HCC)を発症するようになったが、普通食を与えた肥満していないマウスでは細胞老化反応も肝がんの発症も見られないことが確認され、これにより、肥満により細胞老化反応と肝がん発症の両方が促進されることが明らかになったという。
また、免疫組織染色法により肥満したマウスでは、肝臓の間質の細胞の1つである肝星細胞が細胞老化を起こしていたことが確認された。さらに、細胞老化関連分泌因子(SASP因子)を分泌していることが見出されたほか、細胞老化関連分泌因子(SASP因子)の主要因子であり炎症性サイトカインの1つであるIL-1βの遺伝子を欠損したノックアウトマウスでは肥満による肝がんの発症率が低下することも判明。同様の結果は薬剤を用いて肥満したマウスの肝星細胞を除去した場合にも見られたことから、肥満により細胞老化を起こした肝星細胞が細胞老化関連分泌因子(SASP因子)を介して周囲に存在する肝細胞のがん化を促進していることが判明したとする。
そこで、肥満により肝星細胞が細胞老化を起こすメカニズムの解明に向け、肥満に伴うさまざまな生体変化を解析したところ、肥満したマウスでは1次胆汁酸をもとに2次胆汁酸を合成する腸内細菌が増加していることが判明したほか、肥満マウスに抗生物質を投与して2次胆汁酸産生菌を死滅させたところ、細胞老化を起こした肝星細胞の数が減少し、肝がんの発症率も低下することが確認されたという。また、その際に人工的に合成した2次胆汁酸を同時に投与すしたところ、抗生物質による肝がん発症率の低下が見られなくなることも確認したという。
これらの結果、肥満により増加した腸内細菌が産生する2次胆汁酸が門脈を通して肝臓に運ばれ、肝星細胞に細胞老化を起こし、細胞老化関連分泌因子(SASP因子)を分泌するようになることで肝細胞のがん化が促進されたことが示されたとする。
さらに研究グループでは、これらマウスで得られた研究結果がヒトにも当てはまるかどうか調べるために、臨床サンプルを用いた解析を実施。具体的には、ヒトの場合、肥満に伴い発症する非アルコール性脂肪性肝炎(Non-alcoholic steatohepatitis:NASH)が肝がんへと移行することが知られていることから、がん研有明病院で手術を受けた患者の中から、BMIが25以上でNASH肝がんと診断された肝がん切除サンプルを用いて検討が行われた結果、約3割で肝星細胞に細胞老化および細胞老化関連分泌因子(SASP因子)の発現が認められたとのことで、ヒトにおいても少なくとも一部のNASH肝がんにおいては同様のメカニズムが働いていることが示されたとしている。
なお、研究グループでは今回の成果をもとに今後、ヒトの糞便中に含まれる2次胆汁酸産生菌の量を測定することで、肝がんの発症リスクを予想できるようになる可能性が考えられるとするほか、2次胆汁酸産生菌の増殖を抑制する薬剤または、食品添加物を開発することで肥満に伴う肝がんの発症を予防できる可能性もでてくるとしている。