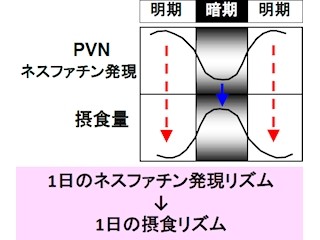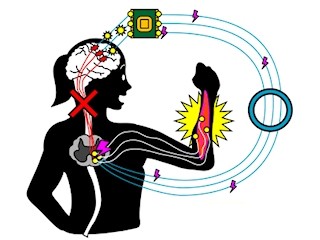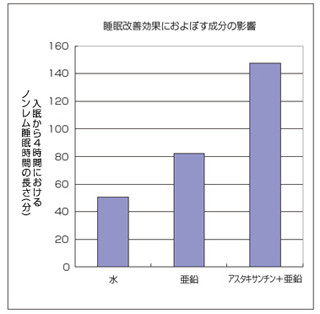協同乳業は4月23日、腸内常在菌が大脳の代謝系に影響を与えていることを代謝産物レベルで明らかにしたと発表した。
同成果は同社研究所技術開発室の松本光晴 主任研究員(理化学研究所イノベーション推進センター辨野特別研究室)、同 澤木笑美子氏、理化学研究所イノベーション推進センター辨野特別研究室の木邊量子氏、同 辨野義己氏、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT)の大賀拓史氏、東海大学医学部基礎医学系感染症研究室の相場勇志氏、同 古賀泰裕氏らによるもの。詳細は「Frontiers in Systems Neuroscience」に掲載された。
腸内常在菌は人の健康、特に免疫系疾患や大腸ガンとの関与が知られているほか、近年では、肥満や寿命など大腸内環境と直接的に接していない全身系への影響も報告されるようになってきた。脳との関連も報告されるようになってきており、腸と脳は、神経系やホルモン、サイトカインなどの共通の情報伝達物質と受容体を介し、双方向的なネットワーク「腸脳相関」を形成していることが分かってきたほか、最近の研究から、腸脳相関の腸管側刺激因子と腸内常在菌が強く関わっていることも明らかとなり、神経発達障害や脳の発達と行動にも腸内細菌叢が影響することが報告されている。
しかし、神経伝達物質以外の脳内代謝系への影響を調べた研究は少なく、未だ解明されていないことから、今回、研究グループでは、脳内代謝物の網羅的解析を行うことで、腸内常在菌が大脳に与える影響の調査を行った。
具体的には、同じ両親から生まれた雄マウスを無菌マウスと通常菌叢マウスの2グループに分けて飼育し、7週齢で安楽死後、ただちに大脳皮質に対し、広範囲の成分を分離・分析することが可能なCE-TOFMSを用い、脳内代謝物のメタボロミクスにて網羅的解析を行ったという。
この結果、大脳皮質から196の代謝産物が検出され、中でも23成分は無菌マウスの方が通常菌叢マウスより濃度が高かったことが確認され、その中に、行動と関連深い神経伝達物質「ドーパミン」、統合失調症との関連性が示されているアミノ酸「セリン」、多発硬化症やアルツハイマーとの関連性が知られる「N-アセチルアスパラギン酸」が含まれていることが判明した。
また、23成分中には解糖系中間代謝産物や補酵素NADH、NADP+とエネルギー代謝に関連する成分も含まれており、大脳のエネルギー消費にも腸内常在菌が影響していること、つまり腸内常在菌が宿主の思考や行動にも影響している可能性が示唆されたという。
一方、無菌マウスの方が通常菌叢マウスより濃度が低かったのは15成分で、中には、神経伝達物質の前駆物質である芳香族アミノ酸(トリプトファン、チロシン、フェニルアラニン)や、てんかんとの関連性が示唆されている「ピペコリン酸」、乳児の脳発達に関与していると考えられている「N-アセチルノイラミン酸」などが含まれていることが確認されたという。
なお、研究グループでは、今回の結果、腸内常在菌が大脳の代謝系に大きな影響を与えていることを示すもので、脳の健康、疾病、発達および衰弱、さらにヒトを含めたほ乳類の学習、記憶および行動の研究において重要な基礎的知見となるものとなると説明している。