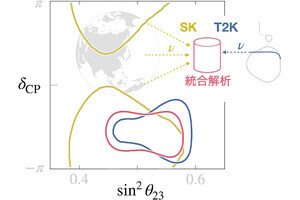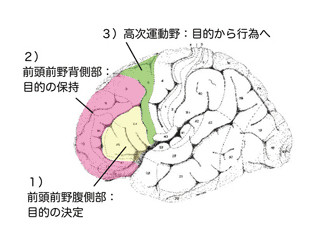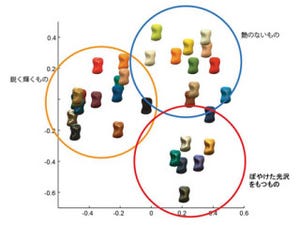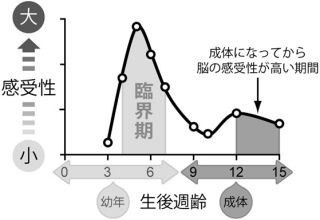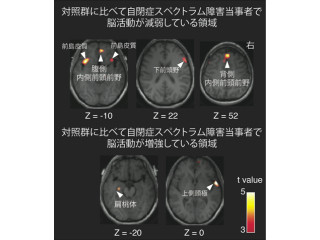東京大学は10月10日、周辺が動いていると静止図形が反対方向に動いて見えるという「誘導運動錯覚」を体験している際の実験参加者の大脳皮質の活動をfMRIを利用して記録し、誘導運動の神経相関を同定したと発表した。
成果は、東大大学院 総合文化研究科の竹村浩昌博士研究員(日本学術振興会特別研究員)、同・村上郁也准教授、京都大学大学院 文学研究科の蘆田宏准教授、東大大学院 新領域創成科学研究科の天野薫特任研究員、立命館大学文学部の北岡明佳教授らの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、10月10日付けで脳科学の学術誌「The Journal of Neuroscience」オンライン版に掲載された。
ヒトは物を見るとき、対象物だけでなく周りにあるものとの関係を計算に入れて、その物を含む世界を心の中に構築している。これを「文脈効果」という。ヒトの感覚システムは、空間的文脈、時間的文脈を巧妙に計算に入れて、外の世界の様子を心の中に構築する作業を行っているのだ。
空間的文脈の例を1つ挙げると、「明るさの同時対比」という心理現象がある。明るさの同時対比とは、例えば同じ灰色でも、白背景に置くと暗く見え、黒背景に置くと明るく見えるという、誰にでも経験した記憶があるものだ。
また、視覚運動に関しても同様な錯覚現象があり、止まっている図形でも、右に動く背景に置くと左に動いて見えるなど、周辺が動いていればそれと反対方向に動いて見え、これが誘導運動である。
誘導運動には視野のある点とその近傍との間の運動の違いに感受性を持つ神経細胞が関与していると考えられるが、誘導運動に関して心理現象と脳活動を直接対応させた研究例はこれまでなかった。
誘導運動は錯覚の1つではあるが、この現象に通底する視覚機能としては、大きな背景の中に1つほかとは異なる動きをしている対象を抜き出してそれを1つの物体として認識するという、生体にとっての基本的な情報処理が考えられ、この誘導運動錯覚を解明し神経対応を同定することで、視覚系の機能解明の本質に迫ることができるのである。
この問題意識から、研究グループはfMRI実験により、誘導運動錯覚を体験している際の実験参加者の大脳皮質の活動を記録して、誘導運動の神経相関、すなわち見かけ上の動きのあるなしに応じて活動量が増減するような場所が存在するかを調べる研究プロジェクトを実施した。
実験では、中心部と周辺部からなる同心円領域に視覚刺激図形を提示。周辺部には、一定の速度で運動するランダムノイズ画像、中心部には白黒のストライプ模様が提示された。
もう少し詳しく説明すると、ランダム画像はすべての画素が無作為に白または黒の強度になっているような画像だ。実験では、そのような画像を生成し、空間的にぼかしてから、画像のパターン全体を一定速度で周辺部内部で動かした。周辺部というドーナツ型領域の窓の中で、パターン全体が滑るように定速で動いているというイメージだ。
fMRI実験に先立ち、実験参加者ごとに、中心部に生じる誘導運動の強さを知覚実験で測定。中心部が物理的に静止していると、誘導運動が生じて、運動している周辺部と反対方向に動いて見える。
これを見かけ上打ち消して、主観的には静止して見えるようにするために、中心部をわざと誘導運動と逆方向に少し動かす。そうしてちょうど動きが打ち消される時の物理的速度を、誘導運動の「相殺速度」とした。
そしてfMRI実験は、中心部のストライプ模様をこの「相殺速度」を含め、周辺部と同方向に動く、逆方向に動く、静止しているなどいくつかの条件を設定して実施(画像)。ちなみに実験参加者は、単に画面中央の固視点を注意深くじっと見つめて行われた。
これらの仕組みは、fMRIで脳活動の指標とする「BOLD(blood-oxygenation-level-dependent)信号変化率」が、物理的運動速度と相関するのか、主観的運動速度と相関するのか、中心部と周辺部の相対運動と相関するのかを切り分けるために必要だったからだ。
なおBOLD信号とは、血中のヘモグロビンの酸素化の度合いによって、信号強度に違いが出てくるのが特徴。活動している脳部位には酸素を多く含む血液が過剰に供給されるという神経・血管カップリングという生体現象を利用しており、脳活動の活性化の度合いを間接的ではあるが測定できるのである。
こうしたfMRI実験の結果、運動図形を提示した時に脳活動が高まる部位を同定することに成功したというわけだ。特に、ヒトで視覚運動の処理に中心的に関与しているとされる大脳皮質領域の「hMT+領域」という場所で顕著な応答特性が見られた。
そして結果だが、周辺部と中心部が逆方向に動き中心刺激の知覚速度が最大になる条件の場合が、脳活動が最も大きくなることを確認。また、中心部が主観的に静止して見える「相殺速度」で動いている条件において脳活動が最も小さくなったことから、誘導運動知覚との対応が見られた。先の問題切り分けの言葉でいえば、「主観的運動速度と相関する」が答えだったのである。
この傾向は、大脳皮質一次視覚野の「V1野」といった低次の領野ではなく、高次の領野であるhMT+領域において最も顕著に見られた。この結果は、hMT+領域と主観的な誘導運動の知覚が関連すること、背景の中から運動する対象だけを抜き出す計算をする上でhMT+領域が重要な役割を果たしていることを示唆するものだ。
村上准教授の研究室ではこの実験に先立ち、縦方向の誘導運動錯覚を生じることによって、中心部に与えた非常に遅い運動図形が左に動いているか右に動いているかがむしろ見やすくなる、感度が増強するという現象を発見している。
今回の成果によって、機能的脳イメージング実験で誘導運動の神経相関がhMT+領域にあることがわかり、心理現象としての誘導運動やそれに伴う感度増強の詳細な解明と共に、それを下支えする神経基盤の解明にも道が拓けた形だ。
このことから、光学的特性によって視力増強の補助をする虫メガネと同じ論理で、知覚心理学的特性によってものの見えやすさを増強する補助をする「錯視メガネ」のような技術開発にも、将来的につながることが期待されるという。
さらに、健常者に比べて感度の低下で苦しむ視覚弱者に対して、心理学の力で感度改善を将来的に実現できることが、今回の研究成果の社会的意義として望まれるとした。
研究グループは、今後の研究の進展によって、視覚運動以外の領域においても空間的文脈の知覚心理学的特性および関連する脳活動の解明でさまざまな発展が期待されるとコメントしている。