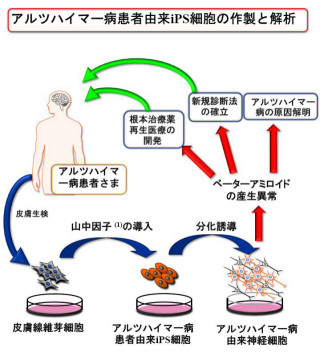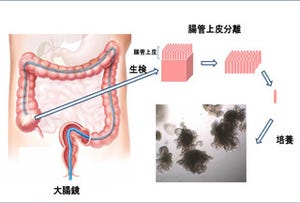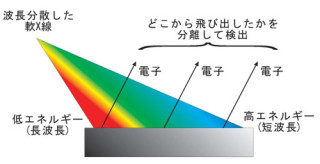慶應義塾大学などで構成される研究チームは、細胞内小器官などで自然に作り出される混雑した複雑な環境が、細胞の環境変化に対する強さ(頑健性)を産み出すことを実験により示すことに成功した。
同成果は、広井賀子氏(慶應義塾大学理工学部助教)、James Lu氏(スイス連邦工科大学博士研究員)、伊庭啓介氏(慶應義塾大学理工学研究科修士課程2年)、田平章人氏(慶應義塾大学理工学研究科修士課程2年)、山下修二氏(慶應義塾大学医学部専任講師)、岡田保典氏(慶應義塾大学医学部教授)、Christoph Flamm氏(ウィーン大学理論化学研究所准教授)、岡浩太郎氏(慶應義塾大学理工学部教授)、Gottfried Kohler氏(ウィーン大学マックスペルーツ研究所教授)、舟橋啓氏(慶應義塾大学理工学部准教授)らによるもので、スイス連邦の科学誌「Frontiers in Systems Physiology」に掲載された。
頑健性を産み出す要素は2つあり、1つは細胞内で、拡散を基礎とする動きをもつ分子が関わる反応の速度を、反応の始まりの時期に促進する性質(細胞が外界に素早く応答する性質)、もう1つは反応開始後の時間経過に伴う分子の枯渇を遅らせる性質(外界からの次の信号に備える性質)だ。今回の実験では、生理的な細胞内環境が、ブラウン粒子の自己組織化によって形成されるフラクタル構造と同等の性質を持つことで、細胞内で次々に起きる生化学反応の、いわば「危機管理」に役立つ機構を備えている可能性を示したもので、先の2要素的性質は、これまでにも理論上のフラクタル構造について証明が行われて来たが、生理的な細胞内環境に備わる性質として、実験によりその役割と共に提示されたのは、今回が初めてだという。
1980年代、自然界に潜むさまざまなフラクタル構造の発見、調査が進み、その際の理論的解析で、ブラウン粒子の自己組織化によって形成されたフラクタル構造のいくつかが、別の理論課題である、パーコレーション問題における構造上の条件を満たすことが分かり、こうした構造が、ブラウン粒子の拡散速度を時間依存的に変化させることが明らかになった。しかし、この理論的解析結果と、動物の生体組織構造や細胞内高分子構造など多くの自然界の構造がフラクタル様の構造を持っていることの、互いの密接な関係については、可能性が想像されながらも、これまで具体的な証明がなされないままであった。
今回の研究では、まず、細胞構成成分に関する一般的生化学的知見と細胞生物学的知見を基礎として、細胞内小器官の集団が創りだす環境におけるフラクタル様の構造の有無や形状、種類を分析した。同時に、実験により、細胞内での球状タンパク質の拡散速度を調べ、その拡散が時間依存的に遅くなる異常拡散にあたるかどうか、ならびに異常拡散の程度を調べた。
次に、これら2つの実験分析から得られた構造の情報と拡散速度の情報を用いた計算で、同等の構造で理論的に起こることが示されている分子動態が出現することを確認したほか、コンピュータ上で細胞内環境を再構成するシミュレーションを実行し、生理的な環境として想定している混雑度で作りだした複雑な環境を、シミュレーション条件として設定した場合には、実験結果から計算された分子動態と同等の分子動態が予想された。
結果として、理論予測、実験観測結果、コンピュータシミュレーションによる再構築計算の3つが、1つの結論 - 生化学反応環境が、ある混雑度で、一様でない複雑な構造を持つ場合、反応の始まりの時期には反応速度が促進され、反応開始後の時間経過に伴う反応分子の枯渇は遅くなる - が確認されることとなった。
こうした性質の生理的な意義を考えると、細胞が外界の変化や外界からの信号に素早い初期応答を行うことを可能にし、同時に、長く一定の環境に置かれた後の急激な変化にも耐えられるよう、新しい環境への備えをし続けることができる仕組みであると考えられます。いわば危機管理メカニズムの1つとして作用し、生命特有の性質とされる、環境の変化に対する恒常性、頑健性機構の一つとして存在しているとみなすことができるという。
なお、今回の実験では、細胞がこの混雑した複雑な構造を持ち合わせており、特に分子の熱運動に基づいて自然発生する構造 - ブラウン粒子の自己組織化によって形成されるフラクタル構造 - とよく似た性質を持つことが示されたことから、この自然に作り上げられた構造が、細胞の危機管理メカニズムとして作用している可能性は、自然界の多くの構造が同様のパターンを持っている背景、特に生体がこのような構造を維持した状態で安定している理由につながる重要な結果であると言えると研究グループでは説明している。