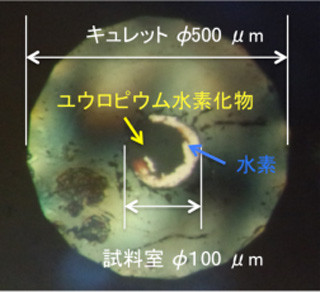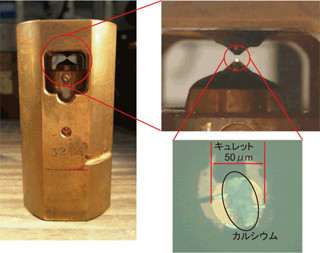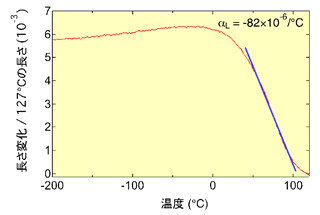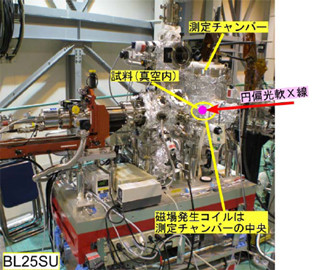物質・材料研究機構(NIMS)の国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA)の冨中悟史研究員と辻本吉廣研究員は、二酸化チタン(TiO2)のナノ構造を保持したまま、内部の結晶構造が異なる還元型酸化物(Ti2O3)へと変化させる合成に成功したことを明らかにした。同成果は、大型放射光施設SPring-8に設置されたNIMSビームステーション「BL15XU」と共同で行い、独化学会の国際誌「Angewante Chemie International Edition」に掲載された。
チタンの還元型酸化物は、電子伝導性や可視光吸収などの魅力的な特性が知られており、ナノ構造を持たせることができれば太陽電池や燃料電池など幅広い応用が期待できるものの、従来の合成法では水素ガス気流中、800~1100℃の高温で還元を行う必要であり、出発原子がナノサイズであっても、粒子が熱による原子拡散により粒子成長してしまうため、ナノ構造を有する材料の合成は困難であった。

|
|
図1 従来の手法と今回の成果で用いられた新手法の比較。従来の高温処理を必要とする手法では、粒子が肥大化してしまい、応用展開が難しくなるが、新手法を用いることで、可視光を吸収するチタン還元型酸化物のナノ粒子の合成に成功した |
今回、研究チームでは、正方晶系のルチル型TiO2のナノ粒子(10~30nm)を、低温で強い還元力を示す水素化カルシウム(CaH2)粉末とともに反応させることにより、これらの課題解決を図った。
ルチル型TiO2とCaH2をよく混合したペレットを真空封入し、従来の還元法よりも350℃で15日間の反応させたところ、試料が還元型チタン酸化物に共通して見られる黒色を呈することが判明した。その試料を大型放射光施設SPring-8のNIMSビームライン(BL15XU)に設置された高分解能放射光粉末X線回折装置を用いて測定を行った結果、出発物質とは明らかに異なる回折パターンが得られ、還元型チタン酸化物のTi2O3(六方晶系)が単相で得られていることが判明した。

|
|
図2 (a)出発物質のルチル型TiO2ナノサイズ粒子、(b)得られた還元型チタン酸化物Ti2O3ナノサイズ粒子の結晶構造、光学顕微鏡写真、透過型顕微鏡写真、(c)中間相と考えられるマグネリ相Ti4O7の結晶構造 |
さらに透過型顕微鏡で粒子の形状を観察したところ、反応前後で粒子の形体とサイズが維持されており、ナノ構造を有する還元型チタン酸化物の合成に成功したことが明らかとなったという。
また、形状が維持されていることの他に興味深い点としては、還元反応前後で正方晶系物質から六方晶系物質へと構造が変化している点が挙げられ、構造を比較してみると、チタン原子と酸素原子からなる骨組みがまったく異なっており、原子の移動を伴っていることが分かる。
一方、同じ化学組成であるTiO2で、しかも同じ正方晶系(結晶構造はルチル型とは異なる)であるアナターゼ型TiO2をCaH2で還元してもTi2O3が得られるが、この場合はナノ構造の形状は維持されず粒子成長が見られた。研究チームでは、この出発物質の違いによるナノ構造への影響の起源を明らかにするために、ルチル型TiO2の還元条件を変化させ、その継時変化の追跡を試みた。350℃で5日間反応させた後の放射光粉末X線測定の結果を見ると、この反応条件でもTi2O3が主成分として生成されるが、そのほかにマグネリ相と呼ばれるTi4O7由来と思われる強度の小さい回折も観測できたという。このTi4O7の構造は、TiO6八面体の稜共有から成るルチル鎖とTi2O3に類似した面共有のTi2O9が連なる層から成っており、このルチル型TiO2と最終生成物Ti2O3の双方の構造的特徴を併せ持ったTi4O7を経由することが、ナノ構造を有するTi2O3の合成の秘訣になっていると考えられるという。

|
|
図3 室温で測定された放射光X線回折パターン。下から出発物質ルチル型TiO2、350℃、5日間還元反応後の生成物質(Ti2O3+Ti4O7)、350℃、15日間還元反応によって得られた還元型チタン酸化物Ti2O3 |
今回開発された手法を用いると、他のチタン酸化物のナノ構造、例えばナノワイヤなどを用いた場合においても、ナノ構造を維持したままの還元反応が達成できるものと考えられ、還元型チタン酸化物の幅広い合成が可能になることが期待できるという。そのため、将来的にはその電子伝導性や可視光吸収特性を活かし、「人工光合成材料への応用」「貴金属フリーの電極材料・配線材料」「燃料電池などの触媒の担体」などへの応用が期待できるとのことで、研究チームでは現在、還元反応機構の詳細や合成したナノ構造を有する還元型チタン酸化物の特性評価を進めているとしている。