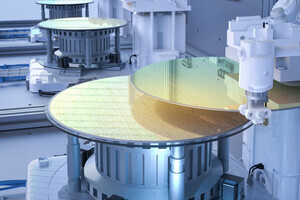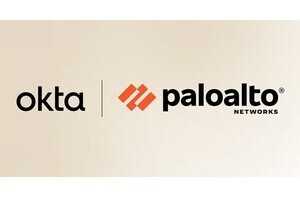タイポグラフィの可能性を「流動的なこと(インタラクティブであること)」に見出す田中と、タイポグラフィの歴史を踏まえつつ、文字環境の開発に関わる山本。一見すると、それぞれのベクトルは真逆を向いているようにも思える。しかし、原は彼らのプレゼンテーションに共通するものとして「文字が本来持っている緻密さ」と「それをどんどん深めていく方向性」を指摘した。
「価値の基盤を、新しいもの(未来)に置くか、それとも伝統的なもの(歴史)に置くか。立ち位置はふたつあると思うんですね。現在は、テクノロジーの進化が加速している時代です。その分、価値観の立脚点が、未来にシフトしている気がします」(原) 「逆に言うと、タイポグラフィに500年の歴史があるとするのならば、我々は500年後の人々に何を残せるのか、ということを考えた方がいい。少なくとも、100年後にも読めるような書物は、どういう形式をしているのか。そのことを探るためのヒントを、たくさんいただいた気がします」
会場からも「言語野を通過しないタイポグラフィは可能か」という古くて新しい問いかけがなされ、議論は白熱したまま終了。今回のテーマである「透視される文字」は、いまだ揺籃期の中にあり、それゆえ、さまざまな可能態が夢想されているのだ。
研究会を終えて
永原康史文字に時間軸を与えるという田中さんの発想はダイナミック(動的)という概念を持つウェブデザインにおいて王道であり、書物への偏愛から文字を語る山本さんはその緻密さ故に異端である。来場者にとって、文字の振れ幅を実感し、考察を深めた時間だったのではないか。もちろんぼくも含めて。
原研哉言語野を通過しないタイポグラフィは可能かという問いは、ことばではない文字があり得るかという問いと同じ。詩とはことばから逃れようとすることば。タイポグラフィにも同じようなところがある。言語野ではないところに、言語野を拡張するのがクリエイション。
(写真:弘田充)