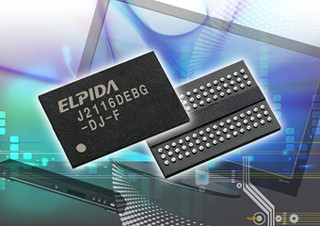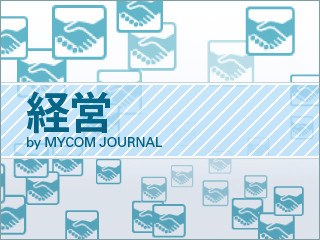エルピーダメモリは2月2日、2011年3月期第3四半期(2010年10月~12月)の決算短信を発表した。該当する3カ月間の業績は売上高が前年同期比35.7%減の971億円、営業損益は前年同期の472億円の黒字から77億円の損失へと赤字転落となり、経常損益も同275億円の黒字から305億円の損失へと、純損益も同211億円の黒字から296億円の損失へとそれぞれ赤字転落となった。
同四半期にて損失を計上した背景を同社は、DRAMメーカー各社の造プロセスの微細化の進展により供給は増加したものの、PC出荷台数の伸び悩みによるPC向けDRAMが需要不振となり、需給バランスが悪化、市場価格の急落を引き起こしたことを指摘。生産委託先からの調達と広島工場での生産見直しを実施し、2010年11月より減産を実施し、過剰在庫リスクの低減を図るなどの対応を行ったものの、販売単価の下落スピードがプロセスの微細化による製造コストの低下スピードを上回ったために損益の悪化を招いたことに加え、たな卸資産評価損等の発生や円高進行の影響があったこと、支払利息24億円や為替差損5億円の計上などもあり、営業損益、経常損益、純損益いずれも損失を計上したとする。

|
|
1Gビット DDR3 1333Mbpsの価格推移。夏頃から需給バランスの崩れなどの影響から値段を下げてきており、2011年2月1日の時点でスポット価格で1.18ドル、コントラクト価格で0.88ドルというところまで低下している |
その一方で、スマートフォンやタブレットPCなどの携帯情報端末の販売は第1四半期後半より堅調な動きが継続しており、これら携帯情報端末向けモバイルDRAMの需給はタイトな状況が継続したものの、デジタル家電向けDRAMの出荷が季節要因により減少となり、プレミアDRAM全体の売上高は前四半期比で約1割減となったとしており、結果として、DRAM出荷ビットは前年同期比18%増、前四半期比11%増となったものの、第3四半期における同社のDRAM平均販売単価(ドルベース)は、前年同期比39%の下落、前四半期比37%の下落となったとする。
これにより第1四半期から第3四半期までの累計業績は、主に前年同期比出荷ビットの増加により、前年同期比32.2%増の4,222億円となった。四半期ベースの売上高を見ると、第1四半期は1,763億円、第2四半期は1,488億円、第3四半期は971億円と、価格下落の影響および円高の影響を受けているものの、第3四半期累計の売上総利益は、先端プロセスへの微細化による製造コストの低減などにより、前年同期比596億円改善の942億円となった。
また、売上総利益の改善により、営業損益は前年同期の109億円の損失から519億円の改善となり、410億円の利益に益転を果たした。しかし、四半期ベースの営業損益は、第1四半期に過去最高の444億円を記録し、第2四半期も235億円の黒字を計上したものの、第3四半期はたな卸資産評価損などの影響もあり269億円の赤字となった。経常損益は、為替差損88億円および支払利息78億円を計上したことなどから、前年同期の245億円の損失から217億円の利益へと、四半期純損益は、契約精算益27億円、固定資産除却損15億円及び少数株主利益121億円の計上などにより、前年同期の306億円の損失から103億円の利益へとそれぞれ益転を果たした。
同社は40nmプロセスおよび30nmプロセス世代への切り替えを進めており、2010年12月に台湾のRexchip Electronicsがすべての生産品を40nmプロセスへの移行したのに加え、広島工場も2011年1月より30nmプロセス世代品の量産を開始、Rexchipも同プロセスでの試作を進めており2011年第2四半期(2011年4~6月)中よりPC向けDRAMとして量産開始を行うことを計画している。
また、2011年上期のDRAM市場の動向については、スマートフォンの市場成長が進むほか、サーバ向けがクラウドコンピューティング向け需要の増加が期待できるとしながらも、デジタル家電およびPCは新興国での需要次第という見方を示している。DRAMメーカーとしての立場からのDRAM需給バランスについては、Mobile DRAMについては、大容量製品が限られたベンダしか製造できないこともあり、良好に推移すると予測するものの、PC向けはフラッシュメモリや他のDRAM製品へのシフトが他のDRAMベンダで進むことが見込まれる程度で、若干の需給バランスの改善にとどまるとの見方を示した。
Mobile DRAMのビジネスについては、「2年前まではKGD(Known Good Die)ビジネスが売り上げの9割を占めていた。結果として、モバイル機器メーカーに間接的にしか納入できず、ダイレクトに要求を聞くことができなかった。しかし、今はPoPやFBGAなどのパッケージビジネスが主流となり第4四半期にはそちらのビジネスが売り上げの9割を占めるようになる」との見方を示す。また、モバイル機器メーカーとの親密な連携も進めており、スマートフォンベンダの7割となんらかのビジネスを行うようになっていること、およびモバイルプロセッサベンダに対して他社に先駆けて2Gビット LPDDR2製品の提供を行い、認証を受けるなど、周辺の整備も進めており、「2012年1~3月期には2011年1~3月期に比べてMobile DRAMの出荷数量は14倍に伸びる」との見方も示し、2011年末までに広島工場での生産物のほとんどをMobile DRAMにする方針を示した。

|

|

|
|
PowerchipのDRAM買取も広島工場でのMobile DRAM増産によるPC DRAMの減少量をカバーする1つの手段として採用した。また、Mobile DRAMの30nm世代プロセスを採用した2Gビット品についても2011年中の量産出荷を計画しているほか、同世代を用いた4Gビット品の製造も計画していうという |
||
なお、同社はDRAMの最大市場であるPC向けDRAM製品の価格が需給バランスの変動による影響を受けやすく、また将来における価格動向を的確に予測することが極めて困難なため、業績見通しを公表していないが、2010年3月期第4四半期の市場見込みとして、ビット成長率を前四半期比5~10%としており、通期のビット成長率を約35%程度としている。