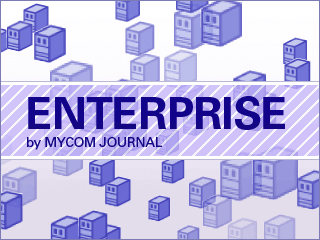まだまだ未知の存在の「MeeGo」

|
|
The Linux Foundation ジャパンディレクタの福安徳晃氏 |
The Linux Foundationは4月21日、2010年2月15日に発表された「MeeGo」に関するセミナー「MeeGo Seminar Spring 2010」を開催した。オープニングスピーチに登壇したジャパンディレクタの福安徳晃氏は、「MeeGoはまだ発表されたもので、日本では海のものとも山のものともつかないイメージがまだある。こうした取り組みを通じて、MeeGoとは何なのか、どういったことができるのかを伝えていければ」と、開催趣旨を説明する。
Linux FoudationによるとMeeGoはただのスマートフォン向けLinuxではなく、ネットブックや車載機器、メディアフォン、ネットTVなどにも対応するマルチプラットフォーム向けOSという位置づけであるが、「ただのLinux OSではない。真にオープンプラットフォームなLinuxで、かつ世界最大規模のディストリビューションで、従来のLinuxで抱えていた課題を解決することができ、Linux全体の発展を可能とするもの」(同)としている。

|

|
|
MeeGoは完全なオープンプラットフォームOS。適用範囲はネットブックやモバイル端末、車載端末といったMeeGo統合以前のMoblinとMaemoが得意としてきた分野が中心だが、あらゆる機器に対応していこうという取り組みとなっている |
|

|
|
The Linux Foundation Exective DirectorのJim Zemlin氏 |
では、どのような課題がLinuxにあり、MeeGoで解決できるのか、それについてはExective DirectorのJim Zemlin氏がより詳しく説明を行った。
Zemlin氏が語るところによると、「Linuxは今、第2の変動期を迎えている」という。第1の変動期は約10年前、IBMがLinuxに対し10億ドルの投資を行うことを決定した時だ。そのころはエンタープライズの分野ではSolarisがSPARCプロセッサ上で稼動していた時期で、Linuxもエンタープライズ領域での活用が見込まれていた。現在、Linuxは証券取引所やスーパーコンピュータなどでも活用されており、その適用分野を広げ、あらゆる分野で活用されるようになった。
ちなみにZemlin氏より、Linuxにまつわるさまざまな数値の紹介も行われたので、紹介しておく。1年間に追加された追加コード数量「270万」、1日に追加されるコード量「1万923」、1日に削除されるコード量「5547」、プロとして費用をもらって開発を行っているデベロッパーの割合「90%」、Linuxで処理されているシカゴ証券取引所の年間取引額「1000兆ドル」、Linuxを1から作成した場合に必要となるコスト「108億ドル」、使用料「0」、Linuxを生み出した人間の数「1」。
「最後の数値である"1"が示すLinus Benedict Torvalds氏の存在がもっともLinuxにとって重要で、その1人の考えの成果が今や地球全体に影響を及ぼすものへと進化してきた」(Zemlin氏)であり、他のOSからLinuxへ転換しようという動きは携帯機器とPCで同様に起きつつあるとしている。