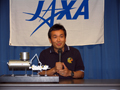同クルーらは矢野社長らとの懇談を終えた後、NECやNEC東芝スペースシステムなどの宇宙関連事業のエンジニアなどを交え、ISSでのミッション概要の解説やさまざまな技術についての報告会を実施。クルーとして、実際に宇宙でNECらが開発したシステムなどを扱った経験を踏まえ、技術者からの質問に答えていた。

|

|
|
NECやNEC東芝スペースシステムらの技術者などを中心に約380名が参加した技術報告会 |
技術者としても宇宙で実際の経験はなかなか聞くことができないため、自分たちの関与した技術(ロボットアームなど)の質問が多かった |
質問としては、技術者の視点から見たものなどが多く、例えば、「現実的に達成困難な要求も多く、そうした理想を示す基準よりも、現実的な基準にした方が効率的な開発ができるのではないか」といった質問に対し、「要求性能はさまざまな背景があり決定されたものなので、運用上の問題として、それを満たしていないと実現場で不都合が起きやすい。宇宙で問題が発生しても、対処のしようがないことが多いので、それを防ぐために高い要求を出している」(David A.Wolf NASA宇宙飛行士)と現場での経験を踏まえた回答としたほか、若田光一宇宙飛行士も「地上の訓練/試験で用いられるモックアップの精度が高くないため、要求性能を遵守することが宇宙で暮らすためには必要」と、理解を求めた。
NECの開発したきぼうに取り付けられたロボットアーム(Japanese Experiment Module Remote Manipulator System:JEMRMS)に関する質問も多く寄せられた。JEMRMSについてNASA宇宙飛行士でSTS-127ミッションの船長を務めたMark L.Polansky氏は、「日本のロボットアームは使いやすい。インタフェースがシャトルとは違うが、非常に使いやすい。スペースシャトルのロボットアームもJEMRMSも操作したが、シャトルのアームと同様に操作できた。ただ、違うのは人間系のインタフェースで、シャトルはスイッチ系の機構が多い一方、ISSはソフトウェアでコントロールしている場合が多く、ロボットアーム各種さまざまな能力を持っているが、運用上のリミットを考えながら操作をする必要がある作りになっている」と非常に良い感触だったことを述べた。
また、次のマニピュレータシステムになにか要望はあるか、との問いについても、次世代アームについては、現状のアームがコントロールシステム、コマンド操作を含め、今、どの位置にあるのかをクルーへ表示にするのと実際の位置に時差があり、その誤差が運用をしにくくしていることを指摘。その誤差を縮めるアーキテクチャや、時差を感じさせないような自動化システムなどに進むと使い勝手の向上につながるのという希望も述べた。
このほか、技術的な話以外に、スペースデブリは怖くないのか、といった質問もあり、これに対しても、「スペースデブリは多く存在しているが、地上からモニタしており、必要があればISSの軌道を変えることもできるため、まったく怖くない」(Thomas H.Marshburn NASA宇宙飛行士)とするが、地上からトラッキングできないデブリもあり、その確率は船外活動200回に1回程度とそれほど多くはないものの、実際に手袋に傷がついた程度の損傷は体験しているとし、当たっても孔が空かないような工夫などを施し、安全性を強化していると説明。
加えて、NECが開発したきぼうとそのコントロールを行う「筑波宇宙センター(TKSC)」を結ぶ衛星間通信システム(Inter-Orbit Communication System:ICS)についても、クルーらは賛辞を送った。実際問題として、ISSにはICSともう1つNASAの回線があるが、「6人で作業を行う場合は、実験や整備作業をする際、地上とのやり取りする必要があるので、NASAの回線だけだと、いわゆる話中となり、待ってないといけない。そうした時間の有効活用ができないという意味では重要な問題。結果としてICSを使いたいと皆が感じており、近いうちにさまざまな用途で使えるようになることを期待している」(NASAフライトディレクターのHolly Ridings氏)と、ISSの6人運用で生じた問題の解決策の1つになると期待を語った。
最後の質問は、日本の宇宙技術と他国の宇宙技術を比較すると、という質問。これには、5人の出席者全員が回答したが、おおむね、宇宙開発という世界的な動きの中、そうした技術が地上へフィードバックされ、人類の進歩に寄与していることを考えれば、日本企業やJAXAは世界に誇れる水準に達しているとする。
また、Polansky船長は、「多くの人々が関与し、きぼうを作り上げた。きぼうは世界に誇れる水準にあると思ってもらいたい。きぼうには高い技術力を感じたし、HTVも成功しており、宇宙技術における今後の日本の役割に非常に期待している。ただ、弱点かもしれない部分は、米国も同様だが、国家として宇宙開発に対するコミットメントが不十分な点。宇宙が国家として重要だということを表明することは米国にとっても、日本にとっても必要なことだと思っている」と指摘、これについては若田宇宙飛行士も同様に「日本はハードウェアもソフトウェアも必要十分なものを提供してくれた。今後もそうしたシステムを生み出していってもらいたい。期待することは、宇宙開発というものが、人類にとっての長期にわたる投資であるという認識。そこから生み出された技術が地上での生活を豊かにするほか、新たな人類のフロンティアとしての認識を、しっかりとビジョンとして国際的に進めていく必要があると感じている」と、意見を述べ、今後の抱負として「我々も日本のすばらしい技術を現場で生かすことができるようにがんばっていきます。今後も、開発と現場と違いはありますが、一緒にがんばっていければと思ってます」と今後も宇宙開発に向け、まい進していくとした。