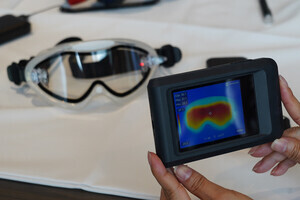映画『らくだの涙』とサハラ砂漠で見つけた"自分の音"
――『Homicevalo』の体験が『Tai Rei Tei Rio』の音楽の根底に繋がっていくと。
高木「ちょうどそんなことを考えていた時期に、その想いをカタチにするきっかけとも言える映画に出会いました。それが『らくだの涙』というモンゴル映画です。この話、『或る音楽』の中でも言ってますが、観ていない方には絶対に観て欲しい作品です。内容はシンプルなドキュメンタリーで、モンゴルの遊牧民の大家族が飼育していたラクダから、新しい命が生まれるんです。けれど母のラクダは赤ん坊を見向きもしない。困った家族は、母ラクダの頑なな心を解くために、この地域の伝統的な秘策を試みるんです。それは、馬頭琴の名手の音楽で、母ラクダの母性を呼び覚まそうとするというものです」
――つまりは音楽療法ということですか?
高木「演奏家は馬頭琴を母ラクダの首にかけるだけで、草原に吹く風に演奏させます。その後は演奏家自ら馬頭琴を奏でて、家族がそれに合わせて歌う。すると驚くことにその音色を聴いていた母ラクダの目から大粒の涙がこぼれ落ちてくるんです。そして子ラクダを連れていくと、ちゃんとミルクを飲ませている。といったストーリーなんですけど、僕はこの作品を観たときに音楽の役割を見つけた気がしたんです」
――音楽の役割とは?
高木「もともとあるべき親子の姿が、何かの原因で引き裂かれてしまう。それが音楽を介すことによって元に戻る。音楽とは本来、離れているもの、離れてしまったものをもう一度繋ぐ役割があるのではないかと……」
――その“気づき”をどのように自身の音に反映させていったんですか?
「それはサハラ砂漠での出来事の影響も大きいですね。まわりには星空と砂漠しかないような、サハラ砂漠の真ん中で宿泊したことがあります。あたりにはテントがいくつか張ってあって、そこで現地の人が太鼓とギターだけで適当に音を遊んでいた。その音がまた、不思議なくらいストンと心に響いて。"これこそ自分が思う音楽だ! でも、この感覚はなんなのだろう?"と思って、彼らに話しかけたんです。そしたらギターを渡されて、日本の曲を弾いてと言われて。いざ弾いたら、全然チューニングが合っていなかった。それで、直した瞬間に、これがまた全然響かない音なんですよ(笑)」
――音が心に響かないということですか?
高木「そうなんです。それでギターを返したら、適当にチューニングを戻されて、彼らが奏でた瞬間にまた音が響きはじめた。つまり自分の弾きたい音を奏でるのではなく、環境に音を合わせる。周囲にある大きな何かにチューニングを合わせると定まる音が見つかる。あとはメロディーなんて気にしなくても、音が湧き出てくる。それを耳にした時に、"僕はこれを聴きたいし、演奏したいんだ"と思ったんです」
――こうして音楽の役割を知り、その役割のもと弾きたい音も見えてきたんですね。
「家に帰ってその感覚を辿るようにピアノを弾いたんです。例えば小鳥が近くで鳴いていたら、小鳥まで音を広げて響かせるように意識する。すると音も変わってくるのがハッキリとわかるんです。そういう意識でピアノと向き合ってからというもの、新旧や自他の曲に関わらず、毎日何を弾いても楽しくなりました」