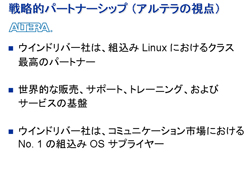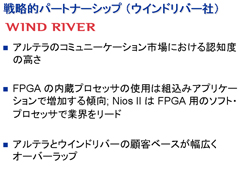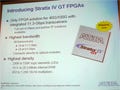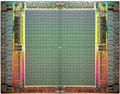サポートサービスをWind Riverが提供
ここまで、AlteraのNios IIとWind RiverのLinuxが組み合わさることのメリットを述べてきたが、そもそも、何故、この2社がパートナーシップを結んだのか。これについて堀内氏は、「FPGAの内蔵プロセッサの使用比率が組み込みアプリケーションで増加する傾向がでてきており、Wind Riverとしてもその対応を模索していた」ことを前提条件とし、「Wind Riverは、コミュニケーション市場における組み込みOSサプライヤとしてはトップクラスのメーカーであり、またAlteraも同分野で強みを持っている。そのためカスタマの多くがオーバーラップしており、そういった意味でパートナーシップを締結する下地が存在していた」と語る。
そのため、Alteraとしても今回のLinux採用アプリケーションの多くがコミュニケーション分野に適用されると見ている。「ネットワークのルーティングが複雑になるほど個々の開発部隊では手に負えなくなる。それを解決するためにはOSをベースにその上で走るソフトウェアを開発していく必要がある」(同)としており、すでにアーリーアクセスとして一部のコミュニケーション分野のカスタマに向けて提供済みであるとする。
また、堀内氏は、「LinuxとNios IIを利用して大規模かつ複雑な装置を作りたいユーザーに向けて提供していきたい」としており、そのための施策として「他のCPUを用いているシステムからの移植などについてもWind Riverが相談を受け付けるほか、オープンソースで作製された通信向けソフトウェアの動作確認や信頼性の保証などもWind Riverがサービスとして提供する」(同)とし、「Linuxを扱うためには実際にはOSのカーネルをいじる必要があるが、ユーザー全員がそれをやれるとは限らない。そういった意味ではベンダ側からさまざまなサービスを提供する必要があり、それが業界トップクラスのシェアを有するリーダーカンパニーであれば、なおさら良い」(同)と、Wind Riverがサポートを提供する意義を強調する。
なお、Alteraのビジネスとしては開発ボードの販売がメインとなるわけだが、これについて堀内氏は、「あくまで個人の希望を含んだ目標」と断りを入れつつも、「このビジネスについては細々とやるつもりは毛頭ない。1年程度の期間で、通信、特にグローバルでビジネスを展開しているような日本の大手メーカー複数社で採用されることを目指したい」と語り、そのためのアピールを展開していくとした。