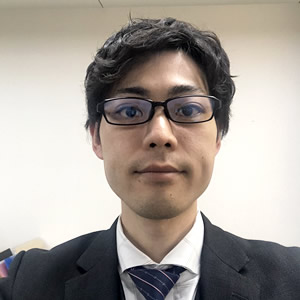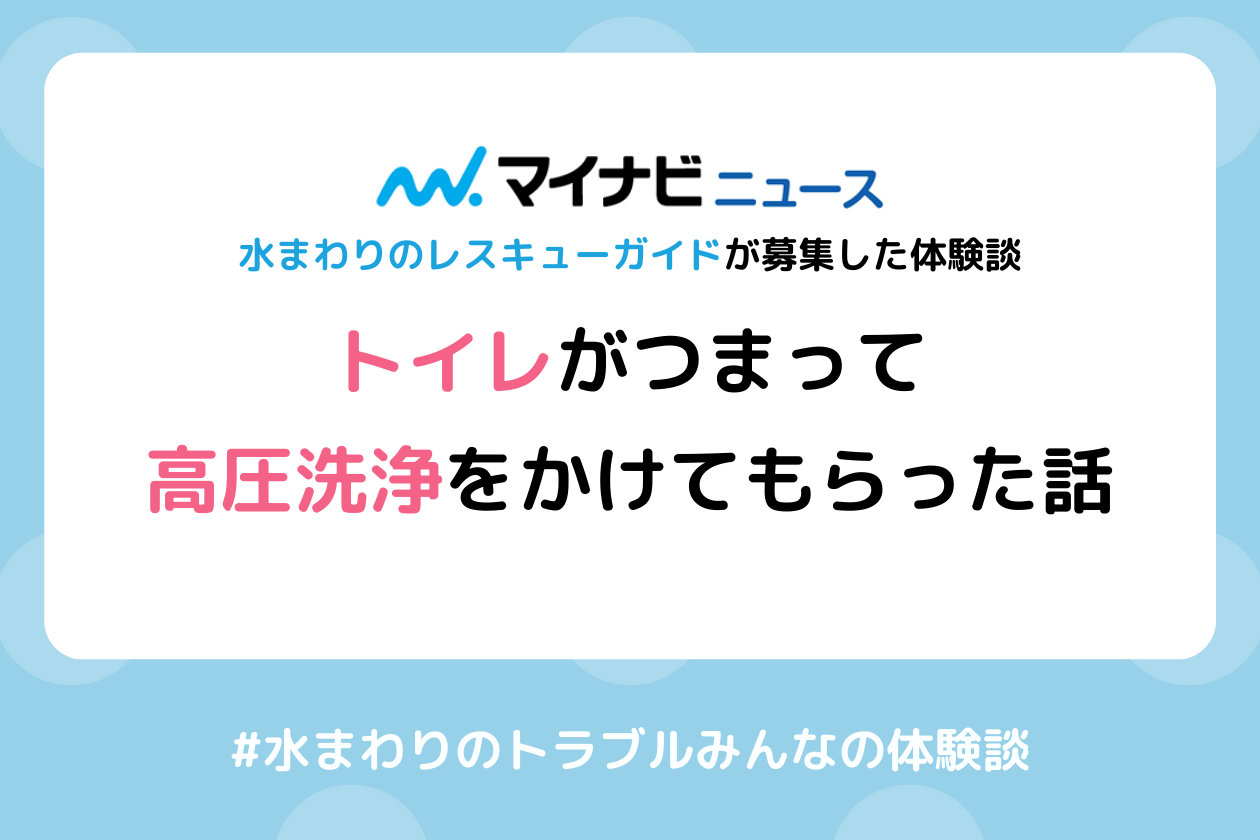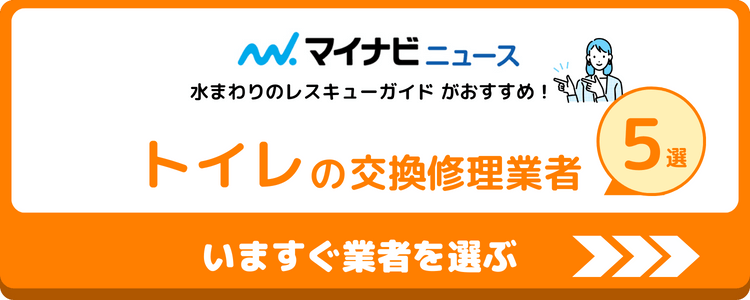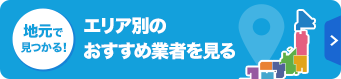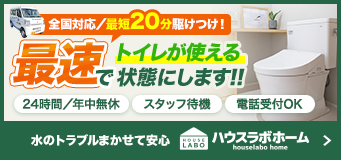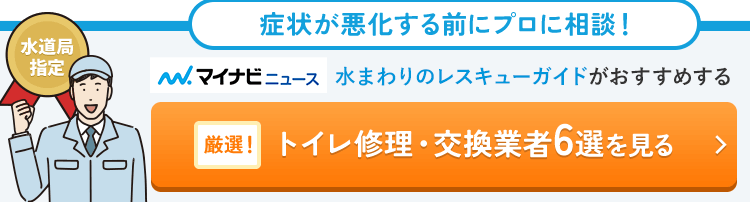トーラーとは

トーラーとは、トイレや排水管の内部につまった汚れや異物を直接取り除くために使われる専用の清掃工具です。
先端にブラシやドリル状の金具が付いた金属製の細長いワイヤーを排水管内に挿入し、手元でワイヤーを回転させながらつまりの原因を削り取ったり絡め取ったりして除去します。
いわば配管内のつまりを物理的に破砕・貫通(通貫)するための道具で、一般的なラバーカップや液体薬剤では対処できない頑固なつまりにも効果を発揮します。
プロの水道業者が使用することが多い高度な工具ですが、近年は家庭向けの簡易な商品も市販されており、自分で扱うことも可能です。
ただし扱い方を誤ると便器や配管を傷つけてしまう恐れがあるため、使用には十分な注意とコツが必要です。
トーラーの特徴・種類
トーラーにはさまざまな種類がありますが、大きく分けて「手動式」と「電動式」の2種類に分類できます。
また、利用シーンに合わせて家庭用と業務用に分けられ、形状や性能・価格帯も大きく異なります。
なお、トーラーのワイヤー長さは製品によって様々で、一般的な家庭用では5~10m程度、業務用では15~30mにも及ぶものがあります。
配管の長さやつまりの位置に合った長さを選ぶことが大切です。
手動式
手動式トーラーは、人力でハンドルやグリップを回してワイヤーを操作するタイプのトーラーです。
ドラム状の本体に細長いワイヤーが巻き取られており、先端にらせん状の金具やブラシが付いています。
使う際はワイヤー先端を排水管内に挿入し、ハンドルを回しながら少しずつ押し込んでいきます。
手動の回転力で先端部分が回り、つまりの原因を削り砕いたり引っかけて取り除いたりします。
比較的構造がシンプルで価格も手頃なものが多く、家庭用トーラーのほとんどは手動式です。
メリットとしては、電源が不要で取り回しがしやすく、軽量コンパクトで初心者でも扱いやすい点が挙げられます。
一方で、人力ゆえに強力なつまりには時間がかかったり、腕力・体力を要するというデメリットもあります。
また太い配管や長い距離の清掃には限界があるため、家庭内のトイレやキッチン排水など比較的軽度なつまり向きと言えるでしょう。
電動式
電動式トーラーは、モーターの力でワイヤーや先端ヘッドを高速回転させるタイプのトーラーです。
電源(家庭用コンセントやバッテリー)に接続して使用し、エンジン音こそ小型ですが内部にモーターやギア機構を備えた本格的な機械です。
手動式に比べて圧倒的に強い回転力・貫通力を発揮するため、固着した頑固な汚れや長年蓄積した硬いつまりでも効率的に除去できます。
業務用では大型のスタンド型やキャリーカート型の電動トーラーも存在し、長大なワイヤー(20~30m以上)を搭載して下水管の奥深くまで清掃できる製品もあります。
電動式のメリットは何と言っても作業スピードと威力で、手動では歯が立たないような重度のつまりにも対応可能な点です。
一方デメリットとして、機械本体が高価で重量もあり、操作にはある程度の技術が求められます。
また電源が必要になるため取り回しが制限されたり、誤操作すると配管を傷つけるリスクも高くなります。
一般家庭で電動トーラーを常備するのは現実的ではなく、価格も数十万円に達する高性能機種もあるため、使用頻度が低い場合の購入はおすすめできません。
個人で扱う場合は、まずは手動式で対応し、それでも難しい場合に専門業者が電動式を投入する、というケースが多いでしょう。
トーラーの使い方

トーラーの基本的な使い方を、手動式を例にとって手順で説明します。
初めて使う場合は無理をせず、ゆっくり慎重に作業しましょう。
- 準備作業:まず周囲を片付け、便器や床が汚れないようにビニールシートや古新聞などで養生します。詰まった水があふれても対処できるようにバケツや雑巾も用意しましょう。また、作業者自身もゴム手袋やマスク、保護メガネを着用し、汚水や汚物が皮膚や目にかからないようしっかり準備します(衛生面と安全面の確保が大切です)。
- 便器内の水抜き:トイレの水位が高い場合、そのままワイヤーを入れると汚水があふれる可能性があります。小さなバケツやポンプを使って便器内の水をできるだけ汲み出し、水位を下げておきます。こうすることで作業中の飛び散りや床への漏水を減らせます。
- ワイヤーの挿入開始:トーラー本体からワイヤー先端を引き出し、便器の排水口(排水管の入口)に先端ヘッドをゆっくり差し込みます。陶器製の便器にワイヤーが直接当たると表面を傷つける恐れがあるため注意してください。可能であればワイヤー先端が便器に擦れない角度を保ちながら挿入し、ゆっくりと押し進めます。狭いカーブ部分では抵抗を感じることがありますが、絶対に無理に押し込まないでください。
- 回転させながら進める:ワイヤーがある程度進んだら、ハンドルを時計回りに回転させながら少しずつ押し込んでいきます。回転させることで先端の金具がつまりの原因に食い込み、削り取ったり絡め取ったりしやすくなります。無理な力を加えず、ゆっくりと回し入れるのがコツです。固い抵抗を感じたら、一旦ワイヤーを少し引き戻し、角度を変えて再度ゆっくり押し込んでみます。これを繰り返して少しずつ前進させましょう。
- つまりの除去:ワイヤーが奥まで入り、先端がつまった異物に届いて削り取れると、詰めていた汚物や紙が崩れて流れやすくなります。ある程度つまりが解消できた手応えがあれば、少量ずつ水を流してみます。水がスムーズに引いていくようなら、つまりが解消し始めている証拠です。完全に水が引ける状態になるまで、ワイヤーを前後させたり回転させたりして異物を除去しましょう。
- ワイヤーの引き抜き:つまりが解消したら、水を流しながらワイヤーを少しずつ引き戻します。一気に抜くと汚れが飛び散る恐れがあるため、ワイヤーに付着したゴミを便器内で洗い落とすようにゆっくり抜き取ってください。ワイヤーを完全に引き抜いたら、便器にバケツの水を注いで流れが正常に戻ったか最終確認します。
- 後片付け:作業後は、使用したトーラーのワイヤーに付着した汚れをしっかり洗浄します。汚物が付いたままだと悪臭や衛生面で問題がありますので、できればバケツなどに中性洗剤を溶かした水を用意し、ワイヤーを何度か出し入れして洗いましょう。洗浄後は乾いた布で水気を拭き取ります。後の「メンテナンス方法」の章で詳しく述べますが、使用後のトーラーはしっかり手入れすることが長持ちさせるコツです。
作業全般を通じて、「焦らずゆっくり」が重要です。
無理に力任せに押し込まないこと、常にワイヤーを回転させながら進めること、この2点を守るだけで初心者でもスムーズに作業できます。
逆に強引に扱うとワイヤーが急に飛び出したり、配管の曲がり角で絡んで抜けなくなったりする恐れがあるため注意しましょう。
また、途中で違和感を覚えたら一度作業を止めて、専門業者に相談するのも安全策です。
トーラーの注意点

トーラーは便利な反面、使用を誤ると思わぬトラブルを招く可能性があります。初心者が扱う際に特に注意すべき点をまとめます。
- 便器や配管を傷つけるリスク
- 操作には熟練が必要
- 汚れ・臭い・衛生対策
- 固形物には使わない
便器や配管を傷つけるリスク
繰り返しになりますが、陶器製の便器内部はデリケートです。
金属ワイヤーが直接こすれると便器に細かな傷がついたり、ひび割れの原因にもなりかねません。
古い陶器は特に脆くなっているため要注意です。プロの業者は作業前に便器そのものを取り外し、直接排水管から作業することもあります。
一般の方がトーラーを使う場合は便器を外すのは難しいため、極力便器を傷つけないよう慎重にワイヤーを挿入してください。
また、古い鉄製の排水管も無理な回転力で削りすぎると穴が開いたり破損する恐れがあります。不安な場合は無理をせずプロに任せる判断も大切です。
操作には熟練が必要
トーラーは簡単に見えて適切な操作にはコツと経験を要する専門的な工具です。
プロの修理業者でも扱いに慣れるまで時間がかかると言われるほどで、初心者が自己流で扱うと「うまくつまりが取れない」「かえって状況を悪化させた」というケースもあります。
特にワイヤーの扱いには注意が必要で、無理に押し込むと配管の曲がり角でワイヤーが立ち往生して抜けなくなる恐れがあります。
また、強い力をかけすぎるとワイヤー自体が折れ曲がったり捻じれて使い物にならなくなることもあります。
徐々に回し入れる感覚を掴むまでは難しい工具なので、「少しでも不安を感じたら作業を中断する」ぐらいの慎重さで臨みましょう。
汚れ・臭い・衛生対策
トーラー作業では排水管内の汚泥や詰まっていた汚物をかき出すため、汚水の飛び散りや悪臭は避けられません。
作業中だけでなく、使用後のトーラー本体にも雑菌や汚れが付着しています。必ず使い捨てのビニール手袋やマスクを着用し、終わった後は手洗い・うがいを念入りに行いましょう。
ワイヤーやヘッド部分は後述する方法でしっかり洗浄・消毒し、保管中も嫌な臭いがこもらないよう乾燥させてください。
固形物には使わない
もしトイレにスマートフォンやおもちゃなど固形物を誤って落として詰まらせてしまった場合は、トーラーの使用はおすすめできません。
無理にワイヤーを押し込むと固形物をさらに奥に押しやってしまう可能性が高く、状況が悪化します。
固形物が原因と分かっている場合は、トーラーでは対処せず速やかに業者に相談しましょう。
業者は便器を取り外して直接異物を取り出すなど適切な方法で対処してくれます。
以上のように、トーラーは効果が高い反面リスクもある工具です。「無理をしない・焦らない・清潔に扱う」を心がけ、安全第一で作業してください。
トーラーで対応できるトイレつまり

トーラーは物理的に排水管内の障害物を除去するアプローチであるため、他の手段では直らなかった頑固なつまりにも威力を発揮します。
具体的にトーラーで対応しやすいトイレつまりの例を挙げてみます。
- トイレットペーパーなどの詰まり
- 汚物や尿石などの蓄積
- 排水管の奥で発生したつまり
- その他の中程度の異物詰まり
トイレットペーパーなどの詰まり
大量のトイレットペーパーや流せるお掃除シートなどが原因で起きた詰まりは、トーラーが得意とするケースです。
紙類は水に溶けるとはいえ、一度に大量に詰まるとラバーカップでは動かせないことがあります。
トーラーで直接絡め取ったり、紙の塊をほぐすことで物理的につまりを崩せます。特に奥の排水管で紙が団子状に溜まったケースでは、長いワイヤーで届くトーラーが有効です。
汚物や尿石などの蓄積
便や尿石(尿の成分が固まった石灰質の汚れ)などが長年蓄積して配管内径が狭くなっている場合も、トーラーで削り落とす方法が効果的です。
ヘドロ状・固形化した汚れを先端の金具で削り取って除去できるため、液体パイプクリーナー(薬剤)では落とせない頑固な汚れにも対応可能です。
尿石によるつまりは再発しやすいため、トーラーで一度取り除いた後に高圧洗浄で徹底的に洗浄するのが望ましいですが、まずはトーラーで物理除去することが有効です。
排水管の奥で発生したつまり
便器から近い範囲のつまりはラバーカップで対処できますが、配管の奥深く(たとえば床下や屋外の排水マス付近)で発生したつまりにはカップの力が及びません。
そのようなケースでもトーラーなら5~20mにも及ぶ長いワイヤーを奥まで到達させて対処可能です。
実際、一般的なつまり解消グッズで直らないような深部のつまりに対して、業者はまずトーラーを用いて対応します。
ワイヤーが長ければ複数箇所に渡るつまりも順番に貫通させることができ、一つひとつ原因を取り除いていけます。
その他の中程度の異物詰まり
トイレに流れてしまった軽い異物(例えば少量の髪の毛や小さな布片など)が原因の場合、トーラーの先端に絡め取って引き出せる可能性があります。
市販の簡易ワイヤーブラシでは届かない場所にある異物でも、プロ用のトーラー(太いワイヤーや特殊ヘッド)なら物理的に引っ掛けて除去できることがあります。
以上のように、ラバーカップや真空式パイプクリーナーでは歯が立たない頑固なつまりや配管深部のつまりに対して、トーラーは非常に効果的な手段です。
実際、トイレつまりの現場では「軽度ならカップ→それで無理ならトーラー→さらに無理なら高圧洗浄機」という順序で対応することが一般的です。
トーラーはまさに「最後の切り札」とも言える存在で、これで解消しないつまりはほとんど残っていないと言えるでしょう。
トーラーでは対応できないトイレつまり

トーラーが万能とはいえ、残念ながら対応できないタイプのつまりも存在します。
無理にトーラーで解決しようとすると、かえって状況を悪化させる恐れがあるケースもあるため、以下に代表的な例を紹介します。
- 固形物が詰まったケース
- 配管の構造的な問題
- 劣化した排水管や古い配管のつまり
- 極端に固着した尿石やスケール
固形物が詰まったケース
前述の注意点でも触れましたが、スマホや玩具、アクセサリー類など固形物が便器や配管に詰まっている場合、トーラーでの対処は困難です。
ワイヤーを入れても異物を押し込んでしまうだけで、根本解決になりません。
先端に引っ掛けて取り出そうとしても、物の形状によってはうまく掴めず二次トラブルのもとになります。
こうした異物詰まりは、基本的に便器の取り外しが必要になるため、最初から専門業者に任せるのが安全です。
配管の構造的な問題
配管自体に問題がある場合も、トーラーでは解決できません。
例えば排水管の破損や陥没、勾配不良によって流れが悪くなっているケースでは、いくら異物を取り除いてもつまりが再発します。
同様に、屋外排水マスまでの経路で木の根が侵入していたり、排水マスが土砂で埋まっている場合も、トーラーで物理的に届かないか除去しきれません。
これらは配管工事や高圧洗浄など別のアプローチが必要なので、早めに専門業者に相談しましょう。
劣化した排水管や古い配管のつまり
トーラーは金属のワイヤーで強くこすり取るため、老朽化した配管ではかえってダメージを与える場合があります。
古い鉛管・鉄管などで内壁が脆くなっていると、トーラー使用中に穴を開けてしまうリスクもゼロではありません。
古い家屋で配管詰まりが発生した場合、「無理に通さずに配管ごと交換した方が良い」こともあります。
状況を見極めて、トーラーでは対処せず配管更新を検討することも必要です。
極端に固着した尿石やスケール
尿石や水垢が岩のように配管内にこびり付いている場合、手動のトーラーでは歯が立たないことがあります。
電動式なら削り落とせる可能性もありますが、薬剤処理や高圧洗浄との組み合わせが有効なケースです。
トーラーだけでは完全に落としきれず、崩したカスが残ってしまうと再度つまりを起こす原因にもなります。
そのため、トーラーを使っても改善しないほど頑固な汚れの場合は、無理せず業者に高圧洗浄で洗い流してもらう方が確実でしょう。
以上のようなケースでは、トーラー単独では解決が難しいと言えます。
無理に続行すると状況悪化や二次被害のリスクがありますので、「これは難しいかも」と感じた段階で早めにプロの力を借りる決断も大切です。
トーラーの選び方

いざトーラーを入手しようと思っても、長さや太さ、形状など様々な製品があって迷ってしまうかもしれません。
ここでは初心者がトーラーを選ぶ際に注目すべきポイントを説明します。特にワイヤーの長さ・径(太さ)と業務用か家庭用かの違いが重要になります。
長さ・径
トーラーのワイヤー長さは製品によって大きく異なります。市販の家庭用ワイヤーブラシ(簡易トーラー)は短いもので1m程度、長いものでも5~10m程度が一般的です。
一方、プロが使うようなトーラーでは15~20m、場合によっては30m以上の超ロングワイヤーもあります。
選ぶ際は、自宅の配管構造やつまりが発生している場所を考慮しましょう。
たとえばトイレから屋外マスまでがそれほど遠くない戸建て住宅なら5~8mもあれば足りますが、長いマンション配管や複雑な経路の場合は10m以上必要になるかもしれません。
「短すぎて届かない」は致命的なので迷ったら長めを選ぶと安心です。
ただし長すぎても扱いが難しくなります。長いワイヤーは途中でたるみが出て力が伝わりにくくなる傾向があるため、必要以上に長尺のものは初心者には持て余す可能性があります。
次にワイヤー径(太さ)です。
一般的な家庭用トーラーの径は5~10mm程度、業務用では12~16mmほどの太くて頑丈なワイヤーもあります。
太いワイヤーは剛性が高く強い力で汚れを削れますが、太すぎると細い排水管に入らないことがあります。
家庭のトイレ排水管は直径75mm前後が多いので、直径6~9mm前後のワイヤーなら無理なく入り込めるでしょう。
一方、キッチンや洗面台の細いパイプにはもっと細径のワイヤーでないと通りません。
このように、対象とする配管の太さに合ったワイヤー径を選ぶことが大切です。
製品の仕様に「適合パイプ径」が記載されている場合もあるので参考にしてください。
最後に、先端ヘッドの形状も場合によっては選択ポイントです。
シンプルなコイル状ヘッドやブラシヘッドのほか、頑固なつまり用にカッター刃付きのものなど様々なアタッチメントがあります。
初心者向けには標準的なコイル(スネーク)ヘッドで十分ですが、もし特定の用途(例えば尿石削り落とし用のカッターなど)が必要なら、交換用ヘッドが入手できる製品を選ぶと良いでしょう。
業務用・家庭用
トーラーには業務用(プロ仕様)と家庭用があります。両者の違いは一言で言えば「パワーとサイズ、そして価格」です。
家庭用トーラー
家庭用は初心者でも扱いやすいよう小型軽量に作られた製品が多いです。
手動式が主流で、ホームセンターやネット通販で数千円程度から手に入ります。
ワイヤー長さは前述の通り数メートル~10m程度で、ちょっとしたトイレ・排水口のつまりに対応できる性能です。
価格相場はおおよそ2000~5000円程度からあり、手頃なので一家に一つ常備しておくのもよいでしょう。
例えばモノタロウやAmazonでは「パイプクリーナー」の名前で5m前後の手動トーラーが販売されています。
こうした家庭用はコンパクトで収納もしやすく、使い方もシンプルなので初心者が初めて使うには適しています。
ただし、威力は業務用に比べ弱めなので、重度のつまりには歯が立たない場合もあります。
業務用トーラー
業務用は水道業者や設備管理のプロが使用する本格的な機械です。
大型で耐久性が高く、威力も段違いに強いため頑固なつまりの解消に適しています。
手動式の業務用もありますが、多くは電動式やエンジン式で、重量も数kgから場合によっては20~30kgになるものもあります。
ワイヤー長さも長く、建物全体の排水管清掃に使えるよう数十メートル規模の製品も存在します。
こうした業務用は価格が非常に高く、安くても数万円、高性能な電動タイプでは数十万円に達します。
一般家庭で購入・保管するには現実的ではないため、使用頻度が低いなら無理に手を出す必要はありません。
業務用トーラーが必要になる場面=プロの出番と考えて、いざという時は業者を呼ぶ方がコスト的にも安心と言えるでしょう。
以上のように、「家庭用 or 業務用」「ワイヤー長さ・太さ」などを総合して、自分の用途に合ったトーラーを選んでください。
ポイントは、狙いたいつまり箇所に届く十分な長さがあること、配管に無理なく入る太さであることです。
逆に性能過剰なものは扱いきれないので避け、まずは手軽な家庭用から試してみるのがおすすめです。
トーラーのメンテナンス方法
購入したトーラーを長持ちさせ、安全に使い続けるためには使用後のメンテナンスが欠かせません。
汚れたまま放置すると錆びついたり悪臭の原因になったりします。
ここではトーラー使用後の手入れ方法を説明します。
- 洗浄:まず、使用後のワイヤーや先端ヘッドに付着した汚れをしっかり洗い流します。バケツに水を張り、中性洗剤を数滴垂らしてワイヤーを出し入れしながら拭うと効果的です。特に先端部分には汚物や紙片が絡まりやすいので、古い歯ブラシなどでこすって除去してください。衛生面が気になる場合は薄めた塩素系漂白剤にしばらく浸けて消毒する方法もあります(ただし金属が腐食しないよう濃度と時間に注意)。
- 乾燥:洗浄後はワイヤーをできるだけ乾燥させることが大切です。布や雑巾で水気を拭き取ったら、しばらく風通しの良い場所に広げて陰干ししましょう。水分が残っていると錆の原因になります。特にスチール製ワイヤーの場合はすぐに錆びやすいため念入りに乾かしてください。
- 潤滑・防錆:ワイヤーが乾いたら、機械油(マシンオイル)や潤滑スプレーを布に含ませてワイヤー全体を拭き上げます。こうすることで金属部分の錆を防ぎ、次回使用時もスムーズに繰り出せます。実際、「使用後はワイヤーに機械油を含ませておくと長持ちする」とされています。家庭用では手軽なシリコンスプレーなどでも代用可能です。先端の可動部(カッターヘッド等)がある場合も、可動部分に油を差しておくと良いでしょう。
- 保管:トーラー本体は直射日光や湿気を避け、乾燥した場所に保管します。ワイヤーは極力大きめの輪状に緩く巻いて収納すると、巻きグセが付きにくく扱いやすさが保てます。ドラム式の製品ならそのまま巻き取って構いませんが、外付けワイヤーの場合は無理に小さく束ねずゆったりとまとめてください。また、小さなお子さんやペットが触れない場所に保管することも大切です。先端部分は尖っていたり汚れが残っていたりする可能性があるので、保管中に誤って触れると危険です。ビニール袋やケースに入れて密閉しておくと安全かつ臭い漏れ防止になります。
以上がお手入れの基本です。
せっかく購入したトーラーですから、メンテナンスを怠らず清潔な状態で保てば、いざという時にすぐ取り出して快適に使うことができます。
工具を良好に維持することも「水まわりトラブル対策」の一環と考え、忘れずに実践しましょう。
トーラーとその他のトイレつまり解消道具の違い

トイレつまりを解消するための道具はトーラー以外にも色々あります。
ここでは代表的なラバーカップ(スッポン)、真空式パイプクリーナー(ローポンプ)、高圧洗浄機の3つを取り上げ、それぞれの特徴とトーラーとの違いを解説します。
「結局どの道具を使えばいいの?」と迷ったときの参考にしてください。
ラバーカップ
ラバーカップは、いわゆる「スッポン」と呼ばれる家庭に普及した詰まり解消道具です。
ゴム製の半球カップを排水口に押し当て、手で棒を上下に動かすことで圧力をかけ、詰まりを吸引したり押し流したりします。
ラバーカップは空気圧の力で間接的につまりを除去する方法であり、使い方も簡単でトイレが軽く詰まった程度ならまず最初に試すべき手段です。
価格も数百円程度と安価で、どなたでも扱える手軽さが最大のメリットでしょう。
トーラーが配管内の異物に直接物理的に働きかけて除去するのに対し、ラバーカップは圧力変化で間接的に動かす道具です。
そのため、詰まり解消効果の高さは一般に「トーラー > ラバーカップ」とされています。ラバーカップで一時的に流れが改善しても、原因が残っていればまたすぐ詰まってしまうケースがあります。
トーラーなら原因そのものを削り取ったり引き抜いたりできるので、根本的な解決が可能です。
ただし、ラバーカップはトーラーに比べて作業の手間や時間がかからず、便器や配管を傷つける心配もありません。
軽度の詰まりにはまずラバーカップを試し、それでもダメならトーラーを使う、という段階的な対処がおすすめです。
ちなみにラバーカップに関してはこちらの記事でご紹介していますので参考にしてください。

真空式パイプクリーナー
真空式パイプクリーナー(通称ローポンプ)は、ラバーカップを強化したようなポンプ型の詰まり解消道具です。
筒状のシリンダーとハンドルが付いており、シリンダー内のピストン操作で強力に空気を吸引・加圧します。
排水口にゴムカップ部を密着させ、ハンドルを引いて強い吸引力でつまりを引き出し、押して強い水圧で押し流すことができます。
要は「強力版スッポン」であり、ラバーカップでは抜けない頑固な詰まりもこの真空ポンプなら取れる場合があります。
ホームセンターなどで数千円程度で購入でき、繰り返し使える道具として家庭でもじわじわ普及しています。
原理的にはラバーカップと同じく圧力を利用した間接アプローチであり、直接異物を削るわけではない点がトーラーとの大きな違いです。
真空式パイプクリーナーはトイレ以外にも浴室やシンクなど幅広い排水口で使えますが、到達できる範囲は排水口付近に限られます。
奥の方で詰まっている場合は空気圧も届きにくく効果が落ちます。
その点、トーラーなら物理的に奥まで届いて作業できる強みがあります。また、トーラーは異物を引っ掛けて引き抜くこともできますが、真空ポンプはあくまで吸引・押し出しのみなので、例えば「固形物を取り出す」ことには使えません。
ローポンプは比較的安全で扱いやすいので、ラバーカップでダメな時の次の手段として有用ですが、それでもダメならトーラー出動…という段階的対応が良いでしょう。
高圧洗浄機
高圧洗浄機は、本来は洗車や外壁清掃に使われる機械ですが、排水管のつまり解消にもプロが活用する強力なツールです。
モーターで水を高圧に加圧し、専用ホースの先端ノズルから強烈な水流を噴射して配管内の汚れを一気に洗い流します。
高圧の水が配管内壁に付着したヘドロや尿石を削り取り、またつまりの原因を粉砕・押し流すため、トーラーと並んで最終手段的な位置付けです。
ただし高圧洗浄は大量の水を使用するため、通常は屋外の排水マスやベランダなどから作業を行います。
一般家庭向けにもコンパクトな高圧洗浄機が売られていますが、本格的な配管洗浄には専門業者の持つ業務用を使う必要があります。
トーラーが室内から配管内にワイヤーを送り込んで作業するのに対し、高圧洗浄機は屋外の排水マスなどからホースを挿入して作業するのが一般的です。
また作用原理も異なり、トーラーは金属ワイヤーの回転・摩擦でつまりを削るのに対し、高圧洗浄機は水圧で汚れを吹き飛ばすアプローチです。
威力面では高圧洗浄も非常に強力ですが、適用範囲に違いがあります。
トーラーは距離が延びるほどワイヤーがたわんで力が伝わりにくくなるため、配管の奥深く遠い場所でのつまりは苦手です。
一方、高圧洗浄機ならホースが届く限り一定の水圧をかけ続けられるので、長距離の配管でも安定した効果を発揮できます。
そのため、遠距離のつまり除去には高圧洗浄が適していると言われます。
逆に、便器直下の詰まりや局所的な異物にはトーラーの方が直接作用できて有効です。また、素人が高圧洗浄機を使うと水浸しになるリスクもあるため、扱いやすさではトーラーに軍配が上がるかもしれません。
トーラーと高圧洗浄機はどちらも強力ですが、状況に応じて「削る」か「水で飛ばす」かの違いがあります。
両者が必要になるケースでは、まずトーラーで異物を崩し、その後高圧洗浄で残った汚れを洗い流す、といった併用も行われます。
トーラーでも解消しないつまりはプロに任せる

ご自身でトーラーを使ってみてもつまりが改善しない場合、早めにプロの水道修理業者に任せることを強くおすすめします。
無理に作業を続けると便器や配管を傷めてしまい、かえって高額な修理が必要になる恐れもあります。
プロに依頼すれば費用はかかりますが、その分確実かつ安全につまりを解消してくれるメリットがあります。
専門業者はトーラー以外にも、高圧洗浄機や内視鏡カメラなど様々な機材を持ち合わせており、原因に応じた最適な方法で対処してくれます。
例えば異物が原因なら便器を取り外して直接除去し、尿石なら薬剤処理と高圧洗浄を組み合わせる、といった具合です。
また、経験豊富なプロなら配管の構造を熟知しているため、素早くつまり箇所を特定し効率的な手順で作業してくれ、自分で試行錯誤するより短時間で直るケースも多いです。
費用の目安としては、一般的なトーラー作業で約1~2万円程度、高圧洗浄機を併用すると2~3万円程度が相場と言われています。
便器脱着が必要な場合は別途1~2万円が加算されることもあります。決して安くはありませんが、トーラー本体を買う費用(数万円以上)と労力を考えればむしろ合理的との指摘もあります。
一度プロに依頼して直してもらえば、その場で再発の予防策や配管の状態も教えてもらえるでしょう。
特に次のような場合は迷わずプロに頼ってください。
- 原因が分からないor固形物かもしれない:原因不明のつまりに素人判断でトーラーを使うのは危険です。固形物だった場合は冒頭で述べたように逆効果なので、最初から業者に状況を説明して適切な処置を仰ぎましょう。
- 道具を使うのが不安:トーラーに限らず、ローポンプなどの器具を自分で扱うこと自体に不安がある場合も、無理せず電話一本でプロに来てもらう方が精神的にも安心です。「ちゃんと直せるかな…」とドキドキしながら作業するより、任せてしまった方が早いです。
- 深夜・早朝など緊急時:トイレが使えないと生活に支障をきたすため、夜間でも受付してくれる24時間対応の水道修理業者もいます。深夜に詰まって慌てて作業し事故を起こすくらいなら、多少割増料金でもプロを呼んだ方が安全です。
プロに任せることで「本当に直るだろうか…」という不安から解放され、確実にトイレを元通り使える安心感が得られます。
トーラーを使ってもダメなつまりは、プロに任せるべきサインと考えて、早めに信頼できる業者へ相談しましょう。
まとめ
トーラーはワイヤー式の専門工具を使ってトイレつまりを物理的に解消する心強い道具です。
初めてトーラーを使う方は、ゆっくり慎重な作業を心がけ、便器や配管を傷つけないよう注意しましょう。
また、今回解説したように、トーラーの使い方・選び方や他の道具との違いを知っておけば、いざというとき適切な対処ができるでしょう。
まずは安全第一で挑戦し、それでも解決しない場合はプロの力を借りることが重要です。
マイナビニュース水まわりのレスキューガイドではさまざまな地域でおすすめのトイレ修理業者を紹介していますので、そちらもぜひ参考にしてください。
おすすめ業者4選
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
PR