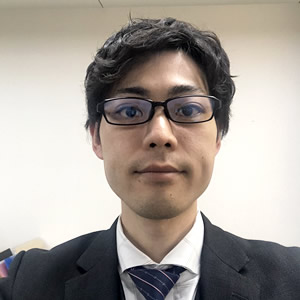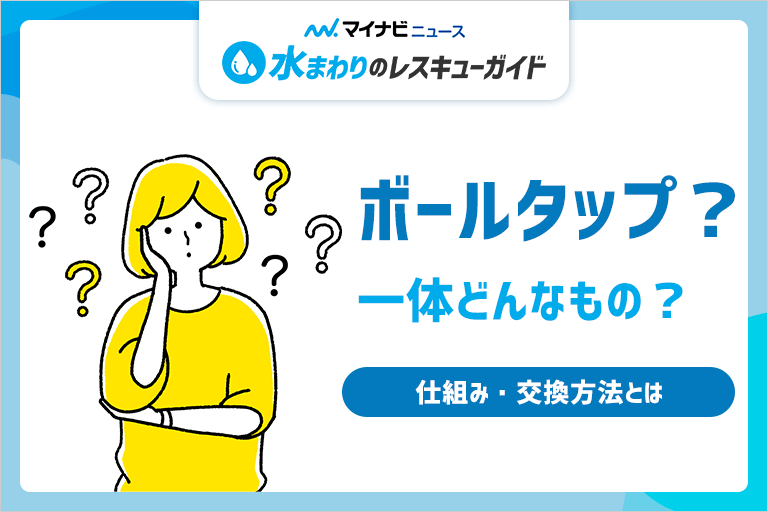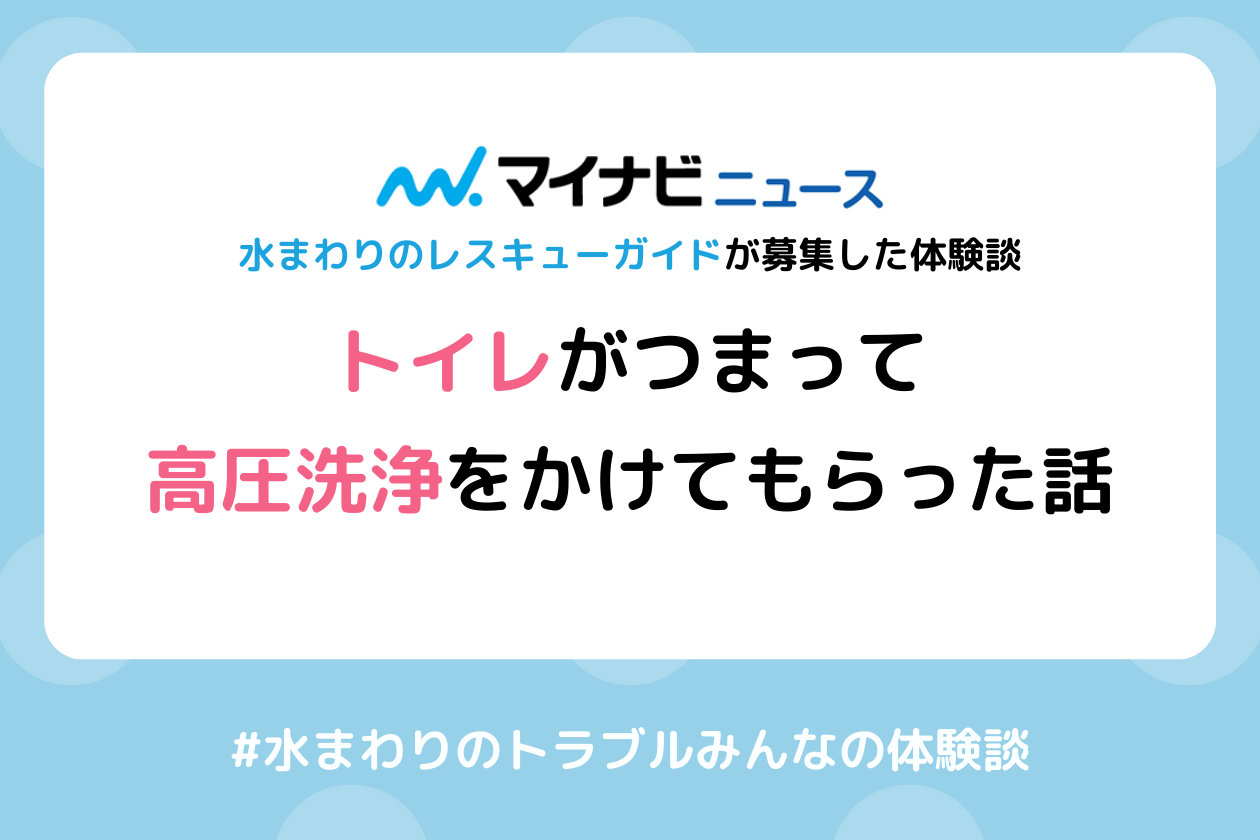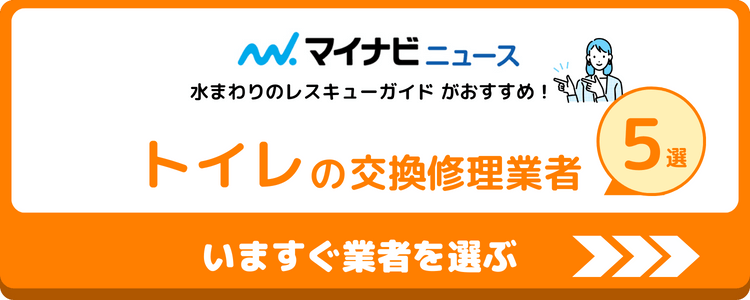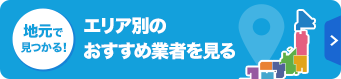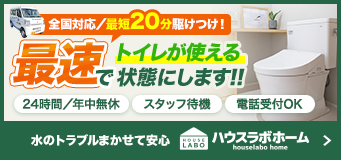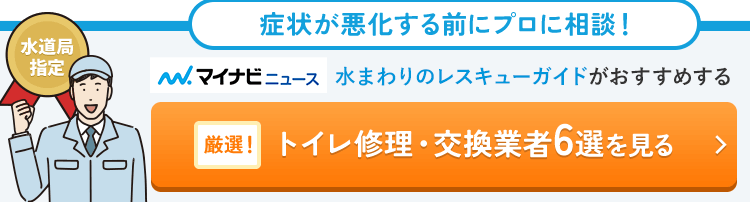便器の仕組み

そもそも便器には大きく分けて以下の2種類があります。
- 洋式便器(腰掛け便器)
- 和式便器
トイレの本体部分である便器は、現代では洋式便器(腰掛け便器)が圧倒的に主流となっており、多くの家庭が洋式水洗トイレを利用しています。
洋式便器にも和式便器にも共通する部分が多く、これから説明するのは洋式・和式どちらのタイプの便器にも共通する仕組みとなっています。

引用:TOTO公式Webサイト
封水(水たまり)
便器の排水口部分にたまっている水たまりを封水と言い、下水管とトイレ内を遮断し、下水や排水管から悪臭や害虫などがトイレ内へ侵入してくるのを防いでくれます。
便器の排水口にたまった封水の水位は後述する「せき」によって決まるため、量を多くしたり、少なくしたりといった水位を調節できません。
排水路
排水路は汚物や使用したトイレットペーパーを洗浄水とともに排出させる便器内の通路のことです。
径が大きければ大きいほどつまりにくくなりますが、限られた水量で排水させるため、むやみに大きくできません。
このため、便器に流せるものの種類や大きさなどが限られています。
便器の排水路はS字型をしています。便器内に封水を貯めておくために、上に向けてせりあがった形をしており、このせりあがった部分を「せき」と呼びます。
せきがあることでトイレを衛生的に使えるのですが、このせきが排水つまりの原因となってしまうこともあります。
排水を行う際に大量のトイレットペーパーを流したり、便秘などで多量の便を排水として流すと、排水路のせりあがった部分の「せき」を乗り越えることができずにトイレつまりが発生します。
タンク内からの水が少なすぎたり、汚れが付着していてつまりが起きやすくなっているケースもあるので注意が必要です。
トイレタンクの仕組み

トイレタンクにはさまざまな部品がありますが、ここでは代表的な以下の部品についてを紹介します。
- ボールタップ
- フロートバルブ(ゴムフロート)
- オーバーフロー管
- 浮き球
- レバー
- 止水栓
トイレタンクは、さまざまな部品が連動して動くことで水が流れるため、その中の一つの部品が故障するとトイレが流れなくなる可能性があります。
部品自体はホームセンターなどで売っているので自分で修理できる場合もあります。

引用:TOTO公式Webサイト
ボールタップ
「ボールタップ」は、タンク内にある部品ですが、根元がタンクの外にある給水管につながっており、先端に「浮き球」という水に浮く指示棒がついています。
レバーを引くことでフロートバルブ栓が持ち上がり、タンク内の水が便器内に流れ出しますが、その際にタンク内の水位が下がるのと同時にボールタップの先端に付いている浮き球が下がります。
浮き球が下がることによりボールタップ内の便が開き、タンク内に水が補給される役割を果たします。
タンク内の水位が戻り浮き球が元の位置に持ち上がるとボールタップの弁が閉じ給水終了です。
トイレタンクからの水が止まらない時や、タンク内に水がたまらない場合は、ボールタップの不具合が考えられます。
その際はボールタップの交換はDIYでも可能なので、ボールタップ自体を交換しましょう。
フロートバルブ(ゴムフロート)
「フロートバルブ」は、レバーの先にチェーンでつながれているゴム製のパーツで、「ゴムフロート」とも呼ばれています。
レバーを回すことでフロートバルブが持ち上がり、バルブが開いて水を流し一定量になると排水口を塞ぎ水を止める役割を果たします。
水がたまらない・止まらない時は、フロートバルブの不具合が原因のケースがあります。
最近ではゴム製ではなく、パッキンが取り付けられているプラスチック製のものもありますが、いずれもDIYで交換が可能です。
オーバーフロー管
「オーバーフロー管」は、タンク内にある管上の部品で「あふれ管」「溢水管」とも呼ばれ、根元の部分にフロートバルブが固定されています。
オーバーフロー管には-WL-という刻印がされているものがあります。
これは、タンク内に最低限ためておく必要のある水の量、いわゆる標準水位というもので、刻印がない場合にはオーバーフロー管から2~3センチ下が標準水位と判断しましょう。
タンク内が問題なく動いているときには、オーバーフロー管は特に動作はせず、フローバルブや浮き球などに故障・不具合があった場合に、タンク内の水位が上昇しすぎて、あふれそうになった状態に時になかが空洞になっている菅の内部を通して水を便器に排出する役目があります。
オーバーフロー管が故障した際も自分で交換することができますが、オーバーフロー管の交換は難易度が高く、失敗するリスクが高いため業者に依頼することをおすすめします。
浮き球
「浮き球」はボールタップの先端にある球状のパーツです。
水位の変化に合わせて浮き球が上下することにより、タンク内の水の量を調節する役割を果たしていて、浮き球の動きが指示棒に伝わりボールタップの弁の開閉を行います。
タンク内の水の出が悪い、溢れて水漏れする場合などは浮き球に不具合があることが考えられます。浮き球自体の交換はDIYで可能です。
レバー
レバーの先は、タンク内でフロートバルブ(ゴムフロート)のチェーンが接続されていて、レバーを回すことにより、チェーンでつながっているフロートバルブの栓を持ち上げ、タンク内から便器へ水を流す仕組みです。
レバーが空回りする、あるいはレバーを引いた後に元に戻らないなどのトラブルの場合は、タンク内でフロートバルブとつながっているチェーンがどこかに引っかかっていたり、切れていることが原因の場合が多いため、チェーンのチェックをしましょう。
止水栓
「止水栓」は、給水管からタンクへと水を送る栓で、床や壁に近い場所に取り付けられており、水漏れなどのトラブルの際や、部品の交換や修理を行うときは最初に止水栓を閉める必要があります。
止水栓を閉めるにはマイナスドライバーで右方向に回すことでタンクへの給水を止められます。
一般的には止水栓を閉めるにはマイナスドライバーが必要ですが、「ハンドルタイプ」と呼ばれる水道の蛇口のような物もあり、その形状の場合はマイナスドライバーは必要ありません。
止水栓から水漏れしている場合には、パッキンを交換するか、止水栓本体が破損している場合には止水栓全体の交換が必要になります。
自分で交換することも可能ですが、難しいと感じた場合にはトラブルを悪化につながる前に業者に修理を依頼しましょう。
トイレタンクの無いトイレもある

トイレタンクの仕組みについて紹介してきましたが、最近では便器の後ろの貯水タンクがないタンクレストイレも人気です。ここではタンクレストイレについての以下を紹介します。
- タンクレストイレとタンク付きトイレとの違い
- タンクレストイレのメリット・デメリット
- タンクレストイレの人気機種
タンクレストイレとタンク付きトイレとの違い
タンクレストイレとは、便器の後ろの貯水タンクがない対応のトイレのことで、水道に直接つないで、水道からの水圧によって排水します。
従来のタンク付きトイレは、タンクにためた水の重みでいっきに水を流すため、一度水を流すとタンクに水がたまるまで待つ必要がありますが、タンクレストイレは水道と直結しているため、連続して水を流すことができます。
具体的に、タンクレストイレのメリットとデメリットを見てみましょう。
タンクレストイレのメリット
タンクレストイレのメリットは主に次の3点です。
- 省スペースとデザイン性
- 節水効果に優れている
- お掃除のしやすさ
省スペースとデザイン性
タンクレストイレのメリットの1点目は、省スペースとデザイン性です。
便器の後ろにタンクがない分、トイレ空間を広々と使うことができます。
また、すっきりしたフォルムが洗練された印象を与えます。
節水効果に優れている
メリットの2点目は、節水効果があるということです。
タンク式のトイレの場合、1回トイレを使用するたびに水が13~15リットル必要とされていますが、タンクレストイレの場合は、3~5リットル程度の水しか必要としません。
年間の水道料は家庭によってもちろん異なりますが、1万円程度の節水効果が見込まれます。
お掃除のしやすさ
3点目のメリットはお掃除がしやすいという点です。
タンクレストイレは便器につなぎ目や凹凸はないためお掃除がしやすく、常にトイレを清潔に保つことができます。
タンクレストイレのデメリット
タンクレストイレのデメリットは主に次の3点です。
- 停電の時は水が流れない
- 手洗い場がない
- 価格が高い
- つまりやすい
停電の時は水が流れない
タンクレストイレは水道管と直接つながっています。
電気によってバルブが開閉され水が流れる仕組みになっているため、停電時には水を流すことができません。
停電が続けば、バケツなどにお湯をためて手動で流す必要があります。
手洗い場がない
タンク式トイレには、タンク上部に手洗い場が付いていますが、タンクレストイレにはタンク自体がないため手洗い場がありません。
手洗いの際に、洗面所まで移動することが面倒だと感じる人もいるでしょう。
トイレスペース内に別途で洗い場を設置する人も多く、その他にもPanasonicのNewアラウーノVのように手洗い場ありのタンクレストイレにする人もいます。
価格が高い
タンク式トイレは5~12万円前後で販売されていますが、タンクレストイレは15~60万円と高額です。
初期費用が高いためタンクレストイレへの交換に悩む人は少なくありません。
また、タンクレストイレは故障の際、便器を全て一式取り替えることになるため基本的に部品交換ができません。
そのため、故障時もタンク式より修理費用がかかります。
つまりやすい
タンクレストイレは、低い水圧で水を流せるため節水効果が高い点がメリットなのですが、その分便器内がつまりやすくなります。
特にマンションの高層階や古い家など水圧が低いところでは、頻繁に詰まってしまう場合もあります。
タンクレストイレの人気機種
タンクレストイレで人気の機種には以下のようなものがあります。
- 【パナソニック】アラウーノシリーズ
- 【TOTO】ネオレストシリーズ
- 【LIXIL】サティスシリーズ
【パナソニック】アラウーノシリーズ
アラウーノシリーズは、全自動のお掃除トイレがポイントで、日々のお手入れが楽になります。
また、汚れに強い有機ガラス系の樹脂を便器に使用しています。
【TOTO】ネオレストシリーズ
ネオレストシリーズの特徴は、きれいサイクル機能で汚れや臭いを自動で探知し洗浄してくれます。
節水性にも優れており、タンクレストイレの定番ともいえる製品です。
【LIXIL】サティスシリーズ
サティスシリーズは、シンプルなデザインでコンパクトなため、トイレ空間を広々と使えます。
スマホをリモコン代わりに使える機能もあり、トイレに入りながらスマホを使用する方にはおすすめです。
トイレの水が流れる時の仕組み

レバーを回して水が流れるまでの一連の流れを順に説明します。
- レバーを回す
- タンクから便器に水が流れる
- タンク内への給水が始まる
- タンク内が適正な水位になると給水が止まる
.png)
引用:TOTO公式Webサイト
1.レバーを回す
レバーを回すと、レバーにチェーンでつながっているフロートバルブが引っ張られることにより、持ち上げられタンク底部のバルブが開きます。
.png)
引用:TOTO公式Webサイト
2.タンクから便器に水が流れる
タンクから便器に水が流れます。
流れ終わると自動的にフロートバルブが元の位置に下がることによって排水弁が閉まります。
3.タンク内への給水が始まる
タンク内の水が少なくなると浮き球が下がり、それに合わせてタンク内への給水が始まります。
.png)
引用:TOTO公式Webサイト
4.タンク内が適正な水位になると給水が止まる
浮き球が上昇し、適正な水位まで給水されると水が止まります。次に使用されるまで同じ水量が保たれます。
トラブルごとの対処法
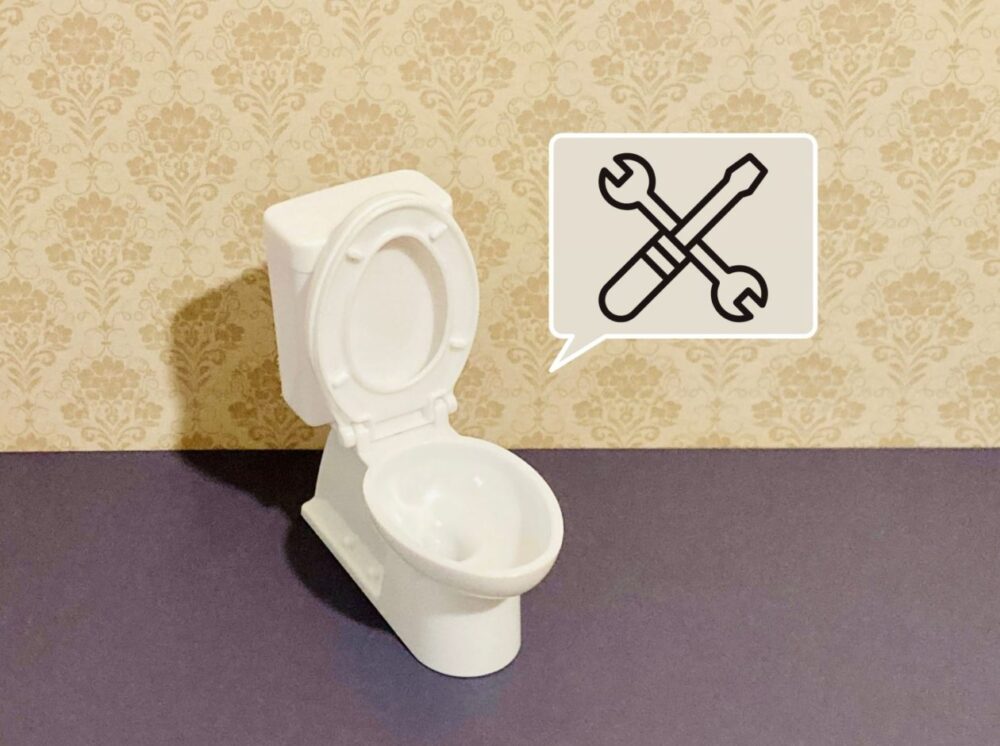
トイレの仕組みがわかると、以下のトラブルの修理方法も理解できるでしょう。
- 水が出ない・水が流れない
- 水漏れ
- トイレつまり
- レバーが戻らない
ここでは、トラブルごとの対処法を解説します。トイレの各パーツの働きや、水が流れる仕組みがわかっても実際に自分で修理できるかどうかはまた別問題です。
自力で修理することが難しいケースもあるため、自分では難しいと感じたらすぐにプロの業者に連絡しましょう。
水が出ない・水が流れない
水が出ない、流れない、あるいは止まらないなどのトラブルは緊急性が高いため、まず次のことを確認しましょう。
- 停電や断水の状況でないか
- ブレーカーが落ちていないか
- コンセントからコードが外れていないか
いずれも該当しない場合には、部品に不具合が発生していることが考えられます。
故障している可能性のある箇所の見つけ方や修理・交換の方法を紹介します。
・考えられる原因1:ボールタップ
ボールタップは、給水管と接続しておりタンク内の水量をコントロールします。
このボールタップが汚れていたり、ゴミがついているとうまく給水ができずタンク内に水がたまりにくくなるため、汚れをふき取るなりゴミを取り除きましょう。
・考えられる原因2:浮き球
浮き球自身が上下することにより、タンク内の水位をボールタップに伝える役割を果たします。
この浮き球の指示棒が引っかかっていたりするとボールタップから適切な給水がなされないため調整してください。
・考えられる原因3:レバー~チェーン~フロートバルブ
レバーがチェーンとつながっているフロートバルブが、レバーを回すことによって開閉し、タンクから便器へ水が流れたり止まったりします。
このフロートバルブとレバーをつないでいるチェーンが何かに引っかかっていたり、切れている場合にはレバーを回しても正常に水が流れません。
チェーンを正しい位置に戻すか、チェーンの交換が必要です。レバーやフロートバルブ自体の不具合も考えられます。
ボールタップ、浮き球、フローバルブ、レバー等は、部品を取り寄せて自分で交換することができます。
適合する部品の型番を取扱説明書で確認するか、説明書がない場合には、メーカーのサービス窓口に問い合わせましょう。
ちなみにトイレの水が出ない・流れない時は以下の記事が参考になりますのでぜひ読んでみてください。

水漏れ
便器やタンクから水漏れがする場合も緊急性が高いトラブルです。大量の水があふれている場合は、まず止水栓を閉めましょう。
前述したように、給水管の付け根のあたりに止水栓があるので、マイナスドライバーで右回りに回すと閉まります。
ちょろちょろと水が漏れる程度であれば、止水栓などに異常がないかを確認し、急いで対応する必要があるかどうかを検討しましょう。
止水栓のパッキンや、止水栓と給水管をつなげているナット、止水栓の金具、ウォシュレットへの分岐金具のパッキンなどが劣化などによる不具合がある場合、止水栓から水漏れする場合があります。
特にパッキンが原因で水漏れするケースが多いです。
パッキンの寿命は約10年となっており、設置から約10年立っている場合は、適合する型番を必ず確認して止水栓のパッキンを交換しましょう。
ナットのゆるみなどから水漏れしている場合には、モンキーレンチなどでしっかりと閉めてください。
止水栓自体が損傷している場合には、止水栓ごと交換する必要がある可能性もあります。
パッキンや、止水栓自体もホームセンターなどで部品を調達すれば交換は可能です。
しかしながら、自分で修理を試みて直らない場合や、原因が良くつかめない、修理が難しいと感じた時には専門の業者に連絡しましょう。
トイレの水漏れについてはこちらの記事でもご紹介していますので参考にしてください。

トイレつまり
つまりの原因は、一度に大量の便やトイレットペーパーを流したり、あるいは異物を流してしまうことです。
「トイレに流せる」トイレ除菌シートなども、一度に大量に流せばつまってしまうことがあります。
排水管のつまりを解決するには、ラバーカップと50度前後のお湯を使って解消できる場合があります。
50度前後のお湯を便器に流し、まずつまっているもの自体を柔らかくしてからラバーカップで吸引し取り除いてください。
ラバーカップでも取り出せない、配管部分の奥の方につまっている、あるいは流してはいけない固形物などを落としてしまうなど、自分ではどうしても取り出せない場合には、無理に対応することで排水管などを傷つけてしまうこともあるので、この場合も業者に連絡しましょう。
トイレつまりに関してはこちらの記事でもご紹介していますので参考にしてください。

レバーが戻らない
レバーが元に戻らない場合には、前述した水が出ない、流れない場合と同じようにトイレタンクのふたを開け、まずフロートバルブとレバーをつないでいるチェーンの状態を確認してください。
このチェーンが切れてしまっていたり、部品から外れていないかを確認します。次にフロートバルブを確認し、本来の場所からずれているとか、劣化してうまく動いていない場合などが考えられます。
ゴミや水垢などで汚れている場合には拭き掃除をすることで正常になることもあります。
また、レバー自体が曲がっていたり、軸が折れている場合もあるので確認しましょう。
チェーンやフロートバルブ、レバーの交換、いずれもDIYで修理することは可能ですが、途中でわからなくなったり、部品を交換しても良くならない場合には業者に相談することをおすすめします。
トイレの仕組みを知りDIYを行おう

便器やトイレタンクのパーツに関すること、またそれぞれの役割に加えて水が流れる仕組みなどを紹介してきました。
これらを知ることによって、ある程度の簡単なトラブルであれば自分で修理が可能であり、その分費用も安くなります。
それでも、どうしても原因がわからない・ある程度やってみたけど良くならない・やっぱり難しいという場合には、プロの業者に依頼しましょう。
おすすめ業者4選
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
PR