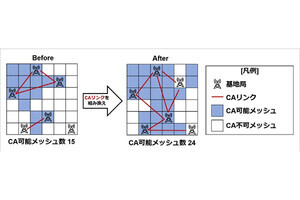コロナ禍でコミュニケーションの方法が様変わりするなか、コンタクトセンターの重要性は歴史上かつてないほどに増している。どのように日本企業はコンタクトセンターのデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めていくべきなのだろうか? 『DXレポート』を著し、日本のDX推進政策を担当している経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 アーキテクチャ戦略企画室長 和泉憲明氏と、コンタクトセンターのクラウドプラットフォームを提供しているナイスジャパン株式会社 日本法人社長 安藤竜一氏の対談をお届けする。
-

(左から)経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 アーキテクチャ戦略企画室長 和泉憲明氏、ナイスジャパン株式会社 日本法人社長 安藤竜一氏
いまだに根強いDXへの誤解
和泉憲明氏(以下、和泉氏):2018年に、ITを中心にしたビジネス変革の必要性を世の中に知らしめたいという思いで『DXレポート』を発表したのですが、実際の反応は期待していたものとは異なるものでした。ITは省力化・効率化のツールではなく競争力強化の道具として捉えるべき、と訴えたにもかかわらず、DXを業務改革の契機として考えるのではなくレガシー刷新の機会として受け取られてしまったのです。これは想定外のことでした。
安藤竜一氏(以下、安藤氏):そもそもの受けとめ方・考え方に「ズレ」があるのですね。実際に、多くの企業がDX推進部を発足し、プロジェクトを立ち上げても、本格的な展開にまで進めないさまをよく見かけます。
和泉氏:その傾向は今も続いており、IPAによる調査分析によれば「全社をあげてDXに取り組む」と言っている企業は、高々8%程度に過ぎません。さらに、メリハリのついた予算配分をしたり、全体最適の観点からシステムを再構築する際に不要なモノを廃棄したりすることができている企業も少なく、ほとんどの企業がDXに未着手の状況に近いようです。
安藤氏:いったい何をどうすればいいのか、社内ノウハウや先行事例を探しすぎて足踏みしているように感じます。
和泉氏:ある会社の経営トップは、デジタルによる変革を「100年に一度の転換期」だと言っています。明治維新並みの変化の時代ということです。幕末に活躍した人々は、はたしてコンサルや先行事例に頼ったでしょうか? 今の経営にこれまでのITを継ぎ足しているうちは、古い経営のままです。デジタルという用語に象徴される新しいITを中心に経営スタイルを変革させてはじめて、新たな経営が生まれるのです。
-

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 アーキテクチャ戦略企画室長 和泉憲明氏
「分析力」がコンタクトセンターを進化させる
安藤氏:コロナ禍による顧客接点の減少によって、コンタクトセンターへのニーズは飛躍的に高まっています。今は史上もっともオペレーター数が多い時代かもしれません。在宅勤務のなかでどのように効率化を進めていくのか。どの場面にAIチャットボットを導入すべきか。検討が始まった一方で、デジタルの力でカスタマーサービスそのものを刷新していこうという動きには温度差があるようです。
私は「おもてなしこそ科学である」と思っています。顧客の姿をより鮮明化・データ化していき、数値管理ではなく分析によって、伝統的な企業文化をさらに磨き上げる時代が来たのではないでしょうか。
和泉氏:私も前職は学者なので、そういった分析への姿勢にはとても好感が持てます。「おもてなし」という言葉を単なるラベルとして使うのではなく、どれだけ具体的に言い換えられるか、経営としての実像にまで落とし込めるかどうかが重要です。
「数値管理ではなく分析」とおっしゃいましたが、たとえば、健康診断のように数字を定期的に見るだけでは、これは経営とは言えません。「健康のためにヨガがいい」「半身浴が効果的」といった仮説を立てて実践し、その効果を数字の変化で評価して、次の仮説立案に活かすことこそが経営力の発揮でしょう。
安藤氏:技術の進歩によって、データを扱うレベルもスピードもどんどんと高まっています。仮説立案からクロス分析までを何倍速にもすることによって、「うちの弱点、本当はこれなんじゃないの?」「実はこれが強みだったのかも」といった新たな価値が見えてきます。
-

ナイスジャパン株式会社 日本法人社長 安藤竜一氏
和泉氏:そういった顧客分析のためのインフラ構築を「本当に自社で直接担当すべきか?」は各社が考えるべきポイントかもしれません。
たとえば、関西では駅の売店のおばちゃんは、ただ「缶コーヒー」と言っても売ってくれないことがあります。「ぬくいのもあるで」「牛乳多いのにしよか」などと言って、どのようなものが欲しいか聞いてきます。お節介といえばお節介ですが、立派なマーケティングでもあるわけです。一方で、関東にある駅の売店では会話どころか、どんどん自動化が進んでいます。
東西どちらが優れているという話ではなく、お客さんの声を自分で聞くべきかどうか、決断すべきということです。コア業務かノンコア業務か、競争領域か非競争領域か自ら判断する、ということが重要です。
今、『DXレポート2.1』をまとめているのですが、そこでは「足し算のDX」と「引き算のDX」を示そうと思っています
経営にITを継ぎ足すのではなく、ITの思想を経営に取り入れる
安藤氏:とても興味深いキーワードが出てきました。「足し算のDX」「引き算のDX」とはどういう考え方なのでしょうか?
和泉氏:最先端のテクノロジーによって新たな事業を構築することが「足し算のDX」とすれば、マルチサイドプラットフォームを利用することによって、自分たちでやっていたオペレーションを切り離すことが「引き算のDX」です。
たとえば、セキュリティ保護はどの企業にとっても重要課題ですが、すべてを自社でやるだけではなく、SOCサービスを利用するという選択肢があります。なんでも拡大するばかりではなく、「割り勘」にして済ませてしまう領域を決めることも、経営センスが発揮される場面ではないでしょうか。
安藤氏:手放すことも含めてDXなのですね。コンタクトセンターのDXに向けて志をともにしているお客様から、以前、「ひとつのことに囚われて身動きができなくなるくらいなら、勇気を持って脱ぎ捨てる」ことが大事だと聞きました。
和泉氏:とても素敵な考え方ですね。どれだけの人が、その自社事業に愛着を持っているのでしょうか。コア領域は自分たちで開発しつつ、ほかの部分はAPI連携によって機能させる。こういった現代ITの思想を、経営こそ取り入れるべきだと思います。
安藤氏:どうも現場には「効率化によって仕事がなくなるんじゃないか」といった「引き算のDX」に対する怖れがあるようです。デジタルの活用によって、個々人がどのようなキャリアアップに繋がるのか、そういった具体的な未来を示していくことが大切なのでしょう。
和泉氏:会社の黎明期にはトップダウンが、ある程度成熟したらボトムアップがアプローチとして有効ですが、今のような大転換期には「ミドルアウト」の仕掛けが必要となります。トップがビジョンを言うだけでも、現場で各論を改善するだけでも足りません。中心となるコンセプトをもとに、巨大で具体的な設計図を示していくのです。
経済産業省としても、上から目線で何かを言うのではなく、変化を姿勢で見せる必要があると思っています。『DXレポート』も、悠長に数年おきに出すのではなく、どんどんアップデートしていって「日本のDX標準パッケージ」を広めていきます。
安藤氏:楽しみにしております。我々ナイスジャパンも、クラウドの技術によって、大企業だけでなく地方の中小企業にITソリューションを届けられるようになりました。今後も、ときに引き算のDXを促すことも必要という気概を持って、「分析」の視点から、日本のコンタクトセンターにおけるDXを支援して参ります。
ナイスジャパン株式会社
通話録音装置の技術で1986年に創業。現在は音声録音ファイルの分析で培ったテクノロジーを活かし、コンタクトセンターのクラウドプラットフォーム(CXone)など、多岐にわたる製品を展開している。日本法人の設立は2004年。
[PR]提供:ナイスジャパン