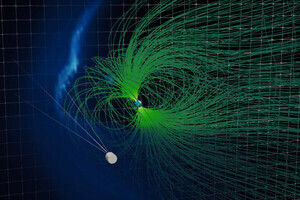収支から見た日本の林業の現状
まず、林野庁の「森林・林業白書」に公開されているスギの価格について見てみよう。下図は、スギの山元立木価格・丸太価格・製材品価格の推移だ。山元立木価格とは、山に立っている木1m3(基本的に木材の材積はm3換算で示される)あたりの価格であり、伐採や運搬などの素材生産にかかる経費を控除したものだ。平たくいえば、素材生産者が森林所有者に払う金額で、森林所有者はこの収益を元手に新たに造林や森林管理を行うのだ。ただし、この価格はあくまで「山元立木価格=丸太価格-経費(伐採や運搬費)」としたもので、正確に見積もられたものではない。
続く丸太(原木)価格は、原木市場から製材所などの川中が購入する価格である。製材品価格は、角材や板材などの木材製品の価格を指す。つまり、住宅に使用される梁や柱の元となる材料だ。現代の木造軸組住宅の90%以上は、大工が角材を建築現場で手加工するのではなく、あらかじめ工場で機械加工された角材を使って建てられる。そして、この機械加工工場をプレカット工場という。
さて、先ほどのグラフからわかる通り、山元立木価格と丸太価格は年々下落している。
また、原木生産にかかる収支について見てみると、下刈や地拵え、苗木代といった造林初期にかかる費用(造林初期費用)は186万円/haなのに対し、山元立木価格は101万円/haである。現状、森林所有者の懐はプラスにはならないのだ。そのため森林所有者は、50年間育てても赤字になるビジネスに関心を示さなくなり、管理が行き届かない森林もちらほら見られるようになった。
そして、その解決策の大黒柱となるのが補助金である。これは、国や自治体からの補助により森林経営を成り立たせようというもので、伐採や搬出を担う素材生産者にも補助金が出る。川上の事業すべて体が補助金に依存した経営ではないにしろ、基本、川上は補助金ありきというのが日本林業の現状である。
生産・流通コストが高い日本市場を
日本の場合、流通コストが高いというのも山元立木価格を押し下げている原因の1つではある。オーストリアと比較すると、その差は歴然だ。この差は、もちろん地形によるものもあるが、労働者1人が1日で生産する丸太の量がまったく異なるために生まれた。
オーストリアの場合、車両系の作業システムで30m3~60m3/人日、架線系で7m3~43m3/人日なのに対し、日本は間伐で約4m3/人日、主伐で約7m3/人日である。国もこれを受け、林業の生産性を向上させるために高性能林業機械の導入を推進している。
しかし、ここで1つ疑問が残る。木を切るだけでは赤字の事業体が多い中、高性能林業機械をどうやって購入するのだろう。高級車以上がザラな機械であるがゆえ、その出処は一体どこだろうか。
そう、もちろんここにも補助金が出ている。効率化・低コスト化を図る名目だ。
さて、日本の林業の現状について、ざっくりとだが把握できたのではないだろうか。実際の現場は日本全国各々であるため十把一絡げに林業を語ることはできないが、データやネットから拾える情報をまとめるとこのような現状だ。
国は林業の成長産業化を叫んでいるが、補助金を出し続けることで成長産業に繋がるのだろうか。その行く末が気になるところだ。今回は木材の川上について話したが、次回は川下、すなわち建築や工務店の立場から木材を使うことについて触れようと思う。木材の大口先である建築側の人間は、一体木材をどのように見ているのだろうか。