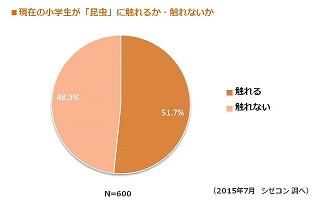昆虫の持つ特殊能力を五感を使って体感
「昆虫の生態」、そして4つ目のチャプター「昆虫の能力」と続くが、ここからは昆虫が、どこに棲み、どのように食べものを食べ、交配相手を見つけ、敵から身を隠し/守って生きているのか、はたまた、その身に秘めた人間にはない優れた能力とはどのようなものか、といったことをいろいろな角度から知ることができる。
中には実際に五感を使って体験できるコーナーもあり、昆虫の生態を、その身をもって体感することも可能だ。
そして5つ目の「昆虫研究室」。昆虫を取るために必要なさまざまな道具の紹介から始まり、標本の作り方の紹介と続くのだが、圧巻なのがその後の標本回廊のコーナー。約5万点とも言われる、昆虫標本が四方の壁全面に配置されており、しかもそれは1人ではなく、複数の人が個別に集めたものをお借りしてきたものもあるとのことで、標本の傾向を見て、それぞれの人がどのように考えて集めたのか、といった収集方針から、どのような人物性なのか、といったことを感じることができる面白さもある。
-

-

-
昆虫研究のはじめの一歩は採集から、ということで、さまざまな採集のための道具類の展示も行われているほか、昆虫採集におけるマナーについての説明もある。特別展「昆虫」で昆虫の世界が気になった人は、大人も子供も、ぜひ、このマナーについての一文を読んで、昆虫採集に臨んでもらいたい
このほか、安全管理などの観点から管理担当者が最後まで公開をためらったという、天然記念物「ヤンバルテナガコガネ」のホロタイプ標本(その種の基準となる標本で、1つの種につき世界に1点のみ)や、展示会の企画チームが2018年2月にマダガスカルに赴き、発見に成功した「セイボウ(青蜂)」というハチの未記載種(未発表の種)の標本も展示されている。
この未記載種は、今後、学名がつけられ、論文に発表されることで、正式に新種と認定される。今回、同展示会では、来場者に広く、新たな昆虫を見つけ、固有の名前を与えるという作業は、分類学上およびその生息地のほごに向けて、非常に意義のある最初のステップであるということを知ってもらいたい、という想いから、応募者1名の名前(名字もしくは名前)を昆虫の学名に付けるキャンペーンを実施(8月12日、当日消印有効)。後日開催されるネーミングセレモニーには、昆活マイスター(オフィシャルサポーター)の香川照之氏も主席する予定だという。
昆虫は先生だ
同展示会の面白さの1つに、大の昆虫好きとして知られる香川照之氏の昆虫に対する熱い思いも聞くことができる会場内で借りることができる音声ガイドの存在がある(550円)。
各コーナーの説明を聞けるのは当然だが、香川氏が、昆虫をどのように愛でているのか、昆虫を採るということに対する心構え、そしてこの企画展に対する思いなどを熱く語ってくれている様を聞くこともできる。また、「昆虫はなんでも教えてくれる」「昆虫は先生だ」「今週はすばらしい、すごい、美しい」と音声ガイド内で昆虫を延々と賞賛し続ける同氏が、オフィシャルサポーターとして、自身が考案した展示も第2会場に展示されている。第2会場は、上述したバイオミメティクスが、どのようなものか、といったことを体験できたり、CTスキャンのような技術を活用して得られた昆虫の3D画像「3D昆虫」(36種類)を実際に360°回転させて、普段は見れない細部や裏側をのぞき見することができるコーナーなどが用意されている。
なお、同展示会の会期は2018年7月13日~10月8日まで(会期中の7月17日、9月3日、9月10日、9月18日、9月25日は休館日)。開館時間は9時~17時となっている(入場は閉館30分前まで。日にちによっては開館時間の延長がある)となっている。
特別展「昆虫」
- 会 期:7月13日~10月8日(休館日7月17日、9月3日、9月10日、9月18日、9月25日)
- 時 間:9時~17時(金曜日および土曜日は20時まで開館。8月12日~16日、19日は18時まで開館。各日ともに入場は閉館時刻の30分前まで)
- 入場料:一般・大学生1600円、小・中・高校生600円(未就学児は無料)
- その他:金曜・土曜限定ペア得ナイト券は2名1組2000円(17時以降、2名同時入場限定。2名の組み合わせは男女問わず、当日会場販売のみ)