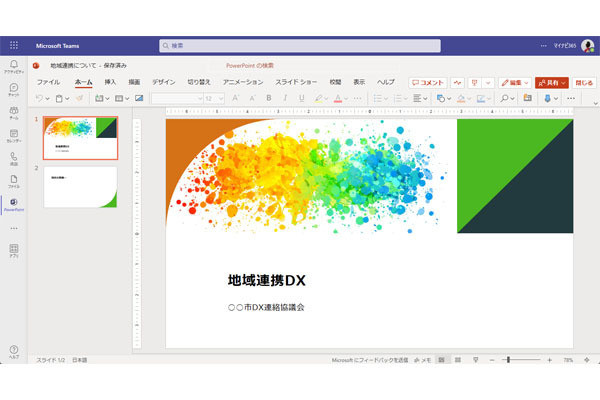この連載はWindows Server 2012/2012 R2の2023年10月の製品サポート終了に合わせ、移行先や「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」について取り上げてきました。最終回となる今回は、早ければこの1年以内に利用可能になる、マイクロソフトの次世代のプラットフォームについていくつか取り上げます。キーワードは、「AI(人工知能)」、「Windows Server vNext」、「Windows 11」の3つです。
Azure AI
クラウドコンピューティングが登場して20年近く経ちました。当初は法規制のためデータを外部に置けない、セキュリティが怖い、ネットワーク遅延の問題など、クラウドのビジネス利用は困難という考えや、根拠のない理由で、クラウド化に踏み込めなかった企業が多かったと思います。しかし、今やクラウドのビジネス利用の障壁の多くは取り払われ、重要なプラットフォームの選択肢になりました。
現在、Microsoft Azureを始めとするパブリッククラウドの話題の中心は、生成AIと言っていいでしょう。2022年11月末にOpenAIがChatGPTを発表してはずか1年で、生成AIは劇的に進化を遂げ、世界を変えつつあります。
マイクロソフトはOpenAIに巨額投資を行い、自社の製品やサービスに次々にGPT-3やGPT-4ベースの生成AIを統合しています。その皮切りは、「Azure OpenAI Service」を始めとするAzure AIサービスです。Azure AIサービスを利用すると、商用データを保護しながら、最先端でミッションクリティカルなAIソリューションをビジネスで活用することができます。
Azure OpenAI Serviceは2023年1月にすでに一般提供が開始されており、すぐにAzureにデプロイできるサンプルコードも豊富で、AIを自社の業務システムやカスタマーサービスに組み込むことで効率化やサービス品質向上に実用レベルで活用できる段階にあります。例えば、自社のカスタマナーサービスにAIを導入することで、サービスリクエストの大部分をAIに解決させ、より重要、緊急の問題に人的リソースを効率的に投入することができるでしょう。
Azureでは、自社独自のAIサービスの構築、実行だけでなく、プログラム開発やセキュリティ、データ分析にもAI機能が次々に組み込まれており、日々、進化しています。例えば、Visual Studioから拡張機能としても利用可能なGithub Coplilot Enterpriseの一般提供(2023年2月)、データ移動からデータサイエンス、リアルタイム分析、ビジネスインテリジェンス、そしてAIまでのすべてをカバーするMicrosoft Fabricの一般提供(2023年11月)、Copilot for Azure、Copilot in Microsoft Fabric(Copilot for Data Science and Data Engineering、Copilot for Data Factory、Copilot for PowerBI)、AzureポータルのAIベース検索、Azure AI Studio、Copilot in Power Platform(Copilot for Power Apps/Power BI/Power Automate/Power Pages)のプレビュー提供などです。
昨年11月のOpenAIのアルトマン氏解任/復帰騒動、それに続く各国の独禁法抵触調査開始の噂、マイクロソフトやOpenAIに対する訴訟などは、マイクロソフトのAIサービスの不安要素になるかもしれません。しかし、体制に変更はあるかもしれませんが、すでに一般提供され、実用レベルで運用環境で利用できる以上、Azureのサービスそのものの品質が低下したり、廃止されたりすることはないと思います。OpenAI以外をベースにした数多くのAIサービスも登場しており、この分野の技術革新は今後も急速に続くとみられます。
Copilot、Copilot in、Copilot for
すでにAzureや開発環境、データ分析関連のCopilotの話がたくさん出てきましたが、生成AIベースの機能やサービスは、Windowsデスクトップにも次々に追加されています。
2023年11月1日には「Copilot for Microsoft 365」(旧称、Microsoft 365 Copilot)が、2023年12月1日には「Copilot」(旧称、Bing Chat/Bing Chat Enterprise)が一般提供されました。
Copilot for Microsoft 365は、Microsoft 365アプリとサービスと連携して生産性を向上する有料のAIサービスです。CopilotはMicrosoft EdgeやEdgeサイドバーから利用できるAIチャットです。さらに、2024年1月からは、Copilot for Microsoft 365の個人向け版であるCopilot Pro(月額3200円)の提供も始まりました。
また、現在、Windows 11バージョン22H2以降に組み込まれOSと連動する「Copilot in Windows」(旧称、Windows Copilot)をプレビュー提供中です。Copilot in Windowsのサブセット機能(OSとの連動機能なし)は、Windows 10バージョン22H2以降でもデバイスで利用可能になり次第、追加される予定です。
-

OSやアプリと連動して作業を補助してくれるWindows 11のCopilot in Windowsプレビュー(画面左)とWindows 11へのリプレース促進のために提供される、O連動機能を持たないWindows 10のCopilot in Windowsプレビュー(画面右)
これらのAIベースの機能やサービスを利用することで、Webやドキュメントの要約や翻訳/英訳、ドキュメントの作成、Windowsの設定やトラブルシューティングを瞬時に行うことができるようになります。AIで短縮された作業時間を、別のより重要なタスクに向けることができるのです。
また、2023年11月からプレビュー提供が始まったMicrosoft Copilot Studioを使用すると、Copilot for Microsoft 365をさらにカスタマイズしたり、独自のCopilotを簡単に作成することができます。
企業向けのCopilot、Copilot in Windows、Copilot for Microsoft 365は、AzureのAIサービスと同様に、商用データが保護(プロンプトに入力されたデータをトレーニングに再利用しない、入力データが外部に漏洩することがない)されます。企業向けCopilotを活用することで、エンドユーザーはオフィス作業の生産性が向上し、IT担当者は負担が軽減されるでしょう。
Active Directoryを再設計、Windows Server vNext
従来、オンプレミスのサーバーが担っていた役割の大部分は、現在、クラウドサービスで完全に置き換えることができるようになりました。しかし、オンプレミスのサーバーの重要性がゼロになることはありません。
例えば、クラウドに100%依存してしまうと、ひとたびインターネット回線に障害が発生すれば、業務は停止してしまうでしょう。ビジネス継続性のためには、オンプレミスとクラウドの両方にまたがるハイブリッドなシステム基盤が優れています。
マイクロソフトは2023年11月に開催した年次イベントMicrosoft Ignite 2023でWindows Server長期サービスチャネル(LTSC)の次期バージョンの新機能について、多くの発表を行いました。
一世代前のWindows Server 2019は2018年9月のリリース、現行バージョンのWindows Server 2022は2021年9月のリリースなので、このサイクルに従うなら、Windows Server LTSCの次期バージョンは2024年後半にになると想像できます(製品名/バージョンは未発表)。
次期バージョンでは、登場から24年たったActive Directoryに、大幅な変更が加えられます。データベースが再設計され、これまでの8Kページサイズから32Kページサイズになり、より長いデータを格納できるようになります。さらにNUMAをサポートするようになり、メニーコアを活用してドメインコントローラーを大幅にスケールアップできるようになります。
また次期バージョンでは、現在、AzureおよびAzure Stack上のWindows Server 2022 Datacenter: Azure Editionでのみ提供されているホットパッチ機能とSMB over QUICが、オンプレミスやAzure以外のクラウド上のインスタンスでも利用可能になる予定です。これにより、ミッションクリティカルなワークロードの長期運用やインターネットを介した安全なSMB接続がどこからでも利用可能になります。
Hyper-V関連では、GPU-P(GPU Partitiong)がサポートされ、複数のVMでのGPUの共有と、ライブマイグレーションに対応し、AIに不可欠なGPUの計算能力を、ミッションクリティカルなワークロードに活用できるようになります。
ファイルサービスとストレージ関連では、SMB認証/接続のセキュリティ強化(NTLM無効化オプションの提供、SMB暗号化をすで定で要求など)、NVMeストレージに最適化されたドライバーの提供によるIOPSの大幅な向上、ソフトウェア定義のストレージのさらなる機能強化などが行われる予定です。SMBのセキュリティ強化はサポート中のWindowsのSMBクライアントでも行われるため、サポートが終了したレガシバージョンとの接続性に影響が出る可能性があり、注意が必要です。
さらに、次期バージョンではライセンス購入方法にも新たなオプションが追加されます。現在の買い切りのWindows Serverコアライセンスに加えて、すでにSQL Server 2022で導入されているサブスクリプション購入モデルが追加されます。
Windows 11非対応デバイスのためのWindows 10 ESU
現在、サポート期間中のWindowsクライアントは、Windows 10バージョン21H2(Enterprise/Educationのみ)、Windows 10バージョン22H2、Windows 11のみです。そして、Windows 10の製品サポートは2025年10月14日に終了します。
Windows 10からWindows 11へのアップグレードは無料ですが、Windows 11のシステム要件(プロセッサモデル、TPM、4GBメモリ、UEFIセキュアブートなど)を満たさないデバイスについては、Windows 11にアップグレードすることができません。そのため、かなり多くのWindows 10デバイスがサポート終了により、安全に利用できなくなります。
マイクロソフトはWindows 11へのリプレースを推奨していますが、最後の手段として、Windows 7のときと同様に、サポート終了後も最大3年間セキュリティ更新プログラムを受け取ることができる「拡張セキュリティ更新プログラム(Extended Security Update、ESU)」をWindows 10に対して有料または無料で提供する予定です。
Windows 365サブスクリプションのWindows 11を実行するCloud PCにアクセスするWindows 10デバイス、Windows 10を実行するAzure Virtual DesktopインスタンスではESUが無料で提供されます。それ以外については、Windows 7 ESUと同様に、最大3年間、年次サブスクリプション購入でWindows 10 ESUを利用することができます。
Plan for Windows 10 EOS with Windows 11, Windows 365, and ESU
Windows 10デバイスをCloud PCにアクセスするためのシンクライアントとして利用するなら、無料で2028年10月まで利用を継続できるということです。また、ESUはこれまで企業向けのプログラムでしたが、Windows 10 ESUは個人向けの提供も検討されているようです。個人ユーザーであっても、もう少し使い続けたいという場合、そのコストが見合うものであれば利用しない手はないでしょう。











](images/005.jpg)