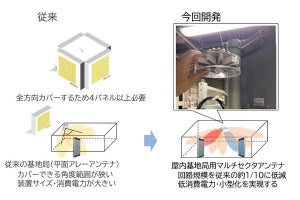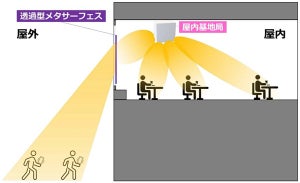ソフトバンクは2023年3月3日、東京海洋大学らと共同で、可視光の無線通信技術で水中ロボットをリアルタイムで遠隔制御売る実証実験に成功したことを発表しました。
Beyond 5Gや6Gに向けては海中、ひいては水の中でも無線で通信できることが求められていますが、ソフトバンクらが実現した可視光による水中無線通信は、どのような点にメリットがあるのでしょうか。
光の明滅を用いて可視光による通信の課題をクリア
Beyond 5G、6Gに向け携帯各社がさまざまな研究開発を進めており、中でも最近では衛星通信やHAPSなど、上空から広域のエリアをカバーする取り組みが注目されています。
しかし、もう1つの未開拓エリアである海、ひいては水の中をカバーすることも6Gでは求められており、携帯電話の電波が届かない海中で無線通信を確立するための技術研究をいくつかの企業が進めています。
その1つがソフトバンクです。同社は2023年3月3日に、東京海洋大学の後藤慎平助教らの研究チームと、北海道厚岸翔洋高等学校の柴田耕一郎教頭の協力を得て、可視光の無線通信技術により水中の狭い場所を移動する水中ロボットをリアルタイムで遠隔制御する実証実験に成功したと発表しています。
この実証実験の大きなポイントは可視光、つまり光を用いていることです。冒頭でも触れた通り水中では電波による通信が難しいので、一般的には音響通信、つまり音波が用いられていますが、ソフトバンクのIT-OTイノベーション本部 サービス基盤統括部 サービス基盤企画部 サービス基盤企画1課 担当課長の今井弘道氏によると、音波による通信は伝搬速度が遅いので通信速度を高めるのが難しく、またノイズやマルチパス(反射波)の影響を受けやすいなど、さまざまな課題を抱えており、とりわけ水深が1m程度の浅い海域ではマルチパスの影響を強く受けて通信ができないことが多いのだそうです。
そこでソフトバンクでは、音波の代わりに可視光を用いた通信の研究を進めているとのこと。ですが可視光による通信も、発信する側と受信する側の双方に光が見えていることが求められるため通信距離が100m程度に限られる、照射角が狭いレーザー光を用いる場合は発信側と受信側の軸を合わせ続ける必要があり、少しでもずれると通信できなくなるなど、いくつかの課題を抱えていました。
その課題を解決するため、今回の実証実験で用いたのがOCC(Optical Camera Communication)というもの。これは光の明滅を信号に変換する仕組みであり、実証実験では送信側が発する光の明滅を受信側のカメラで捉え、コンピューターで画像解析することで水中ロボットを遠隔で制御しているのだそうです。
今井氏によると、OCCを用いる最大のメリットは受信できる範囲の広さであり、光の明滅を判別できればよいことからレーザー光と違って軸合わせを意識することなく、より広い角度での受信が可能だといいます。
それゆえ今回の実証実験では送信側の発光素子にLEDが用いられていましたが、光の色によって減衰の仕方が違うことから最も減衰しにくい青色の光を用いているとのことでした。
また、その仕組み上、親機の光の明滅を複数の子機に同時に受信させることも可能とのこと。それゆえ複数の危機に対して一斉に同じ信号を送るような通信の使い方ができるというのも、OCCを用いるメリットといえるかもしれません。
海洋産業のIoT向け無線通信の早期実現に重点
今回の実証実験は北海道にある厚岸湖で真冬の2月に実施していることから、湖の氷に穴をあけて水中ロボットの親機と子機を約5mの間隔を空けて水中に沈め、親機側におよそ930km離れた場所からThurayaの通信衛星を通じて子機を制御するための信号を発信。それを可視光による無線通信で子機に送り、実際に制御できるかどうかを試しています。
筆者も実証実験が実施される予定の時間に現地を訪れたのですが、そのタイミングではあいにく天候が悪化し、実験が中止となってしまいました。それゆえ実際の実験の様子を直接見ることはできなかったのですが、実証実験に使用した水中ロボットや、地上ではあるものの可視光を用いて通信している様子などは確認することができました。
なお、水中ロボットは東京海洋大学と共同で開発したものとなりますが、多くの部分に汎用の民生品が用いられていることから、一見すると制作は容易なように見えます。ですが後藤氏によると、水中で使用する機器は設計や使用する素材を誤ると水圧で割れてしまったり、海水で腐食したりするなど、多くの故障やトラブルが発生してしまうのだそうです。
そうしたことから後藤氏の研究チームが加わり、実証実験で問題なく動作するよう水中ロボットの素材選定や設計などを実施しているとのこと。ボディの素材からネジに至るまで、場所に応じた最適な素材を選んで設計がなされているそうで、海中での研究活動実績が豊富な後藤氏らのノウハウが存分に生かされている様子がうかがえます。
浅い海域でも使用でき、広い範囲をカバーできるOCCを活用した水中無線通信は多くのメリットがある一方、レーザー光を用いた通信と比べ速度がかなり遅いというデメリットもあります。
ただ、今井氏によると、漁業を主体とした海洋産業を考慮すると映像配信などの高速通信に対するニーズよりも、水温など海中の状況や魚群の発生などをセンサーで通知する、IoT向け通信のニーズの方が大きいとしており、産業向けの海中無線通信を早期に実現するという意味でも今回の実証実験は大きな意味を持つようです。
とはいえ海中での通信が、IoT向けだけにとどまらない高度な通信が求められるBeyond 5Gや6Gにつながっていく技術であることも確かなだけに、今後はより高度な通信を実現する技術の確立も求められることになるでしょう。将来に向けた研究開発も大いに期待されるところです。