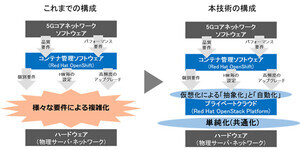衛星通信との干渉によってポテンシャルを思うように発揮できなかった5G向けの3.7GHz帯。ですが衛星通信事業者側の対応によって干渉条件が大幅に緩和され、実力をフルで発揮できるようになりました。条件緩和前と後とで、3.7GHz帯のエリアがどれくらい広がったのかを、KDDIの事例から確認してみましょう。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。
関東は2.8倍、全国では1.5倍のエリア拡大に
サービス開始からおよそ4年が経過してもなお、その実力を発揮できていない日本の5G。中でも大きな要因となっていたのが、5G向けの主要周波数帯である3.7GHz帯が、衛星通信の周波数帯と重複しており、電波干渉を起こしてしまうことです。
この問題に関しては本連載でも何度か取り上げているのですが、衛星通信事業者が衛星と通信するために設置している「地球局」の周辺では、干渉を避けるため電波の出力を大幅に抑える必要がありました。
しかも携帯4社のうち、干渉の影響を大きく受けない4.5GHz帯を割り当てられているのはNTTドコモだけ。3.7GHz帯を持たない他の3社は、5Gでの高速通信を実現するのにとても苦慮していたのですが、2023年末に状況は大きく変わることとなります。
なぜなら3.7GHz帯に関する問題を受け、衛星通信事業者側が地球局の移設を進めてきたからです。干渉の影響が最後まで残った関東圏でも、2023年末に地球局の移設などの対策が進み、3.7GHz帯が抱えていた制約は大幅に緩和されています。
そこで3.7GHz帯の強化に動いている1社がKDDIです。第115回で触れたように、KDDIは開設計画の時点で、携帯4社の中で最も多い3.7GHz帯の基地局数設置を打ち出していました。そして2024年6月時点では、やはり携帯4社の中で最も多い3万8669局の基地局を開設しており、ベースとなる基地局自体の設置はすでにかなりの規模に達しているようです。
衛星通信との干渉条件が大幅に緩和される2024年3月末以降、広域で電波出力の制限を解除したとのこと。これにより、3.7GHz帯の基地局1つでカバーできるエリアが従来の2倍に広がったといいます。
それに加えて、同社では基地局のアンテナの角度も、より電波が遠くに飛ぶよう変更を加えているとのこと。これによってエリアはさらに広がっており、関東圏では一連の施策によって、3.7GHz帯でのカバーエリアが2.8倍に拡大しているとのことです。
また、大阪や名古屋、福岡、札幌といった都市部においても、一連の対策で3.7GHz帯のエリアが拡大。全国で見れば3.7GHz帯が利用できるエリアが1.5倍に広がったといいます。
なぜ関東圏は2.8倍なのに、全国では1.5倍なのかといいますと、関東以外のエリアは元々衛星通信との干渉の影響がなかったり、すでに対策が進められたりしている所も多かったことから、干渉の影響が大きかった関東圏ほどエリアが広がる訳ではないためとKDDI側は説明しています。
KDDIが持つ3.7GHz帯の2つの優位性とは
それでも従来よりも非常に広い範囲で、100MHz幅を持つ3.7GHz帯のポテンシャルを生かした、5Gらしい高速通信が実現できるようになったことは確かです。とはいうものの、3.7GHz帯の干渉緩和の恩恵を受けるのはKDDIだけではなく、4社が公平に受けられるもの。干渉緩和だけで各社のネットワーク品質に大きな差が出る訳ではない印象も受けます。
そこで、KDDIが優位性として打ち出しているのが、先に触れた3.7GHz帯の基地局数の多さです。同社は5Gのエリアを顧客の生活動線、具体的には多くの人が訪れ、混雑が生じやすい都市部の鉄道や商業施設に重点を置いて整備していることから、3.7GHz帯でもそうしたエリアを中心として基地局を密に整備してきたようです。
これに加えて、干渉条件緩和により基地局からの電波出力を強められるようになったことで、屋内や電車内への高い電波浸透を実現できているとのこと。
東京23区を100m四方のメッシュに区切った場合、同社がその基準としている-100dbm以上の電波強度があるエリアは1万を超え、4社の中では最も多い数を実現していることから、電車や建物の中でも高速通信の恩恵を得やすいことがメリットとなるようです。
そしてもう1つ、同社が優位性を持つとして訴えているのが、保有する2つの3.7GHz帯(3700~3800MHz、4000~4100MHz)が周波数的に近い位置にあること。NTTドコモが保有するのは3.7GHz帯(3600~3700MHz)と4.5GHz帯(4500~4600MHz)なので周波数的には離れていますし、今後割り当てが予定されている4.9GHz帯(4900~5000MHz)も、やはり3.7GHz帯とは離れています。
KDDIによると、周波数が近いことで通信機器内の部材を一体で構成することができ、よりコンパクトにまとめられるとのこと。そうしたことからKDDIでは、2つの3.7GHz帯に対応した韓国サムスン電子製の小型Massive Mimo Unit(MMU)を導入予定としており、今後も周波数の優位性を生かした機器の開発・導入を進めていく考えのようです。
ただ、3.7GHz帯の干渉緩和は、5Gの環境改善に向けた初歩の取り組みに過ぎません。3.7GHz帯の環境が大幅に改善した今後は、100MHz幅という広い帯域幅のポテンシャルを生かせるネットワークスライシングの本格提供が求められるでしょう。
そして、そのためには現在KDDIをはじめ携帯4社ともにまったく進んでいない、スタンドアローン(SA)運用への移行が必要不可欠です。
3.7GHz帯を単なるスマートフォンのトラフィック吸収用途で終わらせることなく、5Gの新たな需要開拓につなげるためにも、一層のネットワーク進化に向けた取り組みが求められていることは、間違いありません。