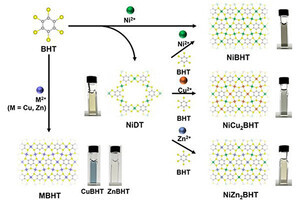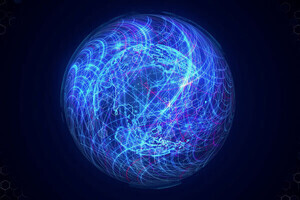あらゆる業種業態の企業変革のキーワードとなっているDX。2018年に経済産業省が公開した「DXレポート」の中に、「各企業は、競争力維持・強化のためにDXをスピーディーに進めていくことが求められている」と明記されており、企業内にDXを推進する部署を設置し、PoC(Proof of Concept:概念実証)を繰り返して、ビジネス変革を模索している企業も増えています。
しかし、日本企業では、有効性は認めつつもDXが進んでいないのが実情です。現場で実行することのハードルの高さを痛感している方も多いのではないでしょうか。本連載では、現場をカメラで撮影して自身の“第三の目”として活用することで、一人一人が日々の意思決定をスピーディーかつ効果的に行っている事例をご紹介していきます。我々はこの仕組みを「映像データによる現場DX」と称しています。カメラ映像を用いて現場の課題をどのように解決したのか。また、どのような副産物がもたらされたのか。業界の垣根を超えて、現場の声と共に解説します。
初回の今回は、DXとはという基本的なおさらいと、映像データを使った現場DXの一例をご紹介します。
DXの取り組みの現状と課題
はじめに、そもそもDXとは何なのでしょうか? 全ての企業が取り組まないといけない問題なのでしょうか? また、推進していく上でどのような課題に直面するのでしょうか?
日本では、経済産業省が2019年に発表した「DX推進指標とそのガイダンス」というガイドラインの発表により、DXが一気に注目を集めました。その書面の中には、以下のように定義されています。
“企業がビジネス環境の厳しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。”
テクノロジーの発展により、あらゆる業界でデジタル技術の導入やデータ化が進み、業務改善の必要性が叫ばれるようになりました。そうした中で、日本では少子高齢化による生産年齢人口の減少から、「いかに現場の生産性を向上するか」が喫緊の課題となっています。従来のビジネスへの取り組み方では、経済規模の縮小と競争力の低下は免れません。多くの経営者はこの状況を打開するため、ビジネスモデルなどを抜本的に見直し、新たな成長・競争力強化につながるDXの取り組みを推進する必要に迫られています。
また、労働者の仕事の質を高め、能力発揮が可能となるような環境を整備しないと、優秀な人材を獲得できないという現実も起きています。その中で、DXの取り組みでの具体的な課題も出てきており、その一部は「DX推進指標とそのガイダンス」でも次のように指摘されています※1。
“顧客視点でどのような価値を創出するか、ビジョンが明確ではない。”
⇒顧客視点でどのような価値を生み出すのか、何を(What)が語られておらず、どのように(How)から入っていることで、業務改善・効率化にとどまっている
“号令だけでは、経営トップがコミットメントを示したことにならない。”
⇒変革を根付かせるための経営としての「仕組み」を明確化し、全社で持続的なものとして定着させることが必要
“DXによる価値創出に向けて、その基盤となるITシステムがどうあるべきか、認識が十分とは言えない。”
⇒ITシステムの話になると、経営者はIT部門に任せてしまうケースが多く、経営者自らがリアルに認識し、必要な打ち手を講じていない
実際に、DX推進担当や現場担当など、業界の垣根を越えてDXに取り組まなくてはいけない当事者の方とお話をすると、「PoCまではたどり着くが、実際、現場への導入は難しい」 「従来のやり方が浸透している現場の仕組みを変えていくのは、ハードルが高い」「取り組まないといけないことは分かっているが、思い切った投資ができない」など、既存の仕組みが成立している中に、新たな仕組みを導入することの難しさや現場の反発に直面し、悩みを抱えている方も多いようです。
※1 矢印の先の説明は、筆者が要約したものです。原文は「DX推進指標とそのガイダンス」を参照してください。
新型コロナウイルスによりDXは加速
2020年の新型コロナウイルス感染症発生以来、緊急事態措置・まん延防止等重点措置の発令により外出制限などの行動規制が実施され、業種関係なく多くの企業で働き方に大きな影響がありました。会議などで人が密集しないようにすることや、一定以上離れた距離での会話が求められるなど、これまでの日常が一変したことは言うまでもありません。総務省は、ICTツール※2を活用した、リモートワーク/テレワークを推進しました。
※2 Information and Communication Technologyの略で、通信技術を活用したコミュニケーションの仕組み。