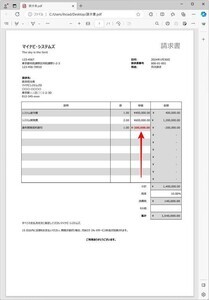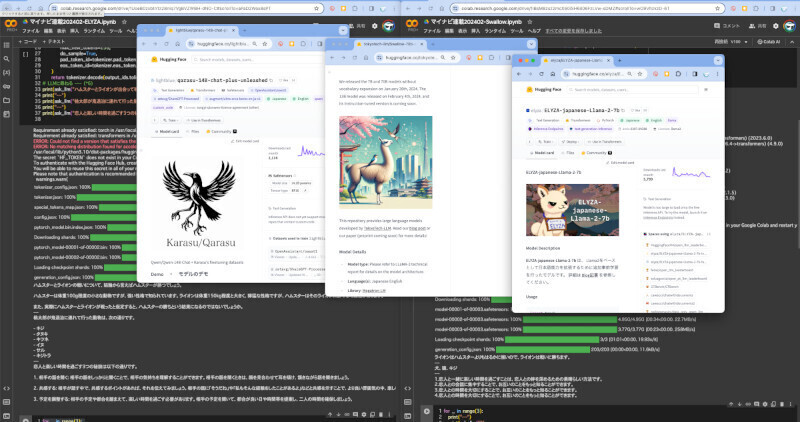開発者目線で語られることが多いプログラミング言語「Python」。しかし、「コードのわかりやすさ」や「学習の容易さ」といった特徴から、ユーザー企業でもPythonの活用が進んでいる。
昨今、多くの企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が進められているが、データ分析のためのツールとして、ビジネスユーザーがPythonを習得するケースも出てきている。
例えば、群馬県沼田市は職員の方々が業務の自動化の実現に向けて、RPAからPythonに乗り換えて、効率化の向上とコスト削減を実現している(参考記事:有償RPAソフトからオープンソースのPythonに切り替えた沼田市、その狙いと効果とは)。
そこで本連載では、開発者ではなく、ビジネスの視点からPython活用についてお届けする。初回となる今回は、Pythonを採用した大規模システム開発を手掛けているグローバルウェイのディレクター 永井謙史氏、プリンシパルエンジニア 小野俊樹氏、Pythonエンジニア育成推進協会 代表理事 吉政忠志氏に話を聞いた。
利用、求人のいずれも増えているPython
企業におけるPythonの活用について紹介する前に、Pythonの需要の最新状況について触れておきたい。吉政氏は、日経クロステックが昨年に行った調査を例に挙げ、「Pythonが使われている分野は広く、各分野で普及が進んだことから、利用の場が広がっています」と話す。
同調査で現在使っているプログラミング言語を3つまで挙げてもらう質問において、「Python」は首位だった。また、複数の言語の中でメインに使っている言語の第1位もPythonだった。
加えて、吉政氏はPythonの求人も増えていると語る。例えば、マイナビ転職の2024年1月14日のPythonの求人情報の集計結果を見ると、Webが最多(37%)で、以前はAI(26%)とほぼ同等だった機械学習が1%と大幅に減少しているという。その背景について、同氏は次のように説明する。
「以前は、企業のニーズがあると見込んで機械学習の学習意欲が高かったのですが、実のところ、大規模なシステムでそれほど利用されていません。DXとデータ活用からデータサイエンスにまでたどりつくのは、リテールなど大規模な企業のみです。データ分析を行いたい企業は多いですが、模索している企業がもっぱらというのが実情です」
Python×Djangoでデジタルプラットフォームを構築
では、企業ではどのような形でPythonが利用されているのだろうか。
グローバルウェイは、企業の既存のシステムを生かしながら、クラウドソリューションを組み合わせて、新たなプラットフォームを構築するというビジネスを展開している。
そうした中、同社はPythonとPythonで実装されたWebアプリケーションフレームワーク「Django」を活用したデジタルプラットフォーム構築に注力している。
永井氏によると、Pythonとフレームワークを組み合わせてスケルトン化することでベースを作っておき、顧客の既存のIT資産に合わせてカスタマイズを行って連携し、プラットフォームを作り上げているという。
永井氏は「Django」を採用している理由として、フルスタックでセキュリティ要件を満たしていること、大規模システム開発の際にコード化しやすいことを挙げた。
Pythonによるシステム更改でリリースサイクルが短縮
一方、小野氏はPython/Djangoによる大手通信会社の法人向けWebアプリケーションのスクラッチ開発を担当した経験を持つ。このプロジェクトは既存のシステムのリプレースだったが、海外のグループが開発したものであることから、改修するにも、機能拡張するにも海外グループの確認が必要で、単価も高いという課題があったという。
そこで、その通信会社はブラックボックス化している部分をホワイトボックス化するため、システムのリプレースを行うことになった。
当時はJavaが強く、PythonでWebアプリケーションを作っている企業はほとんどなかったそうだ。大規模なアプリの開発となると、いろいろなメンバーが参加するため、「コードのわかりやすさ」「保守性の高さ」が求められる。
その点、PythonはJava、Perl、PHPといったプログラミング言語に対し、アドバンテージがあるという。小野氏は「個人的な意見ですが、Pythonは書いたらすぐに確認できるので、スクリプト言語と比べて 楽しいです」と語る。
Pythonによって新たなシステムを構築したことで、以前はリリースのサイクルが1カ月に1回だったところ、1週間に2、3回できるようになったという。「ホワイトボックスになったことで、Pythonだからスピーディーにコーディングできる」と小野氏。開発サイクルが速くなったことで、機能拡張も柔軟にできるようになったそうだ。
開発会社、ユーザー企業の双方にメリットをもたらす
同社はこれまで、Pythonを採用した億単位のプロジェクトとして、以下の実績を持っている。
| 業種 | システムの内容 | プロジェクト規模 |
|---|---|---|
| 通信事業会社 | カスタマーポータルとAPI基盤の構築 | 5億円程度(3年間の追加機能開発含む) |
| 健康機器メーカー | 健康データサービスAPI基盤の構築 | 4億円程度(3年間の追加機能開発含む) |
| 個別指導塾 | 請求入金管理システムの構築 | 3億円程度(保守含め3年間のプロジェクト |
同社は、このような大規模システムの構築にPythonを採用するにあたり、教育に力を入れている。未経験の人には7日間の教育を行い、Python認定試験を受験してもらっているそうだ。「資格取得によって、Pythonのルールに従って構造化できるベースができ、自信につながります」と永井氏は語る。
7年前はPythonを条件にしてもエンジニアが集まらなかったが、現在はPythonの経験を持つエンジニアが増えており、未経験でも応募する人が増えているそうだ。
永井氏は、ユーザー企業にとっても、内製化をキーワードとしたDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に役立つなど、Pythonがもたらすメリットは大きいと語る。
さまざまな調査でエンジニアの支持を得ているPythonだが、ビジネスの現場でも確実に利用が広がっているようだ。