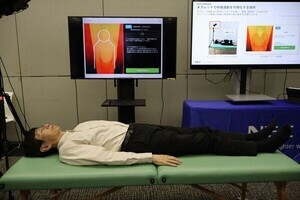インターネットが高度に発達した現代では、知りたい情報をすぐに検索して調べることができる。一方で、本を読むことで得られる想像力やインスピレーションも重要だ。"本でしか得られない情報"もあるだろう。そこで本連載では、経営者たちが愛読する書籍を紹介するとともに、その選書の背景やビジネスへの影響を探る。
第7回に登場いただくのは、不動産業界向けのシステム提供やIT活用コンサルティングなどを手掛けるイタンジの代表取締役 社長執行役員 CEOの永嶋章弘氏。永嶋氏は普段の何気ない行動である"歩く"ことの重要性と健康への影響をテーマにした、経済ジャーナリスト池田光史氏の『歩く マジで人生が変わる習慣』(NewsPicksパブリッシング)を選んだ。
同書によると、哲学者ニーチェや作曲家ヴェートーベンらも"歩く"ことの重大性を説いていたという。Apple創業者の故スティーブ・ジョブズ氏やMeta CEOのマーク・ザッカーバーグ氏も歩きながらの会議を開いていたことで知られる。同書では「座りっぱなしの害はタバコ並」「週3回15分歩くと認知症発症率が40%低減」など、科学的エビデンスを交えながら"歩く"ことについて読者に問いかける。
持ち歩きに便利な電子書籍で多様な知識を獲得
--普段の読書の様子や頻度について教えてください
永嶋氏:普段は寝る前に電子書籍で読むことが多いです。布団の中であとは寝るだけの状態にしてから本を読みたいので、紙ではなく電子書籍を選んでいます。移動中に読む場合もありますが、持ち運びに便利なのでやはり電子書籍を選びます。
年間でだいたい50~70冊ほど読んでおり、目次の中で気になった部分をナナメ読みする場合もあれば、全体を繰り返して読む場合もあります。また、特定の分野に興味を持ち集中的に読み漁ることもありますし、まったく関係のないジャンルの本に手を伸ばすこともあります。
--読む本はどのように決めているのですか
永嶋氏:定期的にAmazonの人気ランキングや最新リリースのページを見て、その中で気になった本を買っています。その他、機会があれば仕事でお世話になった方などに「何かおすすめの本はありますか?」と聞くようにしていて、そこで教わった本を買って読みます。
読むジャンルは、そのときにビジネスで悩んでいることに関するものが多いです。私は2023年11月に当社の社長を引き継ぎましたが、当時は「社長」や「経営」に関する本を読んでいました。その後は「経営戦略」に関する本を読み、最近は経営が実行フェーズに移ってきたと感じるので、経営戦略の実行面をどうするかといったテーマの本を読んでいます。
その一方で、今回ご紹介する『歩く マジで人生が変わる習慣』のように、ビジネスや経営とは関係が無さそうな本も意識的に読むようにしています。なるべくいろいろなジャンルの本を読んで知識の幅を広げたいと思っており、仕事に直接関係が無くても人気ランキングの中でタイトルが気になった本を選んでいます。
--もともと本を読むのがお好きなのでしょうか
永嶋氏:以前は、ほとんど本を読んでいませんでした。若いときに読んで理解できなかった本の内容を、30代になってから仕事や人生の経験が増えたことでようやく理解できるようになったという体験が、本をおもしろいと思うようになったきっかけなような気がします。
仕事の中で経験したものの言語化しきれていない出来事が、本を読むことで言語化できるようになっていく感覚が得られたように感じます。
普段の歩行が与える人間への影響とは
--『歩く マジで人生が変わる習慣』を読んだきっかけを教えてください
永嶋氏:人気ランキングの中でタイトルが気になったことから、同書を手に取りました。普段の経験から、歩行や運動が体にポジティブな影響を与えるイメージがありました。その漠然としたポジティブなイメージを言語化して理解できるのではないかと期待し、読み始めました。
--この本を紹介したいと思った理由を教えてください
永嶋氏:まず、この本では、歩くことが脳の活性化にとってすごく大切であるという内容が書かれています。人類の歴史を見ても、でこぼこした野山を裸足で歩くことで足の裏から伝わる感覚は、脳への良い刺激になるそうです。
トレーニングジムやスポーツジムで日頃から意識的に運動している経営者やビジネスマンは多いと思います。ジムでのウェイトトレーニングやマシントレーニングは筋肥大のためには効率的な動きですが、人間の体にとっては不自然な動きです。筋トレをしすぎて腰痛など不調を抱えている方などもいます。
せっかく運動をするのであれば、人間の動物としての進化の歴史や、人体の構造と機能と問題を理解した方が、健康にも脳への刺激という意味でも、良い影響があることを読者の皆さんにも知ってほしいです。
--何か永嶋さんが実践していることはありますか
永嶋氏:靴を買いました。私が買った靴は、つま先からかかとまでがフラットな構造の「ゼロドロップシューズ」というもので、最近はこれを履いて歩いたり走ったりしています。
女性の靴が特徴的ですが、ヒールのある靴やつま先が細くなっている靴は人間の体の構造としては不自然な体制になりやすいです。ランニングシューズでも、前のめりで反発力が高い厚底の靴があります。この靴は速く走るためには適していますが、やはり体の構造を考えると負担が大きいです。
他にも、あえてでこぼこした山道を走る習慣を取り入れるようにしています。最近はトレイルランなども人気ですが、ジムでのランニングマシンや舗装されたフラットな道ではなく、凹凸のある道を走ることによる足の裏からの刺激を大事にしています。
歩いたらマジで変わった - 生成AIも歩行のメリットに有用
--永嶋さんに何か良い影響はありましたか
永嶋氏:靴を変えたことで今までに経験したことのない部分が筋肉痛になりました。「普段は使えていなかったんだな」という筋肉を実感しました。
また、歩く習慣を意識的に取り入れるようになったことで、アイデアの創出やストレスに上手に対処できるようになった気がします。以前から週末などにランニングをする習慣はあったのですが、最近は意識的に歩きながら考えるようにしたことで、アイデアがまとまりやすくなった気がします。
最近は生成AIの性能も上がっているので、歩くことと組み合わせて活用しています。歩いている間に浮かんだアイデアや考えたことを帰ってからAIに入力すると、要約やアイデアの具体化がはかどります。
--この記事の読者が実践できることはありますか
永嶋氏:皆さん、思っているほど歩いていないので、ぜひ意識して歩く習慣を取り入れてみてください。その際には靴にもこだわってほしいですね。おすすめは「ベアフットシューズ」です。
ベアフットシューズは靴底が非常に薄く、ソールの傾斜が無いので、地面の凹凸や感触がダイレクトに足の裏に伝わります。忙しく散歩の時間が取れない方でも、ベアフットシューズを履いて通勤するだけで、脳への良い刺激が得られるはずです。