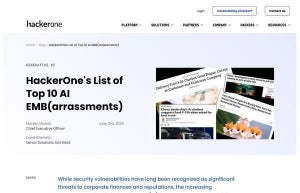今回は著者の失敗経験を紹介します。失敗はビジネスの中での「宝の山」。まずはFail Firstで失敗を学び、そこから改善することが成功につながります。書籍『世界一流エンジニアの思考法』(文藝春秋 著者:牛尾剛)では、成功しようとしまいとまずはやってみて、早く学んで、間違いを修正する精神を「Fail First」と表現していました。これはいいと思い、タイトルにいただきました。
外資系企業の面接では、「今までのキャリアの中で一番大きな失敗は何ですか?」と質問されることが多いです。筆者が面接官として質問することも多いです。経験した失敗の規模の大きさって、キャリアでは大事なのですよ。それだけチャレンジを決行したということなので、ある意味、失敗は勲章です。ただ、同じ失敗を繰り返していては認められません。
もちろんまったく面識がありませんが、筆者は故人のスティーブ・ジョブスも失敗を成功につなげる天才なのかなと思います。NeXTやNewton、ありましたね。あれほどの大きな失敗をMacやiPhoneなどの成功に転嫁できるなんて、やはりスケールが違います。マイクロソフトも今考えてみると、盛大な発表会をして鳴かず飛ばずのものがたくさんあった気がします。BobとかKinとか、その他名前も思い出せない家電との統合技術とか……。
失敗を成功につなげるアジャイルアプローチ
この連載を読んでいらっしゃる方の多くは、単純作業の繰り返しをやっているわけでなく、いろいろな仕事の意思決定を状況に応じて判断しており、いわば答えのない世界にいると思います。そのような世界では、将来の成功のために、取り返しのつかない失敗をする前にコントロール可能な失敗から学ぶことがとても大切になります。
「人生いろいろ」ではないですが、失敗にもいろいろあります。CEOが経営に失敗すると会社は大変なことになるので、それは避けなければいけませんね。お客様を怒らせるような失敗ももってのほかです。筆者の経験で一番まずい失敗は、たぶん人事上の失敗です。人の雇用は長期にわたるので、採用や異動の失敗は尾を引きます。他の人のモチベーションにも影響します。人事は慎重に行う必要があり、仮に失敗であれば早急に是正する必要があります。
私が担当するマーケティング領域は、ある意味で失敗の連続です。想定したターゲットが反応しないといったことが頻繁に起きるからです。そこで何が重要かというと、アジャイルアプローチをとること。まずは実行してみて迅速に修正することです。まったくダメなら、早めに諦めるのです。
残念ながら、私たちには先を見通す予知能力はありません。経験によってある程度は予測できますが、すべてのお客様の気持ちを理解することはできません。データが取得できるような分野は機械学習が進化して、ある程度予測の精度が上がってきましたが、人間相手に、しかも、マスを相手に仕事をしている場合、最初に考えたことがドンピシャ当たることはそれほど多くありません。
そういう意味では、経験と勘でスタートして、予測型のアナリティクスや機械学習を駆使しながら、失敗したらそれを成功につなげていくこと、または早期に中止して痛手を最小限に抑えることが求められるのでしょうね。筆者はマーケティングで失敗したって、マーケティング予算を少し無駄にするくらいで、そんなのまた取り返してやると楽観視しています(CEOに怒られそうですが)。
実施してみて、そこから知見を得て、修正していく、この連続こそが大事なのです。これは、日本で一般的なPDCAとは違います。PDCAはその1周のサイクルが比較的長いので、迅速に正しい方向に舵を切るのが難しいかと思います。やるべきことは、アジャイルです。短期のスクラムを成功のために回していくのです。
「マシュマロチャレンジ」という、チームで実施するゲームがあります。マシュマロとスパゲッティの乾麺を使って、一番高い塔を建てたチームが勝ちというルールです。このゲームに勝利するチームとは、あれやこれやと考えるために時間を使うのではなく、試行錯誤を繰り返すチームなのです。
ただ、失敗には、避けなければいけない失敗と、改善できる失敗、もしくは学習から将来回避できる失敗があります。また、別の視点から、経営へのインパクト度合いも考慮しないといけません。改善でき、かつ、改善して経営に好影響するという範囲の中で、私たちは失敗する必要がありますね。成功のための失敗です。たとえば、日々のオペレーションなどがそうだと思います。
Worked Well / Did Not Work Wellで結果を振り返る
ではここから、(多少の)失敗から回復するための方法を紹介します。筆者は仕事柄、オペレーションで四半期のレビューや月ごとのレビューを受ける機会が多いです。そのときに特に力を入れるのは、Worked Well(うまくいった点)とDid Not Work Well(うまくいかなかった点)です。
Worked Wellは、うまくいった点を認め、今後も継続する、他のグループにベストプラクティスとして共有する項目です。Worked Wellは褒められてとても気持ちいいですが、筆者がさらに注力するのはDid Not Work Wellの方です。これは実行してみたけどうまくいかなかった点です。なぜなら、ここが宝の山だからです。実施していないことについては、機会やチャレンジとして列挙します。
Worked WellもDid Not Work Wellも、うまくいったかうまくいかなかったかの判断が必要なので、基本はKPIをベースにして、100%以上達成すればうまくいった、95%以下であればうまくいかなかったと定義します。この区切りは企業によって異なります。
ここは客観性が大事です。そして、Did Not Work Wellの項目ごとに、次の月や四半期にどのような修正を加えるのかのプランを作っていきます。それを実施して、またKPIをチェックして、という繰り返しのアプローチを取るのです。筆者の欠点としてWorked Wellを少し軽視する部分があり、Did Not Work Wellに気持ちが行きがちなことです。それでは周りのモチベーションが上がらないので、注意するようにしています。
もちろん、失敗すると筆者も落ち込みますよ。でも、失敗の原因を客観的に探り、その対策を打つことで、落ち込みも軽減できます。その対策がうまくいけば喜び倍増です!そういった意味でも、成功への執念というかモチベーションの維持も大事です。人が仕事でパフォーマンスを出すためにはスキルに加えてモチベーションが大事だと、「シチュエーショナル・リーダシップ」というトレーニングが教えてくれたのを思い出します。
営業現場においては、失注もある意味で失敗になります。提案内容や進め方、競合の出方など、失注から学ぶことは受注よりもあるかもしれません。営業の人はついつい隠したがりますが、B to Bにおいては、受注率は3分の1とか、4分の1とかなのです。ですから、失注は当たり前のことで、そこから学ばな"損損"ということです。価値ある失注を。
失敗から学ぶために
失敗から学ぶためには、組織として失敗を許す環境作りがとても大事です。失敗が非難されるようでしたら、「石橋を叩いて、渡らない」みたいに、失敗する前に失敗しそうなことを実行しなくなります。それでは革新的なことはできません。
心理的安全性について書かれた書籍『恐れのない組織 心理的安全性が学習・イノベーション・成長をもたらす』(英治出版 著者:エイミー・C・エドモンドソン)によると、失敗が多いチームほどパフォーマンスが高いのだそうです。マシュマロチャレンジと同じですね。実際は、失敗が報告されるチームほどパフォーマンスが高いということです。
同書では、成功するためには、意見をオープンに言う、失敗を許容する組織作りが重要だと述べられています。さらには、それが人の維持にもつながるとのこと。ぜひ、興味があれば読んでみてください。
失敗が堂々とオープンに話せ議論できるような環境であれば、オープンな意見も言いやすいのではないでしょうか。失敗はチャンスの芽です。そして、その芽が成長する環境作りも大事だということです。