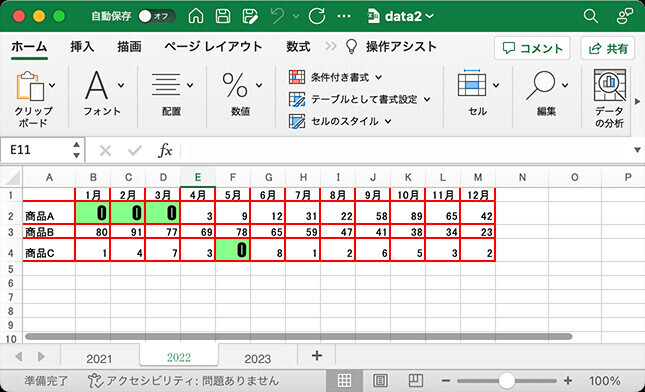本連載の第1回・第2回では、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する組織であるDXMOの概要と構築方法を、第3回ではDXケイパビリティ強化に必要な取り組みについて、また第4回では全社DXのアジェンダとなり得る「データドリブン経営実践」に必要な取り組みについて紹介しました。
5回目となる今回は、製造業におけるDXについて、重工業、産業機械、プラントエンジニアリング等に関する業界エキスパートである丹羽 正、相磯浩史、能登大輔の対談によってお伝えします。モデレーターは、Transformation Strategy/Senior Managerの鈴木一真が務めます。
進んでいるとは言い切れない製造業DX
鈴木: 本日は、製造業におけるDXトレンドについて、お話いただきます。例えば、サービスの付加価値を高める目的とする攻めのDXと、コスト削減が目的である守りのDXといった区分けをするならば、製造業はどのような状況と考えますか。
丹羽: 現状として、コスト削減が目的である守りのDXが主流となっているのではないかと推察します。PwCには攻めのDXに関する相談もいただきますが、会社として攻めのDXをするための準備が整っていない企業が多いと感じます。
丹羽: まず大前提として、製造業の中でも重工業やプラントエンジニアリングといった業種の企業はコモディティ製品を製造しておらず、コモディティではない製造こそが企業の専門性や優位性の源泉であるという思想を持っています。こうした企業ではDXを推進する上で新規ビジネスの創出を掲げたとしても、プロダクト起点で検討してしまう傾向があり、プロダクト自体をどのように利用するかという発想にとどまってしまっていることがあります。
具体的な例で申し上げると、機械にセンサーを付けるところまでは実施するが、センサーから得られたデータは何を意味するかというアナリティクスの領域までは取り組みを進められていない、といったケースがあります。
相磯: なお、ここ2年ほどにフォーカスすると、新型コロナウイルス感染拡大の影響により売上が減少し、守りの姿勢を取らざるを得ない状況にある企業があることも事実です。
鈴木: 製造業の現状において、DXへの取り組みができている範囲とできていない範囲があるように感じることもありますが、いかがでしょうか。
相磯: 全体的に言えることは、事業領域により取り組みの成熟度に差があるということです。コングロマリット的な重工業で例えると、ある事業ではセンサーを付与し、販売したモノに対して保証サービスを提供するような取り組みが進んでいます。また別の事業では、データを取得するにもアナログ作業がかなり残っている状況で、DX化が十分進んでいない印象です。
能登: プラントエンジニアリング企業においては、情報の可視化までは実現できていますが、それ以上のDX施策は現在進行形であるという見立てです。そうした状況を鑑み、昨今は、例えば設備管理や保全の領域において従来主流であった定期的な点検を、AIの活用により予兆を検知し、定期的ではなく必要な時に点検を行っていくような取り組みを行っています。
また、熟練のオペレーターが不足していることから、XR等のデバイスを活用し、ナレッジの保存やマニュアルの自動化といった技術継承への取り組みも行われています。なお最近のトレンドとして、操業データ活用に向けたセキュリティ対応にも関心が向けられています。
鈴木: 領域ごとに差があるということは、領域横断での取り組みはまだ下火と言えるということでしょうか。
相磯: 例えば、情報共有会を実施している企業はあります。そこでは成功事例の共有などが行われていますが、全社で一気呵成に取り組みを進めるようなことを計画しているわけではありません。事業部によりビジネスが異なるため、全社的に進めることは難しいという雰囲気があります。
丹羽: 領域もさることながら、社長を含めたトップマネジメントによる特色もあります。例えば、AIやロボティクスといった領域に精通していたり、あるいは過去にDXを生業とする企業に在籍していたりするような方がマネジメント層にいらっしゃる場合、DX推進が捗っているようなケースがあります。
製造業におけるDXの課題~目的意識と人材~
鈴木: もう少し踏み込んだトピックに移らせてください。製造業という文脈においては、特有の課題やよくある課題というのは、どういったものがあるのでしょうか。
丹羽: 例えば重工メーカーでいうと、DX推進の課題は一般的に言われている課題と大きな差はありませんが、あえて言うなら目的の不明確さが課題として挙げられると考えます。また、部分最適な取り組みや個別システムの更改といった取り組みに落ち着いてしまっている状況も散見されます。そうしたケースにおいては、全社や事業といった階層が異なるセグメント単位を意識しながら、DXの大目的を定める必要があります。デジタル化は進めているが、企業をトランスフォーメーションする段階まで進んでいるかを考える必要があります。
丹羽: デジタル人材の不足もよくある課題です。業界・企業自体がクローズドな潮流を持ってしまっている場合、デジタルに明るい人材や最新テクノロジーにアンテナを張ることができる人材を、内部で育成することも難しく、また外部から登用することも難しいという状況が生まれてしまいます。
相磯: とはいえ、製造業を牽引してきた各企業には優秀な人材が多いため、時間をかければDXを進められるはずであるものの、そのスピード感が不足しているというのが見立てです。そうした中で、われわれPwCのような外部リソースを活用することでスピード感を生み出し、結果としてDXによる効果の発現を早期化することで、外部リソース活用の費用をペイするという形で提案をすることも多いです。
丹羽: DXを推進する人材は、事業部側で擁立可能であれば、まずは事業部側でDXを推進すべきです。一方で、外部登用を含めコーポレート側で人材を獲得可能なのであれば、その人材を事業部側に派遣することで推進するべきと考えます。人材をどこで獲得し、各社での取り組みを検討する際のポイントではないでしょうか。
鈴木: DXを推進するには、事業とデジタルの両輪を理解しながら、目的意識をもって進めることができるケイパビリティを持ち、なおかつ、事業とコーポレートの両サイドと円滑かつ密にコミュニケーションが取れる人材であるという事が重要であるということですね。
鈴木: DXの目的が不明確というお話がありましたが、目的設定のアプローチについて、どのようにお考えでしょうか。
丹羽: そもそもDXの取り組みが推進できていない状況である場合、DXの推進を全社的なメッセージとして社内に届けるトップダウン型のアプローチが必要である一方、事業部側からボトムアップ型で、すなわち推進できる領域から進めるというアプローチも必要です。例えば、物流事業などはBtoCに近く、顧客課題も見えやすいため、ボトムアップでの目的を設定しやすいといった事情があります。
丹羽: いずれの場合でも、先ほど述べた目的設定に対しては課題解決アプローチであるべきです。経営課題を解決する手段としてなのか、顧客課題を解決するための手段なのか、達成したい目的と、その背景情報としての課題を明確にしたうえで、その解決策としてDXを検討しなければいけません。
相磯: また検討すべき事柄によって巻き込むべき対象が変わってきます。例えば、コーポレート側では経営陣に対していかに情報を迅速に提示するかといった検討を進めている一方で、事業部側ではどのように売上を向上させるべきか、マネタイズをどうするべきかを検討しています。こうした状況下においては、誰を巻き込み、どういった目的のために、どのようなDXを検討すべきなのかを考える必要があります。
丹羽: また、これはトップダウンでもボトムアップでも同じなのですが、製造業においてはプランニングの段階でかなり具体的な実現性を問うケースも多いため、DX推進というテーマにおいても実現性が懸念点となることがあります。
鈴木: 世の中に浸透しつつあるものの、まだまだDXという領域が一定新しい領域として捉えられるような企業においては、今までやってきた事業と比べて、プランニング段階でその実現性を図ることにまだ不慣れな状況があるということですね。