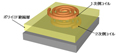実験に用いたテスターのストーリー
図3-2-1は図1-5-1の再掲ですが、筆者がこの業界に入るきっかけとも言えるような(当時の子供レベルで考えれば)超高性能測定器です。筆者は子供のときに、このテスターを中古で、すでに他界した父からもらいました。
アナログ式メータであることから、相当の年季モノ(ビンテージ品)だと言えるでしょう。35年以上は使っていますので、製造されてから40年近く経過するものと思います。これがプロとなった今でも自宅の実験ベンチで、現役で活躍しています。ちょっとしたモノや事柄が、人生を大きく左右するというのは、このことかもしれません。
さきに説明したように、測定器はこのテスターだけを用いて進めていきます(なお波形観測のデモンストレーションのためにオシロスコープを用いる)。
回路を設計し、デバイスを選定する
それでは実際に回路設計にかかってみましょう。まずここでいくつかのポイントがあります。
(1) 使用する周波数帯域を考える
ハイスペックなオーディオ(HiFi)システムでは、周波数特性として少なくとも数10kHz程度まで増幅する必要はありますが、ここでは「必要十分なレベル」と考え、10kHz程度を目標としてみます。次の(2)で選択するOPアンプもこの10kHzを視野にいれて選んであります(理由は少し難しくなるので、興味のある方はOPアンプの専門書をお読みいただきたい)。
ところで音質と周波数特性は深く関係しており、周波数特性が広く良好なほうが、高い周波数まで安定に増幅できること、信号の遅れ(位相遅れという)が広い周波数範囲にわたって少なくなり、高品質な音質が実現できることになります。
(2) 電源の電圧
電源はさきに説明したように、単3電池を2本使うことを基本として考えます。OPアンプには±の2種類の電源がありますので(単一のプラス電源でも動かすことができるが、少し回路構成が面倒になるのでこのような回路構成とした)、電池をプラス側に1本、マイナス側に1本使うことにします。そうすると±1.5Vで動くOPアンプが望ましいと言えますが、電池が減ってきても使うことができるように、もう少し低い電圧(±1.2V)で動くOPアンプを選択しておくことにします。
図3-3-1はアナログ・デバイセズのWebサイトでパラメトリック検索と呼ばれる機能により、この目的に適合するOPアンプを選択している状態です。ここで「AD8607」は±0.9V(単一のプラス電源だと1.8V)という低い電源電圧でも動作できますから、これを選択してみましょう。
(3) 入力の信号レベルを考える
OPアンプは電源電圧範囲内の入力電圧レベルを受けられ、同じくその範囲の出力電圧レベルを出せる能力が必要です(図3-3-2)。AD8607もその機能を持っています。
これは「当たり前ではないか?」と思われるような話ですが、この機能を持ってないOPアンプも多数あります。IC設計上の理由などがあるためで、それでも適切な使い方をすればまったく問題はありません。
「信号が電源電圧まで振幅しても動作可能」なOPアンプを「レールtoレールOPアンプ」と言います。まず入出力信号を詳しく考える前に、この機能を持ち合わせていることを最初に確保しておきましょう。これも考えてAD8607を(実は)選択しています。
さて、マイクから入ってくる信号の大きさは、通常数mVというところです。この信号は大きさが小さいので、テスターで測定することはできません(筆者も実は中学生のときにやったのだが、テスターの針はぴくりとも動かなかった)。この小さいレベルを増幅して、ヘッドフォンで聞こえるレベルの大きさまでもっていきます。
(4) 出力の信号レベルを考える
出力をヘッドフォンで聞こえるようにするには、だいたいアンプの出力を振幅1Vくらいまで増幅させる(大きくする)必要があります。この場合は出力が±1V程度まで変化するわけですから、先の(3)で示したようにOPアンプが「レールtoレール」である必要があります。
(5) 直流のブロック
このようなアンプ回路では、入力する、出力する信号は、それぞれ直流電圧がそのまま伝わっていくような回路にすることはあまり良いことではありません(一般論ではある。直結する場合もある)。
そこで連載第5回で説明したようなコンデンサを用いて、図3-3-3のように直流電圧が直接伝わることを阻止(ブロック)するような回路構成にします。
ところが実際の回路では、直流だけを通さないモノというのは実現ができず、「直流から、ある低い周波数の間を阻止する回路」というところで我慢(妥協)しなければならないことが現実です。
このことは少し難しくなるので、本連載では深く説明しません。「カットオフ周波数」という用語でネットでサーチしてみるといろいろ出てくるので、参考にされると良いと思います。
回路構成は非反転回路にする
ここでは連載第9回で示したような、「非反転回路」で回路図を書いてみましょう。これはレールtoレールのOPアンプだから安易に設計できるというポイントが(実は)あります。
この回路は非反転回路そのまま、また上記の(5)で説明した直流ブロックが入力側に入っています。抵抗R3が入っていますが、これはOPアンプ回路が安定に動作するように(少し難しいが動作点を決めることと、バイアス電流を流すため)必要なものです。
さらに連載第7回に示したように、「よりクリーンな」電源供給ができるように、OPアンプの電源端子にはコンデンサを接続します。コンデンサを接続する理由は、連載第5回に示したように「コンデンサは周波数に比例して電流を通すようになる」ため、電池単独で対応が出来ない高い周波数でも、クリーンな電源供給が可能になります。
なおこのコンデンサには極性がありますから、製作時には接続する向きに注意してください。
著者:石井聡
アナログ・デバイセズ
セントラル・アプリケーションズ
アプリケーション・エンジニア
工学博士 技術士(電気電子部門)