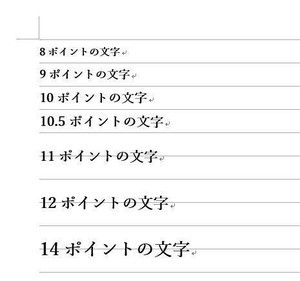今回は、段落に背景色を指定できる「網かけ」の使い方を紹介していこう。また、前回疑問を投げかけていた、「左の罫線」だけを描画した場合の対処方法についても紹介する。どちらも最適な配置にするには、ちょっとした裏技のようなテクニックが求められる。この機会に覚えておくとよいだろう。
左罫線だけを描画したときの挙動
まずは、前回疑問を投じていた「左の罫線」だけを描画した場合の対処方法について紹介していこう。以下の図は、段落に「左の罫線」を描画して見出しのデザインを作成した例だ。
この結果は以下の図のようになる。現時点では2行分の行間が確保されているので、少し長めの罫線が描画されている。この配置を調整していこう。
最初に「行間」を調整する。たとえば、行間を「固定値、20pt」に変更すると、それに応じて「左の罫線」の長さが以下の図のように変化する。
この結果を見ると、文字の(下の間隔)が(上の間隔)より狭いことを確認できる。そこで(下の間隔)を調整することにした。もういちど罫線の設定画面を開き、「オプション」ボタンをクリックして、下の間隔を「3pt」に変更する。
結果は以下の図のとおり。もともと「1pt」だった(下の間隔)を「3pt」に変更したのに、何も変化していないように見受けられる。
このような結果になってしまうのは、「下の罫線」を描画していないことが原因だ。というのも「オプション」ボタンで指定できる間隔は、《その方向の罫線を描画しているときのみ有効》という仕様になっているからだ。今回の例では「下の罫線」を描画していないため、(下の間隔)の数値は無視されてしまう。その結果、「何も変化しない……」という結果になってしまう。
その一方で、不可解な現象も発生する。たとえば、見出しと本文の間隔を広げるために「段落後」の書式を指定すると、それに応じて「左の罫線」が長くなってしまう。以下の図は、段落後に「1行」を指定した例だ。少し極端な例ではあるが、段落後の値に応じて「左の罫線」の長さが変化していることを確認できるだろう。
「段落後」は(段落の下)の間隔を調整する書式であり、普通に考えると「段落罫線」は影響を受けないはずである。しかし、実際には上図に示したような不可解な現象が起きてしまう。
このように「左の罫線」だけを描画した状態で間隔を調整しようとすると、さまざまな問題が発生する。「右の罫線」だけを描画した場合も同様だ。そこで、この問題を解消するテクニックを紹介していこう。
左罫線だけを描画したときの間隔調整
前述したように「オプション」ボタンで指定できる間隔は、《その方向の罫線を描画しているときのみ有効》という仕様になっている。逆に考えると、上下の罫線を描画してあげれば、「オプション」ボタンで(上下の間隔)を変更することが可能になる訳だ。
そこで、上下の罫線も描画することにした。罫線の設定画面を開き、「自動(黒色)、0.25pt」の罫線を「上」と「下」に描画する。
すると、見出しのデザインは以下の図のように変化する。上下に罫線が追加されてしまうが、これで(下の間隔)を自由に変更できるようになるはずだ。
もういちど罫線の設定画面を開き、「オプション」ボタンをクリックして(下の間隔)を調整する。今回の例では、下の間隔に「3pt」を指定した。
今度は(下の間隔)が正しく機能してくれたようだ。これで文字を上下中央に配置することができた。
続いて、見出しと本文の間隔を調整していこう。「段落後」の書式を「0.5行」に変更する。こちらも問題なく機能しているようで、先ほど示した例のように「左の罫線」が長くなってしまう現象は見られない。
このように(下の間隔)や「段落後」の設定を正しく機能させるには、「下の罫線」の描画が必須となる。とはいえ、今回の例のように、上下の罫線は必要ないというケースもあるだろう。
この問題は、上下の罫線を「白色」に変更することで解決できる。もういちど罫線の設定画面を開き、同じ太さで「白色」の罫線を「上」と「下」に描画するように修正する。
すると、上下の罫線が見えなくなり、「左の罫線」だけを描画したデザインに仕上げることができる。最後に、罫線の位置を「文書の幅」に揃える処理を行っておこう。今回の例では、「左の罫線」の太さを6pt、(左の間隔)を4ptに指定しているので、その合計となる「10pt」を左インデントに指定すればよい。
これで「左の罫線」だけを描画したデザインの完成となる。見た目はシンプルなデザインなのに、これを実現するには少し裏技的なテクニックが求められてしまう。
もちろん、「こんなに苦労してまで……」という意見もあるだろう。しかし、見えない罫線を描画するテクニックはさまざまな場面に応用できる。続いては、今回の本題ともいえる「段落の背景色」について紹介していこう。
「網かけ」を使った背景色の指定方法
Wordは、段落の背景色を指定することも可能となっている。この場合も、段落全体を選択した状態で「罫線」コマンドから「線種とページ罫線と網かけの設定」を選択すればよい。
罫線の設定画面が表示されるので「網かけ」タブを選択する。ここで「背景の色」を指定すると、段落の背景を好きな色で塗りつぶすことができる。
このように、段落の背景色を指定する操作は特に難しいものではない。しかし、文字の周囲に間隔を設けようとすると、途端に難しい話になってしまう。文字の周囲の間隔は「オプション」ボタンで指定できるが、これを有効にするには「罫線」を描画しなければならない。
このような場合にも、先ほどと同じテクニックが活用できる。その手順を簡単に紹介しておこう。罫線の設定画面を開き、上下左右に0.25ptの細い罫線を描画する。続いて「オプション」ボタンをクリックし、上下左右の間隔を指定する。このとき「上」の間隔だけを少し小さい値にしておくと、上下左右の間隔を等しくすることができる。
結果は以下の図の通り。段落が罫線で囲まれ、文字と罫線の間に間隔が設けられるのを確認できるだろう。
この罫線が不要な場合は、「背景と同じ色」に変更して罫線を見えなくしてしまえばよい。
これで文字の周囲に間隔を設けた背景色を指定できるようになる。最後に、文書の幅に揃える処理を行っておこう。今回の例では、罫線の太さに0.25pt、左右の間隔に5ptを指定したので、その合計となる「5.25pt」を左右のインデントに指定すればよい。ちなみに、入力したインデント(5.25pt)は自動的にミリ単位に換算されるため、画面の表示は「1.9mm」という値になっている。
このように、段落に背景色を指定するときにも「見えない罫線」が役に立つ。むしろ、このテクニックを知らないと、周囲に余白(間隔)のない背景色しか指定できなくなってしまう。少し設定が面倒ではあるが、ぜひ覚えておくとよいだろう。
なお、脚注や注意書きのように小さな文字を「罫線で囲む」または「背景色を指定する」といった場合は、左右のインデントを大きめに指定してもよい。以下の図は、左のインデントを大きくした例だ。1行あたりの文字数が少なくなり、読みやすくい文章に仕上げることができる。
また、どうせ罫線を描画するのであれば、それをデザインの一部として活用する方法もある。以下の図は、線の種類に「太-細の二重線」を指定した例だ。
こちらは目につきやすいデザインになるため、脚注の記載には向いていないが、コラムの作成などに活用できるだろう。
ということで、これまで3回にわたって「段落罫線」と「網かけ」の使い方を紹介してきた。細かな間隔調整が面倒ではあるが、「線」と「塗り」はデザインの基本といえるので、よく使い方を研究しておくとよいだろう。「段落罫線」と「網かけ」を思い通りに使いこなせるようになれば、それだけデザインの幅も広がるはずだ。