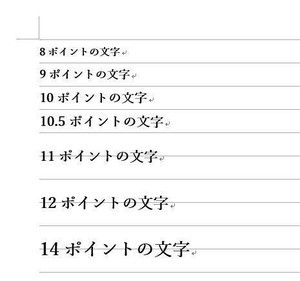本連載の第11回では「均等割り付け」を使って文字の開始位置を揃える方法を説明した。このほかにも文字の配置を整える機能がいくつか用意されている。
その代表的な存在となるのが「タブ」だ。とても便利な機能だが、仕組みをよく理解できておらず、使ったことがない人もいるようだ。今回は「タブ」の基本的な使い方と考え方を紹介していこう。
タブの入力と規定のタブ位置
タブは「Tab」キーを押して入力する制御記号の一種で、以降の文字を決められた位置に揃えて配置する役割を担っている。まずは、タブの入力方法から紹介していこう。
タブを挿入したい位置にカーソルを移動して「Tab」キーを押す。すると、その部分に間隔が設けられる。以下の図は「新宿本店」の文字の後にカーソルを移動して「Tab」キーを押した例だ。
入力された「タブ」を視認したいときは、「編集記号の表示/非表示」をクリックしてオンにすればよい。すると、タブが入力されている位置にグレーの「→」記号が表示される。これが「タブ記号」となる。
同様の手順で各店舗名の後に「タブ」を挿入していくと、それ以降の文字(電話番号)を揃えて配置できるようになる。
ただし、必ずしも開始位置が揃うとは限らない。上図を見ると、「渋谷店」の電話番号だけ開始位置がズレていることを確認できる。
この原因を探るために、ルーラー(定規)を表示した状態で解説を進めていこう。「表示」タブを選択し、「ルーラー」のチェックボックスをオンにする。
この画面をよく見ると、「渋谷店」の電話番号は4字の位置から、他の電話番号は8字の位置から開始されていることを確認できる。これは「既定のタブ位置」が4字間隔に初期設定されているためだ。つまり、タブ以降の文字を「4字、8字、12字、16字、……の位置から開始する」という設定になっている。
「渋谷店」は3文字しかないので、4字の位置から電話番号を開始しても十分な間隔を確保できる。しかし他の店舗は4文字以上あるため、4字の位置から電話番号を開始すると、間隔がなくなってしまう(または文字が重なってしまう)。よって、他の店舗は8字の位置から電話番号を開始する、という考え方になる。
では、すべての電話番号を揃えて配置するにはどうすればよいだろうか? 最も簡単なのは「渋谷店」の行にタブを追加入力してやる方法だ。すると、次のタブ位置となる8字の位置から電話番号が開始されるようになり、すべての電話番号を揃えて配置できるようになる。
このように、タブ以降の文字を「4字、8字、12字、16字、……の位置から開始する」というのが、Wordにおけるタブの初期設定となる。
規定のタブ位置の変更
これで電話番号の開始位置を揃えることができたが、「店舗名と電話番号の距離が離れすぎている……」と感じる人が多そうだ。この問題を解決する手法のひとつが「既定のタブ位置」の変更。「渋谷店」のタブをひとつに戻した状態で解説を進めていこう。
「ホーム」タブの「段落」グループの右下にある「小さい四角形」をクリックする。なお、「既定のタブ位置」は文書全体に関わる設定となるため、あらかじめ段落を選択しておく必要はない。
「段落」ダイアログが表示されるので、「タブ設定」ボタンをクリックする。
以下の図のような設定画面が表示される。最初は「既定値」の値が4字に初期設定されているはずだ。よって、タブ位置は4字間隔で設定されることになる。「既定のタブ位置」をカスタマイズするときは、この数値を変更してやればよい。ここでは試しに「6字」に変更した例を紹介しておこう。
「OK」ボタンをクリックすると「既定のタブ位置」が6字間隔に変更される。つまり、タブ以降の文字を「6字、12字、18字、24字、……の位置から開始する」という設定になる。今回の例の場合、すべての電話番号が6字の位置から開始されるようになる。
画面が見やすくなるように、「編集記号の表示/非表示」をオフにした例も紹介しておこう。店舗名の文字数に関係なく、電話番号を揃えて配置できているのがわかる。
このように、タブを使って文字の配置を整えることも可能である。今回の例の場合、最も長い店舗名は「千駄ヶ谷店」の5文字となる。ここに1文字分の余白を加えて「6字」の位置から以降の文字(電話番号)を配置することで、各文字が整列して配置されるように工夫している。
なお、「既定のタブ位置」をカスタマイズするときは、その設定変更が文書全体に影響を及ぼすことに注意しておく必要がある。「既定のタブ位置」は段落の書式ではなく、文書全体を対象にした書式となる。よって、文書内の他の箇所でもタブを使用している場合は、それらのタブ位置も一緒に変更されることになる。この点を勘違いしないように注意したい。
タブ位置を自由に指定する
続いては、先ほどの例に「各店舗の担当者」を追加した例を考えていこう(以下の図を参照)。現時点では「規定のタブ位置」を6字間隔にカスタマイズしているため、担当者名は6字の位置、電話番号は12字の位置から文字が開始されている。
それぞれの文字は整列して配置されているが、「担当者と電話番号の間隔が広すぎる……」と感じる人も多いだろう。このような場合は、「規定のタブ位置」ではなく、「自分で指定したタブ位置」で文字を配置してやるとよい。
こちらは、それぞれの段落に対して指定する書式となる。よって、あらかじめ対象とする段落を選択した状態で「段落」ダイアログを呼び出す必要がある。
「段落」ダイアログが表示されるので、「タブ設定」ボタンをクリックする。
先ほど同様に、タブの設定画面が表示される。タブ位置を個別に指定するときは、「タブ位置」の項目に数値を入力する。なお、この数値の単位は「X字」が基本となっている。たとえば「6.5」と入力した場合は、6.5字の位置にタブ位置が設定されることになる。数値を入力できたら「設定」ボタンをクリックする。
これで1番目のタブ位置を指定できた。続いては、2番目のタブ位置を指定していこう。今度は「11」と入力して「設定」ボタンをクリックする。
これで2番目のタブ位置を指定できた。すぐ下にあるテキストエリアを見ると、「6.5字」と「11字」という値が表示されているのを確認できる。これを確認してから「OK」ボタンをクリックする。
以上で、タブ位置の指定は完了。タブ以降の文字が、それぞれ6.5字、11字の位置から開始されているのを確認できる。
このようにタブ位置を個別に指定していくと、それぞれの文字を好きな位置から開始することが可能となる。ただし、1回の操作で適切なタブ位置を指定できるケースは稀だ。先ほど紹介した例を見たときに、「6.5字や11字という値はどこから来たのか?」と疑問を感じた人も多いのではないだろうか。
これらの数値は、文字数の計算により求めたものとなる。今回の例の場合、店舗名の最大文字数は5文字で、その後に1.5文字分の間隔を設けるとすると、1番目のタブ位置は5+1.5=6.5字という計算になる。
一方、担当者名の最大文字数は3文字で、6.5字の位置から開始されている。よって、6.5+3=9.5字の位置が担当者名の右端になる。その後に1.5文字分の間隔を追加すると、2番目のタブ位置は9.5+1.5=11字になる。
このような計算により導き出した数値が6.5字と11字になる。とはいえ、いちいち計算するのではなく、「もっと感覚的に操作したい」という声も多く聞かれそうだ。もちろん、そういった指定方法も用意されている。これについては次回の記事で詳しく紹介する予定だ。
行の先頭にタブを入力するには?
最後に、タブを入力するときの注意点を補足しておこう。以下の図のように、行(段落)の先頭にタブを入力したいケースもあると考えられるが、この場合、「入力したタブ」が勝手に「字下げ」に変更されてしまう。画面をよく見ると、最後の行だけ「→」の記号が表示されていないことを確認できるはずだ。
これはオートコレクトが機能した結果であり、Wordが気を利かせて「こちらで自動的に変更しておきましたよ」という挙動になる。とはいえ、「タブ」を入力したかったのに勝手に「字下げ」に変更されてしまうのは、かえって迷惑な話といえる。
正しくタブを入力するには、以下の図に示したアイコンをクリックし、「タブに戻す」を選択しなければならない。
すると、勝手に指定された「字下げ」を「タブ」に戻すことができる。今度は「→」の記号が画面に表示されているのを確認できるだろう。
このように、オートコレクトが「余計なお世話」をしてくれるケースもある。中には、このオートコレクトが「邪魔でしょうがない」と感じる人もいるはずだ。そこで、このオートコレクトを無効化する手順を紹介しておこう。
- (1)「ファイル」タブから「オプション」を選択
- (2)Wordの設定画面が表示されるので、左側のメニューで「文章校正」を選択
- (3)「オートコレクトのオプション」ボタンをクリック
- (4)オートコレクトの設定画面が表示されるので、「入力オートフォーマット」タブを選択
- (5)「Tab/Space/BackSpaceキーでインデントとタブの設定を変更する」をオフに変更
- (6)「OK」ボタンをクリック
これで行頭に挿入した「タブ」を「字下げ」に自動変更するオートコレクトを無効化できる。
ただし、行頭に挿入した「スペース」を「字下げ」に自動変更する処理、「BackSpace」キーで「インデント」や「字下げ」を解除する自動処理、なども無効化されること注意しなければならない。さまざまな操作に影響を及ぼす設定項目なので、安直に無効化するのではなく、まずはWordの仕組みを十分に学び、「それでも、やっぱり邪魔だ」と感じたときに無効化するとよい。