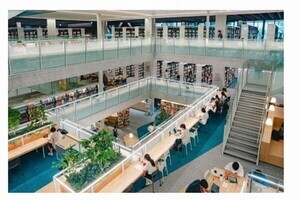STEM(Science:科学、Technology:技術、Engineering:工学、Mathematics:数学)分野、いわゆる理工系分野における女性の活躍を推進するため、東京都と山田進太郎D&I財団が連携して、「Girls Meet STEM in TOKYO」を開催している。
その取り組みの一環として、富士通が女子中高生向けのオフィスツアーを実施。同社が手掛ける技術とその歴史をツアー形式で紹介するとともに、富士通で働く現役女性社員との交流会を開催し、「学生時代はどんな勉強をしていた?」「理系を選んだきっかけは?」などリアルな会話が繰り広げられていた。
筆者もツアーと交流会に密着したので、本稿では参加者の感想も交えながらその様子をレポートする。
STEM分野における女性活躍はOECD最下位
東京都は2022年度より、女子中高生を対象としたSTEM分野の企業や大学研究室などでオフィスツアーを開始している。以降、2024年までの3年間で18社でツアーを開催しているが、計844人の定員に対し約1万人の応募があるなど、反響の大きさから需要の高さがうかがえる。
過去のツアー後に実施したアンケート調査では、97%の生徒が「STEM分野への関心が高い状況が続いている」と回答し、80%以上の生徒が「意識や行動に変化があった」と回答した。
具体的には、「迷っていたが理系に決めた」や「デジタル関係を考え始めた」などの声も寄せられいるという。オフィスツアーへの参加をきっかけに女子中高生の進路や職業の選択肢が広がっていると考えられる。
都のこうした活動の背景には、STEM分野に携わる女性の少なさがある。日本は世界的にもその数が圧倒的に少ないと言われており、STEM分野の大学卒業生における女性の比率は17.5%と、OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構)に加盟する38カ国の中で最下位。なお、OECD加盟国の平均は32.5%(OCED,Education at a Glance 2023)。
STEM分野で活躍する女性をさらに増やすためには、文理選択の前にSTEM分野の仕事や学びに触れる機会を提供し、キャリアへの興味を高めることが重要だ。
東京都は今年度から、女子中高生のSTEM進路選択を支援する山田進太郎D&I財団と連携し、「Girls Meet STEM in TOKYO」として参画企業を50社以上に拡充。富士通の他にも、セガやサイバーエージェント、サッポロビール、アマゾン ウェブサービス ジャパンなどがオフィスツアーを受け入れた。
富士通の歴史と最新技術をツアーで体験
富士通のオフィスツアーは、JR南武線 武蔵中原駅が最寄りの本店・Fujitsu Technology Park(神奈川県 川崎市)で開催。都内に在住・在学の女子中高生約30人が参加した。
参加者はまず第一部で、富士通が掲げるパーパス(存在意義)や、設立90周年を迎える同社に受け継がれるテクノロジーのDNAや行動指針などを学んだ。さらには、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI活用支援といったITサービスの領域で特に業績が拡大していることなども学んでいた。
続いて、同社が手掛ける技術の歴史と現在地を展示するFujitsu Technology Hallを見学。1935年の設立からの歴史をたどるHistory zoneでは、1945年(昭和20年)に逓信院の標準規格認定を受けた「富士形3号電話機」が紹介されると、多くの参加者が初めて見るダイヤル式の電話機に驚いていた。
次に紹介されたのは、1957年(昭和32年)に完成した「FACOM 138A」。FACOM128Aの小型・廉価版に相当し、大きさを3分の1ほどに圧縮している。なんとこの機体、現在も稼働する。マチンの公式にグレゴリ級数を代入して、円周率の近似を求める様子が体験可能だ。
テープを設置して参加者が運転ボタンを押すとリレー(継電器)がパチパチと動作し、タイプライターのように計算結果が紙に印字された。スマートフォンでその様子を撮影する参加者も多かった。
その後は最新技術として、スーパーコンピュータ(スパコン)「FUJITSU Supercomputer PRIMEHPC FX1000」や量子コンピュータを見学。超伝導方式の量子コンピュータはマイナス273.13度という極低温下で稼働すると説明を受けた参加者が、その温度など詳しい情報をメモに残していたのが印象的だった。
また、富士通が手掛けるAI技術として、行動分析技術「Actlyzer」や体操競技の動作をセンシングしてAIが分析する「Judging Support System」、JR上野駅で実証実験が行われた音の視覚化装置「エキマトペ」なども見学した。
Actlyzerのブースでは、まずAIの発展を支える重要な技術であるディープラーニングの概要から学習。「ディープラーニングという言葉は聞いたことがあるけど、うまく説明できない」という参加者のモヤモヤが解消されたようだ。
Actlyzerは「腕を組む」「バンザイ」「歩きスマホ」など、13の行動を検知可能だ。参加者はカメラの前で実際に動きながら、AIによって検知されるのかを確認していた。
富士通で働く現役女性社員のリアルな意見は?
第二部では、富士通で実際に働く女性社員との交流会が開かれた。冒頭ではCHRO室シニアマネージャーの美堂梓氏が「当社はワークライフシフトを推進しており、自宅からリモートで働いている社員や、子どもの世話などで一度業務を離れてから再開するような働き方をしている社員もいる。自分らしい自律的なキャリア形成ができる組織を目指している」と挨拶を述べた。
次に、○×形式でのパネルトークが行われた。ここでは、富士通社員の学生時代の過ごし方や文理選択などが語られた。
「学生時代、数学や理科は苦手だった」に対し、〇と回答した水間氏は、「高校から大学まで文系だった。通知表で2が付くほど数学や理科が苦手だった。今はSEでプログラミングコードを記述する仕事をしているが、まさか自分がこの仕事をするとは思っていなかった」と振り返った。
「理系に進む予定はなかった」という質問に〇と回答した山並氏は、「大学も文系科目なので理系に進むつもりはなかった。のちに経済学の勉強をすることになり、そこで数学を多く使うことになった結果、今はその知識を活用して研究職に就いている」と話していた。
反対に、×と回答した中附氏は「私は最初から理系に進む予定しかなかった。数学に自信はなかったが、生き物が好きなので生き物に関する勉強がしたかった」と話していた。
第二部の後半は、4~5人ほどのグループに分かれて、富士通社員と交流の場が設けられた。「中学・高校時代○○してました」「好きなことの見つけ方」「理系女子あるある」などのトークテーマが事前に提示されたものの、「なぜ富士通に入社したのか」「入社前と入社後のギャップ」「普段の1日の生活の様子は」など、よりリアルな意見を求めている参加者も多かった。
イベント終了後に参加者に話を聞くと、「富士通はPCを作っているイメージだったが、それ以上に、スパコンやAI技術で生活にどう貢献できるのかを考えている企業なのだと知りイメージが変わった」「90年の歴史のある企業だが、人間とAIが共存する社会を目指す姿勢に驚いた」などの感想が聞かれた。
また、「探求は趣味から始まるという話を聞いて、身の回りの興味のあることを将来の仕事につなげたいと思った」「富士通は技術系だけでなく社会福祉分野の研究もしていると知れたので、文系理系に関係なく将来の選択肢として興味を持てた」など、今後の進路に関する感想もあった。
女子中高生らとのグループトークに参加した富士通研究所の山並氏は「これから何でもできるし何にでもなれるので、数学や苦手な強化に縛られずに、好きなことややりたいことを大事にしてほしい。好きなことをもっと楽しむために、理数系の勉強や技術がつながっていることが少しでも伝わっていれば嬉しい。今回参加して、未来を考えることはわくわくする楽しいことであると、私自身が良い刺激をもらった」と話していた。