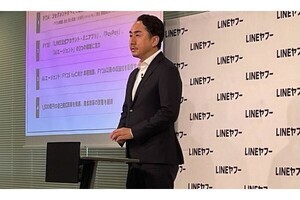LINEヤフーは6月30日と7月1日の2日間にわたり、エンジニア・デザイナー・プロダクトマネージャーのための技術カンファレンス「Tech-Verse 2025」を東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンスで開催した。
同イベントでは12カテゴリー131のセッションが開講され、同社の開発・研究の成果や知見、最先端技術などの詳細な情報を得られる絶好の機会として、オンラインおよびオフライン(招待制)で7,200名以上が参加した。本稿では、基調講演の模様をお届けする。
今年のテーマは「AI Strategy」と「Platform Integration」
「Tech-Verse」は、2024年に開催された「Tech Week」で好評だった講演会をピックアップした技術イベント。今年も開催される「Tech Week」の冒頭の2日間として位置づけられ、残り3日間が「Hack Day」として開催された。
セキュリティ、サーバサイド、プライベートクラウド、データプラットフォーム、インストラクチャー、フロントエンド、アプリ、デザイン、プロダクトマネジメント、エンジニアマネジメントなどをテーマに12領域131のセッションで技術者による講演が行われた。
今回のテーマは「AI Strategy」と「Platform Integration」。2つのテーマに関連した多くのセッションが開催された。開会式として、LINEヤフー 上級執行役員 CTO(Chief Technology Officer)の朴イビン氏とLINEヤフー 執行役員 サービスインフラグループ長 冨川修広氏による基調講演が行われた。
AIカンパニーとしてAIエージェントサービスを拡大
LINEヤフーは2025年5月に決算発表会でAIカンパニーを目指すと宣言しており、その具体策として、サービスのAIエージェント化、AIによる生産性の大幅な向上を打ち出している。朴氏は壇上で、生成AIをサービスに適用する事例が44件、AIによる生産性の向上の事例が35件進められていることを発表、一部事例の紹介を行った。
Yahoo! JAPANのAPP「AIアシスタント」については、サジェスト形式で情報の深掘りが可能な機能や抽象的な質問を投げても、すぐに知りたいことにたどりつける機能を紹介した。
LINEにおいては「LINE AI」「LINE AI Talk Suggestion」「LINE AI Friends」の3つのAIエージェントを発表。「LINE AI」はPDFファイル他内容の翻訳や要約などの機能、「LINE AI Talk Suggestion」では会話で入力する内容をAIが提案する機能を提供している。これらの機能は公開済みの機能となる。
「LINE AI Friends」はAIキャラクターと会話が可能な開発中の機能で、現在一部ユーザーに先行リリースされている。近日中に一般公開される予定だ。
Yahoo! JAPAN ショッピングでもβ版として「Special Offers」「Product Comparison」「Specifications」「Review」などのユーザーの商品購入をサポートする多くの機能を提供している。提供されるAIサービスは独自の統一したロゴを活用しているので一目でわかる仕様となっている。
また、業務の生産性向上にもAIを積極的に活用。カスタマーサービスでAIを利用してメールでのユーザーの問い合わせに対応している。月8000件のメールの問い合わせに対し、初期対応による解決率が92.1%という成果が出ている。
「Ark Developer」で開発の生産性を向上
そして、注目すべきは生成AIを利用した開発環境を進化させる「Ark Developer」だ。これは開発エンジニアを対象に、ソフトウェアのUIデザイン、コーディング、ソフトウェアテストの3つ機能で知的サポートを提供するもの。
その名称は、急激変化する今の時代を共に生き延びるための方舟になることを願ってつけられた。プロジェクトイエローという名称で開発が進められ、現在エンジニアに対して導入が開始され7月から本格運用が開始されるという。
「Ark Developer」は、LINEヤフーの開発プロセスに合わせて6つのツールで構成されている。そのラインアップは以下の通りだ。
- Ul to Code:デザイン領域におけるLINEヤフーのコーディングスタイルに合わせてコードを出力する
- Code Assist:コーディングの段階でプログラミングをサポートする
- Code Review:AIがコードレビューを行う
- Docs:開発コードのレポートを作成する
- Auto Tes:テストデータを作成
- QA Support:テストの設計を支援する
各機能はチューニングを重ねることで高評価を獲得しており、「Ark Developer」導入により。2025年は開発の生産性が10%から15%アップしたという。
Yahoo!とLINEを統合する新プラットフォーム「CatalystOnePlatform」
LINEヤフーの新プラットフォーム「CatalystOnePlatform(カタリストワンプラットフォーム)」については、冨川氏が説明を行った。
「CatalystOnePlatform」は、Yahoo!とLINEの合併に伴い今まで分かれていたプラットフォームを統合し、日本、韓国、台湾、タイなどグローバルで活用する共通の単一サービス中核基盤として2030年完成を目標に開発が進められているプラットフォーム。
同プラットフォームは、2社の重複環境の改善、セキュリティの大幅な強化、AIなどのイノベーションを加速する開発基盤の3つを重視している。「Catalyst」という名称はサービス成長のための触媒、変化のきっかけ、原動力、促進剤といった意味を込めて付けられたという。
今回、「CatalystOnePlatform」におけるプライベートクラウド「Flava」とデータプラットフォームについて多くの時間を割き説明が行われた。
プライベートクラウド「Flava」
「Flava」は、同社のプラットフォームの統合と機能と性能、セキュリティ、コストメリットの最大化を実現するため開発が進められているプライベートクラウド。データプラットフォームとしては、LINEとYahoo!という2つの大規模サービスを運営しつつ、最新のAIサービスの運用と開発を円滑に行うことを可能とする。
「Flava」は、2社のシステム統合において、AWSなどのパブリッククラウドではなく、プライベートクラウドを採用している。冨川氏によればコスト面において、各社パブリッククラウドサービスと比較して、平均で約4倍のコストメリットを実現しているという。
加えて、同社グループが提供するユーザー認証やデータストレージ、メッセージング、支払いシステムなど200万を超えるサービスを効率的に運営するため。LINEとYahoo!の高度なチューニング技術を結集して、仮想マシンのさらなる性能向上を計画、パブリッククラウドと比較して20%の性能向上を実現しているとのことだ。
セキュリティに関しても、サービス情報のセキュリティレベルに応じたセキュアな環境の構成・運用を可能とする基盤と、VPCの導入による各サービスに対する緻密なアクセス制御などにおいて向上が図られている。
「Flava」の開発は順調に進んでおり、同氏によれば「今年度中には現在想定しているすべての機能がリリースする予定になっている」とのことで、今後2026年から2030年に向けて既存環境からFlavaへの本格的なマイグレーションが開始されるという。
データプラットフォーム
データプラットフォームに関して、冨川氏は、「統合する前のLINEの機械学習、基盤技術、データガバナンスの構造化などの強み、Yahoo!サイドの広告、レコマンドに必要な大規模データの最適化と商用利用での強みなどを生かし構築が進められた」と説明した。
具体的には、コスト構造の見える化と最適化、セキュリティ強化、サービスをオーダーしたIDの変換とデータベース連携の仕組みなどが最適化され、データガバナンス面においても多くの進化を成し遂げたという。開発の一部は既に完了し、残りの部分も今年中に完了を目指すという。
機械学習プラットフォームについては、AutoML(自動機械学習) コンセプトを積極的に取り入れモデル開発の効率を大幅に高めるほか、Realtime ML piplines(リアルタイムで入力データから継続的機械学習、予測や意思決定を行う)などの採用により、現在の約6倍もの速度でのモデル開発を実現するべく開発が進められている。
また、データプロダクト領域は合併により進歩し両者のデータの組み合わせにより、より高精度なレコメンドやターゲティングが可能になったという。これらの効果を最大限に生かしAIによる更なるデータ解析と運用もあわせてサービスの質を向上させていくことが可能になるという。