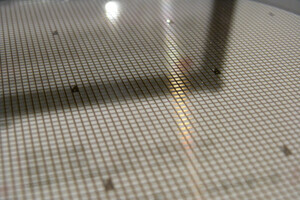今回の米騒動は、日本の農業の在り方を見つめ直す好機でもある。コメの小売価格がなぜ1年前に比べて倍になっているのかということで、消費者の不満・不平から『令和の米騒動』が出発。小泉進次郎農相が新手の〝随意契約によるコメ価格引き下げ〟という策に出て、安い米の登場を実現させている。ただ、中長期的に日本でのコメ生産をどうするかという問題が大きな課題として残る。コメ農家が生き残るにはコメ価格3千円台が必要だと言われる。食料自給率38%、先進国最低の水準をどう向上させるか─。
コメ問題の背景
─ 小泉進次郎大臣に代わり、備蓄米を小売りに届けることで米の価格を下げるということが行われていますね。
渡邊 備蓄米の放出については総理の方から「随意契約(随契)を活用した備蓄米売渡しの検討」という指示が小泉大臣に出て、入札から随契への切り替えを行いました。
客観的状況としては、今まで1回目から3回目までは入札による売り渡しをして、集荷業者の皆さんに入札で参加していただいています。そこに、今まで31万㌧を放出し、5月25日時点で、集荷業者はその全量を引き取っています。
しかしながら、その31万㌧の内、実際に小売に流れているのは4万㌧程度ということがわかりました。末端の消費者に届くまで時間がかかり十分に行き渡っていない状況でした。
そういう状況をふまえ、このまま入札形式を続けていても状況が変わることはないだろうと。集荷業者ではなく小売業者に対して、直接売り渡しをするということになりました。
─ 現在4㌔㌘あたり2千円台で販売するお米が市場に出ています。
渡邊 はい。第1回目から3回目までの備蓄米は1年前のお米でしたが、新たに小売業者さんにお渡しをするものは、4年産と3年産で、収穫されてから3年以上経っているお米です。
この2千円台の備蓄米がそれなりの量出ていけば、消費者の選択の幅が広がりますし、そういう価格に反応して銘柄米の価格も少し下がってくるのでは、というのを期待しています。
─ 一方で、石破茂総理大臣は3千円台が適正だというふうに言われています。その根拠は何ですか。
渡邊 石破総理がおっしゃられた3千円台というのは、備蓄米だけではなく、普通のお米も含めて3千円台ということだと思います。
価格の根拠は、某報道機関が生産者、集荷業者、卸、小売に取材をしていて、大体5㌔3千円~3千500円ぐらいであれば、それぞれの立場の人は納得がいくという報道を行ったと聞いています。
そういったことも踏まえ、3千円台が適正とおっしゃったのだと思います。
─ 今回小売りに直接売り渡したのはあくまで臨時的措置だと思いますが、今後コメの流通制度をどう捉えていくべきと考えますか。
渡邊 そもそもお米の流通は、農家さんから集荷業者がお米を集めて、集荷業者さんが卸に売り、卸の人たちが精米をして袋詰めをして、小売の方々に販売をし、小売の方々が消費者の方々に販売するというルートです。
それはわれわれが作った流通ルートと言うよりは民間業者の方々が作り上げたルートですが、5次問屋まであるとの話もあり、合理的な姿なのかは議論が必要です。
─ なぜ通常の流通ルートでスムーズに流れていかないのかという国民の声がありますが。
渡邊 1つは、卸業者さんは普通の銘柄米も扱っていますから、それにプラスオンで国からの備蓄米を流すことになって、時間がかかっているということではないかと思います。
もともと小売は自前で精米をできるところは少ないです。ですからいきなり政府が備蓄米(玄米)を持って来られても困るという意見が、ヒアリングで小売り側から上がってきていました。
しかし、実際に小売に玄米で届けると、小売から卸業者に「これだけ精米を引き受けてくれないか」という話を持っていくという、今までに無い商取引が行われています。
─ 随契による備蓄米は小売りにまず行ってから、精米を求めて卸業者に持っていき、それがまた小売りに戻ると。
渡邊 そういうことです。今回の随契による備蓄米については、新たに国の備蓄倉庫から精米工場までの運搬費については政府で負担をすることにしました。
農家の収入をどう守るか
─ 消費者にとっては米の価格は安い方が有難いですが、生産者の持続可能な経営という面でコメの適正価格をどうもっていけばいいでしょうか。
渡邊 今売られている6年産のお米は去年の秋に収穫をされ、その時点で集荷業者の人たちが値段を決めて買っていますから、既に生産者にはその時の値段で支払われています。
その時点では小売の米の売価は5㌔当たり4千円台にまだなっていませんから、その後小売りでコメが4千500円台と高騰していてもその分農家の方々の収入が増えている訳ではありません。
次のお米の7年産はまだ田植えが終わったばかりですけども、今年の秋以降に収穫がなされます。その時に、いくらで集荷業者が買うのかが問題になるだろうと思っています。
─ 流通段階でなぜ価格が上がったのでしょうか。
渡邊 もともと令和5年・6年産の時に、一時的に小売で売る価格が非常に上がって、それを反映して集荷業者の価格も上昇しています。
それまで資材費や人件費が上がっているのにもかかわらず、お米の価格は上がらなかった。そのことにより長年農家が赤字経営であると言われていた問題が、別の要因で米価が上がり、農家の赤字を賄える水準になったのではと言われています。
今後7年産については、そういう資材費の高騰や人件費の高騰など、コストが上昇した部分は考慮された価格で、かつそれなりの利益が出るような価格で農家から買い取るということになれば、お米の価格は正常に戻ってくると思います。
今回の価格が高騰したのは、端境期の7月から8月にかけてお米が去年のように不足し棚になくなるのではないかと業界の人たちみんなが恐れ、それが消費者にも影響して、その不足感の印象をみな持っておられるので価格が高止まりしています。
農家の経営を立て直すには?
─ 減反政策は2018年に廃止されていますが、大豆などの転作で補助金が出る仕組みなどがあって実質的に続いていると指摘する人もいます。今後このことについて再検討することはあるのですか。
渡邊 これは、今年の4月に閣議決定した食料・農業・農村基本計画で、具体的に、何をどのくらい作るのかを目標値として掲げています。
その中に、「水田政策の見直しの方向」を入れていまして、実質減反補助金じゃないかと言われている「水田活用の直接支払交付金」という補助金について令和9年度から根本的な見直しをするということになっています。
要は水田に着目した支援から、生産性向上を後押しする支援に切り替えます。そういう意味では、水田政策のあり方を見直す方向で既に打ち出しています。具体的な議論はこれから詰めていきますが、9年産から新しい支援方法になる予定です。
─ 農家や生産法人などの生産者がコメ作りを継続していけるかどうかということも議論していくと。
渡邊 はい。それから、今国会で食料システム法案が成立・公布されました。この法案というのは、農家のコスト割れが起こるような値決めは止めましょうという仕組みづくりです。
米も含め、生産者からすれば生産コストが上昇していますが、卸業者ないしは加工業者と販売交渉をやる際に今までの価格水準では自分の経営を維持していくのは困難な状況だと。
ですから、生産者から値上げをしてほしいというお願いをしても一切交渉に応じないだとか、そういう交渉に誠実に対応してくれない場合、国がそこに指導・監督に入れるという新たな仕組みを、今国会で議論していただきました。
その法律ができれば、生産者の方々のコスト割れが起こらないような価格形成を促していけると思います。
同時に、生産者には実際にどのくらいコストがかかっているのか指標をしっかり示していただく必要もあります。このような仕組みを具体的にどう作っていくのかが、今後の課題です。
米消費量が減少を辿る中で
─ トランプ関税策の交渉が続き、お米が交渉カードになるという話も出ましたが、これについてはどう考えますか。
渡邊 日米交渉でアメリカ産米の輸入を増やしたらいいというご意見もありますが、日本で米は100%自給ができていますので輸入の必要があるかは慎重に考えるべきだと思います。
─ 米の消費量は年々下がっています。自給バランスでは、大体消費は700万㌧とみていいですか。
渡邊 はい。消費量は毎年10万㌧ずつ減少しています。お米を食べずに他の肉や牛乳の消費増など、食生活の中身が変わっています。
それから2050年までに2千万人減るという人口減の問題もあります。
そうすると今1人当たりお米を約50㌔食べていますが、25年後は人の数が2千万人も減るので、米の消費量も100万㌧程度減少します。ですから国内の需要だけを見ていたら、どんどんお米を作る量を減らさなければならない。
そうなると生産基盤を維持することが難しくなりますから、海外の需要を取り込むことで増産も可能にしていくことが今後重要になってきます。
企業の農業参入は
─ 日本の食料自給率38%と先進国の中で最も低いですね。この自給率問題についてはどう考えていますか。
渡邊 食料自給率はできるだけ上げた方がいいと思いますが、まず前提として、世の中的には、お米を食べなくなって、小麦を食べるようになったから自給率が下がっているといわれていますが、実は自給率70%と高かった時代は昭和40年くらいで、人口は1億人いませんでした。
今は1億2千万人で2千万人増加しているのに、農地のうち水田の面積は340万㌶から230万㌶に減っています。人口増加の中で農地減少ですから、なかなか自給率は上がる方向にはありません。
しかも、今の食生活を維持するために必要な農作物を全部日本で作ろうとすると、3倍の農地の1332万㌶が必要です。逆にいうと、今の食生活を支えるだけの必要な農地は、3分の1しか日本国内にない状況です。
─ 土地がない中で100%を目指すのは非現実的だと。
渡邊 なかなか難しいと思います。
また、1人当たりのカロリー摂取量では、米を食べる量が減って小麦が増えたと思っている人が多いですが、実は違います。米が減った分増えているのは、畜産物と油です。
何か有事があった時に自給率が低くて困るのは、実は小麦だとか大豆、畜産物の餌といった外国から輸入しているもので、船が止まった途端にアウトです。ですからそれらを日本の国内でもっと作るよう努力しないといけないと思っています。
生産現場は、この自給率の話もあるけれども、人口減で生産者も減りますから、少ない人数で今の農地を維持しなければならないというのが一番重要な課題です。
そのためには、しっかりした農家を育てて、しかもスマート農業技術などで効率的に農業ができる仕組みをつくっていく必要があります。
─ その場合に、企業の農業参入はどう考えますか。
渡邊 もちろん企業も農業を支える大きな力だと思っています。実はもう既に多くの企業が農業に参入してきています。農地を借りて農業を行うリース法人は15年前くらいに全面自由化してから、10倍くらいに増えて4千法人ほどになっています。
有名な企業では、例えばイオン、楽天、大和証券も入っています。農地所有適格法人で農地を所有できる法人として参入しているのが、ローソン、モスバーガー、カゴメ、デンソーなど。
半導体を作っているデンソーはスマート農業にすごく関心があります。スマート農業に使われるテクノロジーでは様々な商機があると思います。
こういう大きな企業も入っていますから、非常に歓迎するべき話だと思います。実は全体で民間企業の法人数というのは今約4%しかありません。数は小さいですが、農地面積の約4分の1は法人が耕しています。
─ つまり大規模化しているわけですね。
渡邊 はい。販売額は約4割を占めます。これから個人農家がどんどん減っていくことが見込まれますので、非常に期待しています。
ただ、なかなか農業自体が儲からないので、参入する人が少ないということですね。モスバーガーやローソンなど、自分のところで農産物を商品として作っているような人たちが、生産にも関与したいということで参入する場合は多いです。
─ 企業側に期待することは何かありますか。
渡邊 これからは今までの伝統的な農業者だけではなく、技術もそうですし、担い手としてもいろいろな方々と連携をして、日本の農業を強くしていかなくてはなりません。
ぜひ企業の方々には日本の農業の現状をよくご理解いただいて、日本の国の食料確保を盤石なものにするお手伝いをしていただける企業が1つでも多く増えていってもらえればと思っています。