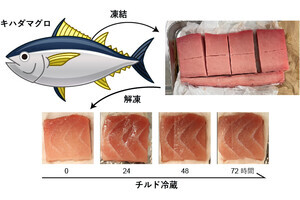東京大学(東大)は6月30日、日本人成人2757人から得られた延べ6万食以上の食事データを基に、食塩摂取量が多い食事の状況と食品の種類を明らかにしたと発表した。
同成果は、東大大学院 医学系研究科 社会予防疫学分野の篠崎奈々助教、同・村上健太郎教授、同・佐々木敏東京大学名誉教授らの研究チームによるもの。詳細は、食事と身体活動を扱う学術誌「International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity」に掲載された。
ナトリウムはヒトの生命維持に不可欠な必須ミネラルの1つであり、体内では血液などの体液中に塩化ナトリウム(食塩)、重炭酸ナトリウム、リン酸ナトリウムとして存在している。日本人の通常の食事ではナトリウムが不足することはなく、むしろ食塩摂取量は世界トップクラスとなってしまっている。
2024年に厚生労働省が発表した「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」によれば、1日平均の食塩摂取量は成人男性の平均が10.7g、成人女性の平均が9.1gとなっており、世界保健機関(WHO)が推奨している1日5g未満の約2倍に達する。食塩の過剰摂取は世界的な課題だが、中でも日本では多く、高血圧、ひいては心臓や脳の疾患につながるため、減塩が極めて重要視されている。
減塩を目的とした栄養教育やキャンペーンでは、食事の状況(いつ、どこで食べるか)や、食品の種類や量(何をどれくらい食べるか)に関するメッセージがよく用いられる。実際、これまでの研究から、外食や飲酒の頻度が高い人ほど食塩摂取量が多いことが示されている。
しかし異なる個人間の比較ではなく、同一人物の食事ごとに食塩摂取量の変化、つまり「どのような食事で食塩摂取量が増加するのか」は十分解明されていなかった。この疑問には、食事情報をリアルタイムに繰り返し収集する「生態学的瞬間評価」の手法が有効と考えられている。そこで研究チームは今回、生態学的瞬間評価を用い、各食事における食塩摂取量と関連する食事の状況や食品摂取の特徴を調査したという。
今回の研究には、18歳~79歳の日本人男女2757人が参加。各季節に2日ずつ、計8日間、すべての食事において、食事の種類(朝食・昼食・夕食)、勤務日か否か、食事場所、同席人数といった食事の状況と、食品の種類および量が記録された。
記録に基づき、減塩政策で摂取制限が推奨される汁物、漬物、加工肉・魚介類と、積極的に摂ることが推奨されている果物、減塩調味料、ハーブ・スパイス、酢・柑橘類果汁、野菜の摂取状況が調べられた。加えて、日本人の食塩摂取量と関連が深いとされる主食の種類(米飯、パン、めん、その他、主食なし)やアルコール飲料の有無も分析された。食塩摂取量への影響が小さい間食は除外し、延べ6万3239食が解析対象とされた。
その結果、1食当たりの食塩摂取量は、昼食や夕食、仕事や学校の休日、レストランなどでの外食、誰かと2人で摂る食事、そして秋や冬に多い傾向が確認された。一方、公園や車などでの食事、夏に少ない傾向が見られた。
食塩摂取量は、主食(特にめん類)や汁物、漬物、減塩調味料、ハーブ・スパイス、酢・かんきつ類果汁、中程度~高度に加工された肉や魚介類(ソーセージ、かまぼこなど)、アルコール飲料を含む食事で多かった。一方、果物を含む食事では少ない傾向が見られた。また、塩を使った調味料や野菜の使用量が多いほど、食塩摂取量も多い傾向が見られた。
-

食品の種類の各カテゴリーのける、基準と比較した1食あたりの食塩摂取量(g)の差。塩を使った調味料と野菜については、それぞれ摂取量が中央値にあたる12.5g(塩を使った調味料)および80g(野菜)増えた場合の、1食あたりの食塩摂取量(g)の変化が示されている。その他の食品は、非摂食の場合と比較した食塩摂取量の差が示されている(出所:東大プレスリリースPDF)
今回の研究は、食事の状況や食品の種類と食塩摂取量の関連が、生態学的瞬間評価を用いて明らかにされた初の研究だ。この成果は、日本人の食塩摂取量を減らすための、具体的かつ実践的な対策の検討に役立つことが期待されるとしている。