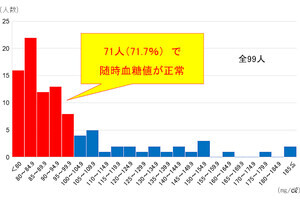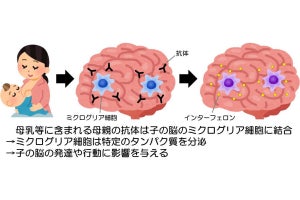大阪大学(阪大)は6月5日、マウスによる動物実験により、ほ乳類の性決定において、鉄代謝がエピゲノム制御を介して中心的な役割を果たすことを解明したと発表した。
同成果は、阪大大学院 生命機能研究科の岡下修己助教、同・立花誠教授らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。
ほ乳類の性決定では、発生初期における生殖腺の精巣・卵巣への分化が重要であり、その開始にはY染色体上の精巣決定遺伝子「Sry」の一過的な活性化が不可欠だ。Sryの発現は、発生時期・発現細胞・発現量のすべてが厳密に制御され、わずかなずれでも性分化に影響を及ぼす。この発現は、クロマチン状態に依存するエピゲノム制御によって調節され、特に「H3K9me2」の脱メチル化が転写活性化の鍵を握る。研究チームは、ヒストン脱メチル化酵素「KDM3A」がこの脱メチル化反応を担い、Sryの発現を活性化することを過去に報告している。
KDM3Aなどの「JmjCドメイン」を持つヒストン脱メチル化酵素群の活性には、補因子として鉄イオン(Fe2+)が必須だ。しかし、発生期における鉄代謝が性決定やエピゲノム制御にどう関与するのかは不明な点が多い。そこで研究チームは今回、鉄代謝とKDM3A依存的なSry活性化の関係に着目し、マウスを用いて因果関係を多角的に検証したという。
その結果、まず、マウスの性決定期(E(胎生)10.5~E12.5)における胎仔の生殖腺では、鉄の取り込み因子とFe2+産生因子の発現が、Sryを発現する雄性支持細胞(プレセルトリ細胞)で特異的に高いことが判明したとのこと。また同細胞では、Fe2+の蓄積レベルも高かった。これらの結果から研究チームは、KDM3Aが雄化の性決定で機能するには、十分な鉄の供給が不可欠という仮説を立てたとする。
次にこれを検証するため、Fe2+の細胞内への取り込みを担うトランスフェリン受容体を、生殖腺から特異的に欠損させたマウスが作成された。このマウス胎仔の性決定期の生殖腺では、細胞内のFe2+と総鉄量の著しい低下、H3K9me2の増加、Sryの発現低下が確認された。また、Sry遺伝子座でのヒストンH3K9me2脱メチル化が著しく阻害され、一部のXY個体では雄から雌への性転換が発生。以上の結果は、「TFR1」を介した鉄取り込みがKDM3AによるSry活性化に不可欠であることを実証するものだったとした。
次に、E10.8胚由来の生殖腺を「鉄キレート剤デフェロキサミン」(Dfo)存在下で体外培養し、Fe2+を急性除去した場合での性決定が検討された。Dfo処理下でも生殖腺の細胞数に大きな影響はなかったが、Fe2+と細胞内鉄貯蔵に関わる「フェリチン」の量は大きく低下し、Sry発現が著しく抑制されていた。その結果、XY生殖腺における精巣の体細胞マーカー「SOX9」の発現が失われ、卵巣の体細胞マーカー「FOXL2」陽性細胞が出現するなど、雄化の抑制と雌化の亢進が観察された。
そしてSryの強制発現で性転換を回避できたことから、鉄欠乏による性転換の原因はSry発現の抑制にあると判明。Dfo処理によりH3K9me2が顕著に蓄積し、Sryプロモーター領域での脱メチル化が阻害されることも示された。さらに、H3K9メチルトランスフェラーゼ「EHMT1/2Δ/+」の機能を遺伝学的・薬理学的に阻害すると、Dfo処理下でもSry発現の部分的な回復が確認された。これらの結果から、鉄欠乏による性決定破綻は、KDM3AとEHMT1/2Δ/+のH3K9me2修飾のバランスの破綻によるものだったのである。
続いて、妊娠マウスに「鉄キレート剤デフェラシロクス」(Dfx)を投与し、子宮内での急性鉄欠乏モデルが作成された。E6.5~E10.5にかけて母体にDfxを経口投与したところ、E11.5胎仔の生殖腺でSry発現が有意に低下していたとのこと。ここでも、XY胎仔でSOX9陽性細胞とFOXL2陽性細胞が混在した卵精巣化が起きており、一部の個体で性転換が起きていた。この結果は、母体の鉄状態が胎仔の性決定に直接影響を及ぼしうることを示す強力な証拠とした。
また最後に、より生理的な鉄欠乏モデルとして、妊娠前から母体に鉄欠乏食を与える長期モデルを用いて実験を行った結果、性転換は生じなかったが、Kdm3aヘテロ欠損と組み合わせることで、一部のXY胎仔においてSry発現の低下、H3K9me2の蓄積を伴う、性転換が確認された。これにより、母体の栄養状態と遺伝的背景が相互作用することで、胎仔生殖腺の性決定に破綻が生じる可能性があることが解明された。
以上の結果について研究チームは、Fe2+の生体内レベルがヒストン修飾酵素であるKDM3Aの活性を支え、Sryの転写活性が保証されるという、代謝-エピゲノム連関の存在を示すものであり、ほ乳類の性決定における鉄代謝の根幹的役割が明確にされたとする。
今回の研究は、これまで見過ごされがちだった「母体の栄養状態」が、胎仔の発生運命に重大な影響を与えうることを、性決定という最も基本的な発生プロセスの1つにおいて示した点で重要とのこと。妊娠中の鉄欠乏は、世界中で数億人規模の女性に影響を及ぼす公衆衛生上の問題であるため、今回の研究成果は大きな問題提起になる可能性もある。
ただし研究チームによると、今回の結果が直接ヒトに当てはまるかは、今後も慎重な検証が必要だという。鉄が必須補因子のエピゲノム関連酵素はKDM3A以外にも多く、それらの酵素群は神経系や造血系など他の発生プロセスにも広く関与する。今回示された“鉄とエピゲノムの連携”の概念は、性決定を越え、多様な発生異常や疾患の解明に波及的に貢献する可能性があるとしている。