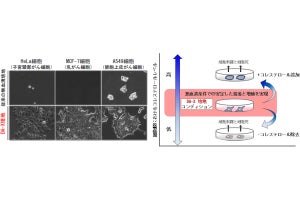東京大学は5月23日、分化と熟成の工程が、培養筋細胞や培養3次元筋組織において、“肉の味”に深く関わる「遊離アミノ酸」の量や組成を変動させ、とりわけ熟成が培養肉の遊離アミノ酸の量を大幅に増加させることを明らかにした。
同成果は、東大大学院 情報理工学系研究科の古橋麻衣大学院生、同・竹内昌治教授(東大 生産技術研究所 特任教授兼任)らの研究チームによるもの。詳細は、食品の化学と生化学を扱う学術誌「Food Chemistry」に掲載された。
国連経済社会局人口部が発表する世界人口推計によると、世界の人口は2058年には100億人を突破すると予測されている。もし世界中の人々が現在と同じ食生活を続けた場合、人口増加に伴い肉の需要は飛躍的に増大し、その結果として家畜の飼育頭数を増やす必要が生じる。
これにより、放牧地の拡大に加え、家畜の飼料となる穀物増産のための農地拡大も避けられない。さらに、家畜、中でも牛のゲップには、二酸化炭素よりも遥かに強力な温室効果ガスであるメタンガスが多量に含まれており、飼育頭数の増加はそうした環境問題への対策を不可避とする。こうした複合的な問題に対し、従来の食肉に代わる培養肉(人工肉)の生産技術の開発が喫緊の課題として求められている。
培養肉の生産技術の開発が重要であることは確かだが、たとえその技術が確立されたとしても、もし従来の食肉と比較して味が著しく劣るようでは、消費者の需要は伸び悩む可能性が危惧される。
これまでの研究では、培養肉の栄養価や培養手法の検討が中心であり、味を構成する分子成分に焦点を当てた研究は限定的だった。とりわけ、肉の味に深く関与する遊離アミノ酸に関する知見は乏しく、培養肉と従来の食肉との味の差異やその制御方法は未解明のままだった。
遊離アミノ酸とは、タンパク質に結合していない自由な状態のアミノ酸のことであり、肉の旨味や甘味、苦味といった味に直接影響を与えることが知られている。この知見に基づき、研究チームは今回、ウシの筋肉由来の細胞を使用し、分化や熟成といった工程が細胞内の遊離アミノ酸量および組成に与える影響を、極微量の化合物を高精度で分析可能な「液体クロマトグラフ飛行時間型質量分析」法を用いて、詳細な解析を行った。
まず、筋芽細胞と、その分化(特定の機能を持つ形へと発達する過程のこと)を経た筋管細胞を比較した。その結果、分化によって細胞内の遊離アミノ酸量が一時的に減少し、タンパク質合成が促進されることが示された。しかし、その後の4〜14日間にわたる低温下での熟成工程、すなわち肉の風味や柔らかさが向上するプロセスを経ると、タンパク質が分解され、遊離アミノ酸量が再び大きく増加することが明らかにされた。
注目すべきは、熟成過程において苦味系・甘味系アミノ酸の顕著な増加が観察された点だ。これは、熟成に伴う味覚成分の強化に大きく寄与している可能性が示唆されているとする。
-

筋芽細胞、筋管細胞、牛肉の遊離アミノ酸量の比較。分化によって遊離アミノ酸は減少するが、培養細胞は牛肉と比較して2倍以上の遊離アミノ酸を含有していることが確認された。特に、細胞(筋芽細胞と筋管細胞)はうまみ系アミノ酸が多い傾向が見られたという
(出所:東大ニュースリリースPDF)
加えて、乾燥重量当たりの遊離アミノ酸含量について、市販の牛肉との比較が行われた。その結果、非熟成状態の培養細胞が市販牛肉よりも2倍以上高い遊離アミノ酸濃度を有しており、培養細胞自体が強い味を持つ可能性が示唆されたという。
さらに、培養培地中のアミノ酸濃度を調整することで、細胞内の遊離アミノ酸組成を人工的に操作できる可能性も示されたとした。これらの成果は、将来的には「狙った味」を持つ培養肉の設計が実現可能になるという期待を抱かせるものだとしている。
今回の研究成果は、これまで感覚評価や官能検査に頼っていた「おいしさ」を、科学的に定量評価するための新たな指標を提供するものだ。さらに、培養肉の風味改良に向けた培養手法の構築に大きく寄与するものとしている。