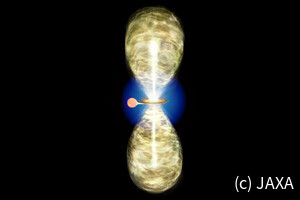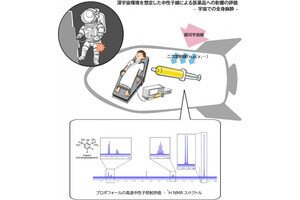国立天文台は5月7日、超新星爆発が濃い星周物質と相互作用した際に生じるニュートリノ・ガンマ線放射を新たな手法で計算し、2023年に天の川銀河の近傍銀河で発生した超新星爆発「SN 2023ixf」へと適用することで、宇宙線の生成効率に関して新たな制限をつけることに成功したと発表した。
-

おおぐま座の方向に約2000万光年離れたM101銀河(回転花火銀河/風車銀河)に出現した超新星SN 2023ixf。(c)International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA(出所:国立天文台 科学研究部Webサイト)
同成果は、東北大学 学際科学フロンティア研究所の木村成生准教授、国立天文台 科学研究部の守屋尭助教の研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。
宇宙空間には、高エネルギーの陽子や原子核が無数に飛び交っており、それらは宇宙線と呼ばれ、今この瞬間にも地球に数多く降り注いでいる。宇宙線はエネルギーによって、主に3種類に分類される。まず、エネルギーが比較的低い太陽宇宙線は、その数が多く地球近傍で最も観測されるものの、遮蔽は比較的容易であり、宇宙飛行士に対するリスクは小さめだ。次に、太陽宇宙線よりもエネルギーが高く、数も比較的多い銀河宇宙線がある。こちらはエネルギーが高いために遮蔽が困難であり、地球磁気圏外での宇宙活動において宇宙飛行士の主要な被爆源となり、DNA損傷などの危険性がある。最後に、数は極めて少ないので宇宙飛行士へのリスクは少ないが、極めて高いエネルギーを持つ超高エネルギー宇宙線が存在する。
これら3種類の宇宙線のうち、太陽宇宙線は太陽活動によって生成されることが明らかになっている一方で、銀河宇宙線と超高エネルギー宇宙線の起源天体や加速メカニズムには未解明な点が多い。特に、エネルギーが最も高い超高エネルギー宇宙線は、銀河系外で加速されていると考えられているが、起源天体を突き止めることは極めて困難である。活動銀河核やガンマ線バーストなどが起源天体の候補として挙げられているが、その正体は宇宙物理学における大きな謎の1つとなっている。
銀河宇宙線の起源には未解明な点が多いものの、研究は着実に進展中だ。宇宙線を加速させる領域の有力候補として考えられているのが、天の川銀河内の超新星残骸だ。そのメカニズムは、超新星爆発の際に放出された物質と星間ガスが衝突して生じる衝撃波によって宇宙線が加速されているというものだ。
近年の観測から、超新星爆発の際に周囲に非常に濃い星周物質が存在することが明らかになってきた。その結果として、星周物質と爆発噴出物が衝突して衝撃波が形成され、そこで宇宙線が加速されるというメカニズムが考えられている。さらに、そこで加速された宇宙線が濃い星周物質と衝突すると、ニュートリノやガンマ線が生成される。これらを捉えることで、宇宙線の加速領域や加速メカニズムを解明できる可能性がある。
このような背景の下、研究チームは今回、ニュートリノ・ガンマ線放射を計算する新たな手法を開発。そしてそれを、おおぐま座の方向に地球から約2000万光年離れた「M101銀河」(「回転花火銀河」あるいは「風車銀河」とも呼ばれる)に発生した超新星爆発SN 2023ixfに適用したという。
今回の研究では、輻射流体シミュレーションを用いてSN 2023ixfの観測データ(可視光など)を再現し、星周物質や超新星爆発の放出物質の構造を明らかにした。このシミュレーション結果に基づき、宇宙線の生成効率をパラメータとして、ニュートリノ・ガンマ線放射の計算が行われた。その結果、宇宙線の生成効率が10%以上の場合には、現状のガンマ線望遠鏡による未検出データと矛盾することが解明された。つまり、今回の研究により、宇宙線の生成効率に関する制限をつけることに成功したのである。
研究チームは、今後、今回の手法を複数の超新星爆発に適用することで、衝撃波における宇宙線の生成効率を解明できる可能性があるとしている。