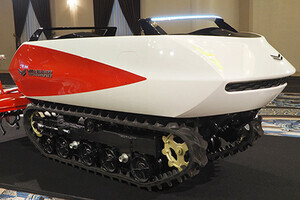ヤンマーエネルギーシステムは、イネのもみ殻を原料とする「バイオ炭」の効率的な製造装置の実証試験を、岐阜県で開始したと4月24日に発表。農作物の収量向上に向けた「高機能バイオ炭」のベースとなるもので、製造コスト削減に向けた研究開発を実施する。今後、全国50地区以上で行う栽培試験といった現地実証などに活用予定だ。
NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)と、ヤンマーホールディングス傘下のヤンマーエネルギーシステム、ぎふ農業協同組合による取り組み。「高効率もみ殻バイオ炭製造装置」の実験機を、JAぎふ方県カントリーエレベーター(岐阜市)に設置し、高機能バイオ炭のベースとなるバイオ炭の製造実証を開始した。「グリーンイノベーション基金事業/食料・農林水産業のCO2等削減・吸収技術の開発」における第1号機となる。実証期間は2031年3月末までの6年間。
ヤンマーエネルギーシステムらで構成する「高機能バイオ炭コンソーシアム」では、農作物の収量を向上させる新しいバイオ炭資材「高機能バイオ炭」の開発を進めている。これは、農業の副産物として出るイネもみ殻などを炭化し、土壌の炭素貯留に寄与するバイオ炭に、土壌中の養分を肥料成分として作物に供給することや、作物の健全な生育を助長するといった微生物機能を付与することで、収量向上を追求するものだ。
なおバイオ炭とは、IPCCガイドラインにより「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350度超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物」と定義されたもののことを指す。
-

JAぎふ方県カントリーエレベーター(岐阜市)での式典の様子。左から農林⽔産省 東海農政局局⻑ 秋葉一彦氏、ヤンマーエネルギーシステム ⼭下宏治社⻑、ぎふ農業協同組合 代表理事組合⻑ 岩佐哲司氏、新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事 ⻄村知泰氏、岐⾩県農政部次⻑ 河尻克晴、岐⾩市 後藤一郎副市⻑、農林⽔産省 農林⽔産技術会議事務局 研究総務官 東野昭浩氏
バイオ炭を広く農業者に使ってもらうにあたり、製造を含むコスト低減が課題だ。そのためにヤンマーエネルギーシステムでは、高効率もみ殻バイオ炭製造装置の開発に取り組んでおり、バイオ炭1トンあたりの製造コスト目標を3万円に設定。燃焼を効率化することなどにより、製造コストを通常のバイオ炭製造技術と比べて約40%抑えることをねらう。
同装置で生成したバイオ炭を使って、農作物の種類や地域の気象・立地条件が異なる地域で栽培試験を実施。その結果を、「農作物の単収向上効果」と「農地炭素貯留」を同時に実現する栽培技術体系としてまとめ、全国普及をめざす。さらに、農地炭素貯留効果によるカーボンクレジットの活用や、当該農法によってつくられた農産物の環境価値を可視化し、消費者に対して“環境価値農産物”として有利販売していくこともめざしている。
バイオ炭の原料となるイネもみ殻は、穀物を生産する多数の農家が共同利用するJAの大規模施設「カントリーエレベーター」などでの“もみ摺り”工程で大量に発生する。バイオ炭による炭素貯留効果を最大限に活かし、2050年カーボンニュートラルを実現するためには、こうしたカントリーエレベーターの敷地内(オンサイト)で効率的にバイオ炭を製造することが望ましいとされ、全国のJAとの連携は欠かせないという。
高機能バイオ炭コンソーシアムがめざす、オンサイト(地域)での効率的なバイオ炭の製造・利用、農産物の環境価値の可視化と価値訴求は、JAぎふが推進する地消地産型の農業との方向性が一致することから、方県カントリーエレベーターでの高効率バイオ炭製造実証と、持続可能な農業を実践する拠点「有機の里」でのバイオ炭の施用試験を行う。
ヤンマーエネルギーシステムでは24時間稼働で、1時間当たり100㎏のもみ殻から炭素残存率の高い30㎏のバイオ炭を製造できる高効率バイオ炭製造技術を確立することで、バイオ炭製造コストの低減を追求。前出の1トン当たり3万円という製造コスト目標に向け、同社がもつ従来の自動化と省エネ技術を活用する。さらに製造時の歩留りも従来比120%に引き上げることで、前述のように通常のバイオ炭製造技術比で約4割のコスト削減を見込む。
今回の実験機では、炉のピースを複数通り組み合わせることで、「もみ殻供給高さ」、「二次空気供給高さ」、「空気流量」などの最適な操作変数を導き出す。また、同社の従来技術を適応することで、化石燃料を使わず、製造時の温室効果ガス(GHG)排出量を低減。イネもみ殻を燃焼利用するときに問題となる発がん性物質“結晶質シリカ”の生成抑制も追求しており、環境に配慮した資源循環農業にも寄与するとのこと。