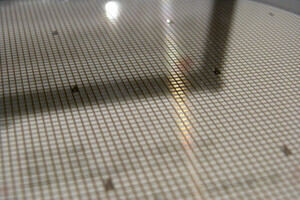米国の新たな相互関税では、適用対象として、その製品を構成する米国原産の部品・原料のコストが製品価格の20%以上であれば、当該の米国原産部品・原料に係るコスト分については、相互関税の対象外となるという条項が盛り込まれたが、TrendForceによると、関税導入によるインフレおよび景気後退リスクが、半導体を搭載する最終製品市場の2025年出荷見通しを下方修正する要因となっているという。
2025年第1四半期はサーバ、スマートフォン(スマホ)、ノートPCの出荷は予想を上回ったが、これは新たな関税導入に先立つ米国への出荷前倒しによるもので、TrendForceでは、サプライチェーン各社がコストの増加を吸収する方法を依然として検討中であると指摘している。
米国での価値がブランドの国籍での評価なのか、製造原産地に基づく評価なのかは、業界にとっての懸念事項となっており、TrendForceでも2つの修正予測シナリオを提示している。関税により需要が常識的な範囲で減少するベースケースでは、米国における20%の価値はブランドベースと解釈され、米国ブランドはシステム全体または完成品に対して免除を受ける可能性が高くなる一方、最悪ケースでは、製造拠点に基づいて定義され、市場縮小のリスクが高まるとする。
AIサーバ分野ではベースケースは関税免除による部分的な負担軽減が想定されている。関税リストから除外されているメキシコはUSMCA協定に基づき、戦略的な再輸出拠点であり続けるが、不確実性の継続からTrendForceでは2025年のAIサーバ出荷成長率予測を前年比24.5%に下方修正。最悪ケースでは、関税の高騰による景気減速でAIサーバ投資も先送りされ、同約18%に低下するとしている。
また、企業の設備投資も抑制され、2025年後半にはIT予算がより保守傾向となる予想により、サーバ出荷成長率予測も同5.4%へと下方修正。最悪ケースでは、関税が半導体などの部品にまで拡大されると見て同2%の伸びに留まると予測している。
スマホ分野は20%ルール次第で、中上位機種が関税免除となる可能性がある一方、下位機種が影響を受け続ける可能性があり、消費者もコストパフォーマンスを重視した購入に向かうことで、2025年のスマホ生産量はベースケースで前年比横ばい、最悪ケースで同5%減と予測している。
ノートPC分野は、消費者と企業ともに需要の抑制され、2025年のノートPC ODM出荷成長率はベースケースで同3%増、最悪ケースで同2%増に鈍化すると予測している。
すでに4月9日の相互関税発効(と一部の90日間の停止)に併せる形でHPやDell、Acer、ASUS、Lenovoといった大手PC各社はサプライチェーンに対し、生産国に関わらず、米国向け製品の出荷停止を通知したと台湾メディアが報じている。
それによると、この停止措置はノートPCのほか、周辺機器にもおよび、2週間ほど実施される見込みで、対話のの周辺機器メーカー各社は顧客から一時的な出荷停止の通知を受けたという。
一方、台湾の光学部品および受動部品メーカーの多くは米国に直接出荷をしていることが稀であることもあり、通常通り製品の出荷を継続しており、関税関連コストの分担などの協議も行われていないとする企業もある模様だ。ただし、新たな関税による経済の減速とそれによる景気後退の可能性については懸念を示している。