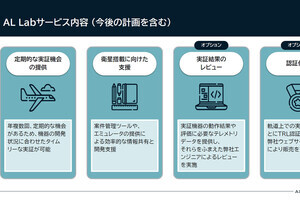アクセルスペースは、新たな地球観測衛星「GRUS-3」計7機を2026年に打ち上げ、現在運用中の「GRUS-1」5機とあわせて10機以上の体制に増強すると発表。広範囲を高頻度に観測できるようにする。4月9日に都内で実施された記者発表会では、日本橋にある本社オフィスに設えたクリーンルームの様子も公開した。
画質向上し水中も撮れる新衛星「GRUS-3」
次世代地球観測衛星「GRUS-3」(グルーススリー)では、新しいイメージセンサーを使用し、地上分解能2.2m(中分解能)を実現。2018年から運用している「GRUS-1」(グルースワン)よりも取得できる画像の品質が向上する点が大きな特徴だ。
-

側面に多数の太陽電池パネルを搭載。中央上のスリットは、大気圏に再突入するための“ブレーキ”として展開する膜を出す部分で、設計寿命(5年程度)を迎えたタイミングで、衛星自身がスペースデブリになってしまわないよう、自律的に減速してデオービットする(軌道を離れる)とのこと。ちなみに、中央下のスリットは衛星が完成したあともデータを取れるようにする“整備用ハッチ”で、打ち上げ時にはフタをしてしまうそうだ
同社のAxelGlobe事業本部ミッションペイロードグループ ミッションPM SEユニットユニットリーダーを務める仁井田麻理氏は、「GRUS-1による画像でもサービスの提供や解析には十分なデータだが、GRUS-3で画像が向上することで、顧客によってより使いやすいデータとなることに期待している」と自信を見せた。
GRUS-3の1機あたりの撮影能力は、観測幅28.3km×最長観測距離1,356kmで、7機をあわせた1日の撮影能力は、日本の面積の約6倍相当の最大230万平方kmにおよぶ。撮影頻度も強化しており、北緯25度以上の地点であれば、同一地点をほぼ同一時刻に毎日撮影できるとのこと。
観測バンド(観測可能な光の波長)には、パンクロマティック(白黒)と青、緑、赤、レッドエッジ、近赤外に加え、新たに水中を観測できる「コースタルブルー」が加わった。コースタルブルーの波長帯は水中で減衰しにくいため、沿岸域の観測に有効だとしており、たとえば水中のCO2(二酸化炭素)を固定する沿岸部の藻場や、サンゴ礁、マングローブなどをモニタリングできるようになると説明している。実際に観測できる水深は、大気や水の状態にも依るが、5~10m程度を見込んでいるとのこと。
運用軌道は、高度585kmの太陽同期軌道。大きさは“単身者用の冷蔵庫”ほどのサイズ感と説明しており、外形寸法/質量は96×78×126cm(幅×縦×高さ)/約150kgと、GRUS-1よりも大型化している(GRUS-1の外形寸法/質量は60×60×80cm/約100kg)。
ちなみに、現行のGRUS-1計5機による1日の撮影能力は75万平方kmで、撮影頻度は2~3日に1回。新たに加わるGRUS-3は、現行のGRUS-1と一体運用することも可能で、これらの撮影能力を組み合わせることで、従来よりもさらに速く撮影データを顧客に渡せるようになるとしている(なお、1と3は周回する軌道が違うため、撮影能力の数値は純粋な足し算にはならない)。
なおアクセルスペースでは、GRUS-3に搭載する望遠鏡(カメラ)を含む光学システムの性能や、衛星の基盤となる構造や機能を標準化した「衛星汎用バスシステム」を検証するための小型衛星「GRUS-3α」(グルーススリーアルファ)をあわせて発表。
2025年夏(6月以降)をめどに打ち上げる予定で、米カリフォルニア州・ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から、スペースX(SpaceX)のFalcon 9ロケットによって打ち上げることが決まっている。
同社AxelLiner事業本部プロジェクトグループ プロジェクトマネジメントユニット プロジェクトマネジャーの杉本和矢氏によると、GRUS-3αは打ち上げ後、まず動作チェックとチューニングを数カ月かけて行い、性能検証を進めていくことになる。汎用バスシステムの検証も兼ねており、たとえばソフトウェアで機能を追加することになった場合、まずGRUS-3αで検証した後に、GRUS-3へ展開していくといった使い方も考えているようだ(なお、GRUS-3αには衛星間通信機能は備えていない)。
軌道上で使える実験衛星となるGRUS-3αと、商用機として今後展開していくGRUS-3。位置づけは異なるが、基本的な部分はほぼ共通ということで、GRUS-3αで取得したデータを商用展開することも考えられそうだ。杉本氏は「現時点で確定ではないが、そういうことも検討はしている」と話していた。
-

アクセルスペースの商用光学衛星の変遷。「GRUS-1」はロシアのソユーズロケットでは2018年に1機、2021年に4機打ち上げ、現在も運用中。2022年頃には「GRUS-2」を打ち上げ予定だったが、ウクライナ情勢の影響で計画自体がキャンセルになったとのこと。性能検証機である「GRUS-3α」は前述の通り、スペースXのFalcon 9ロケットによる打ち上げが決まっている
AxelGlobeの強みは「フルカラー画像」と「広域観測」
アクセルスペースは、小型衛星のものづくりとサービス提供というふたつの事業を両立させ、顧客の宇宙ミッション実現のための衛星開発・運用事業を行う「AxelLiner」(アクセルライナ−)、自社の光学衛星コンステレーションによる地球観測データ提供事業「AxelGlobe」(アクセルグローブ)を展開する宇宙ベンチャー企業だ。
AxelGlobeは2019年にスタートし、現在は小型光学衛星「GRUS-1」計5機による、国内最多機数の商用光学衛星コンステレーションを構築。衛星の姿勢制御技術を生かして、特定エリアを指定して確実に撮影できる体制を整え、顧客の情報収集や意思決定に役立つ衛星画像データを提供している。
提供可能なデータと事例として挙げたのは、地上の植生の活性度などの可視化や、森林伐採をはじめとする地上の時間的変化の把握、海上の貨物船の自動検出といった情報定量化、浸水する可能性のある地域を調べる状況把握の4種類。
AxelGlobeの地球観測は、太陽光が地表に反射した光を観測する光学方式で行うため、フルカラーの直感的な情報が得られ、多様な解析ができることや、広域観測が可能な点が強みだという。同一地点を複数回撮影した画像を処理することで、雲のない衛星画像を生成することもできる。
具体的な例として、同社は2025年3月に起きた岩手・大船渡市の山林火災を受けて撮影した画像を公開。このように宇宙から様子が見える事象については積極的に撮影を行って関係各所に提供しているということで、2024年1月の能登半島地震や、直近では2025年3月のミャンマー大地震を受けた撮影も行ったとのこと。
このほか、衛星画像がフェイクではなく真性のものであることを証明できるよう、画像撮影時の衛星の軌道上の位置や姿勢などの情報を画像とともに管理し、客観的に証明できる技術も保有しており、特許取得済み。今後サービスへの実装を検討しているという。
ちなみに、衛星から地表に向けて電波を照射し、跳ね返ってきた電波の特性を観測するSAR(Synthetic Aperture Radar)方式は、白黒画像にはなるが夜間や雨天時も観測可能で、地表面の対象の形状把握や、地形の時系列変化の抽出が得意という特徴をもち、光学では難しい撮影も行える点に強みがある。
アクセルスペースの事業内容や特徴を紹介した、同社代表取締役 CEOの中村友哉氏は、光学データとSARデータの特徴の説明の中で、「(両者は)お互いの強みと弱みを補完し合う関係にあるというふうに考えている。どちらが優れているというよりは、どちらも使わなければいけないといえるのではないか」と付け加えた。
AxelGlobeのデータはこれまでに、世界30カ国以上の行政機関や民間企業に提供しており、地域別では国内67%、海外33%。顧客別でみると、全世界では民間企業66%、政府案件34%と、民間のほうが割合が高くなっている。ちなみに国内では民間企業49%、政府案件51%とほぼ半々。中村氏は「政府案件も大事にしているが、(アクセルスペースが)より成長するには、民間向けのサービス拡充と利用普及も大事だ」と述べた。
そのAxelGlobe事業を成長させるための3つの柱として、同社では「衛星の数を増やすことによる観測能力の増強」、「画像やサービスの拡充による多様なニーズへの対応」、「業界を超えた協業による新しいソリューションの提供」を掲げ、不動産や金融、環境事業、国土管理にいたるまで、幅広い産業における地球観測データの利用促進をめざしている。
今回発表したGRUS-3と10機超への体制増強は、同社がまず実現すべき目標として掲げてきた、衛星機数の増加による観測能力強化を実現する足がかりとなる。