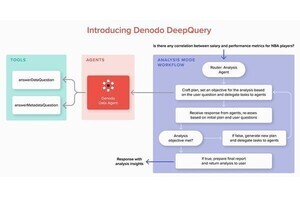3月18日・19日の2日間にわたり、東京国際フォーラムを中心とする丸の内・有楽町エリアで開催された「第9回 サステナブル・ブランド国際会議2025 東京・丸の内(SB'25)」。今や世界共通の標語ともいえる「サステナビリティ」をテーマに、さまざまな角度から取り組みを進める各業界の先駆者たちが一堂に会した同イベントでは、数多くの講演やセッションをはじめ、ブース展示、オープンセミナーなどを通じてたくさんの交流が生まれた。
多くの来場者を集めた同イベントの2日目の様子は、以前の記事(「サステナブルの最前線「SB'25」開催 - Hondaが燃料電池自動車を展示」)で紹介した。今回は、創業70周年を迎えるヤマハ発動機に注目。脈々と受け継がれてきた製品開発の歴史や、同社執行役員 経営戦略本部長の青田元氏の講演から、ヤマハ発動機の“サステナビリティ”について考える。
ヤマハ発動機を象徴する“赤トンボ”と“黄色い帽子”
SB'25のスポンサー企業やコミュニティ、学生などがブースを展開したネットワーキングエリア「Activation Hub」にて、ヤマハ発動機は、同社のサステナビリティを象徴する3つの製品を展示した。過去製品として展示されたのは、同社にとっての第1号製品であるオートバイ「YA-1」と、ボートの動力源となる1961年発売の小型船外機「P-3」。そして現在も提供中の製品として、電動車いすの試乗体験展示が行われた。
ヤマハ発動機の主力製品と言えば、二輪車だ。その礎となったYA-1は、創業者である川上源一氏が口にした「生活を楽しむことを拡げたい」との言葉を象徴した製品で、黒が主流だったオートバイ市場に一石を投じる赤茶色のボディから“赤トンボ”と呼ばれ愛された。この製品を通して同社が顧客に届けようとしたのは、「生活を楽しむこと」。実用性だけを追い求めるのではなく、趣味性を高めたYA-1は、今なお「感動創造企業」を企業目的に掲げるヤマハ発動機の起点となる製品だとする。
そして二輪車と並ぶ現在の事業の柱が、ボートや水上バイクなどを含むマリン事業。その基礎を築いたのが、“黄色い帽子”の愛称がついた小型船外機のP-3だという。開発当時は、国内のさまざまな漁業従事者に話を聞いてニーズを抽出し、製品に活かしていたとのこと。製品の耐久性や馬力を向上させ、日本全国の沿岸漁業者から愛されるに至った。
これらの歴史を紡いできた製品たちに並び体験展示が行われたのは、電動車いす製品。ブースでは体験展示が行われ、実際に乗り込んで走る来場者からは、小回りが利き動きやすいその性能に驚きの声が上がっていた。
“楽しさ・豊かさ”を提供するというサステナビリティ
ヤマハ発動機は、2025年からの中期経営計画の中でサステナビリティ経営方針として3つのテーマを提示。「モビリティの楽しさ」「豊かな人生」「地球との共生」をメッセージとして掲げた。この3つのうち、CO2の排出量削減やリサイクルによる資源消費量削減など、“サステナビリティ”という標語から連想しやすいのは、「地球との共生」だろう。その取り組みとして同社は、無人ヘリコプターに搭載した高解像度LiDARなどの高度レーザ計測および分析技術を用いて、広範な森林の状況を3Dデータで提供する森林デジタル化サービス「RINTO」などの事業も展開している。
一方で、今回のブースで展示されたのは「モビリティの楽しさ」や「豊かな人生」をターゲットに提供されてきた製品群といえる。二輪車のYA-1は、利便性だけを見れば四輪車に劣る面も多いものの、面倒くささや手間などを“乗り物としての魅力”につなげている存在であり、モビリティの楽しさを生み出し、さらに人生を豊かにする役割を担う。また船外機は、アフリカなどでは漁に出るための道具として人生を豊かにする役割を果たす一方で、ホビー目的での利用が多い現在の北米市場などでは楽しさを与える存在であるなど、さまざまな角度からヤマハ発動機の掲げるサステナビリティに貢献。そして電動車いすも、歩くことのできない人に移動の可能性を与え、人生を豊かにさせている。
そもそも“サステナビリティ”の日本語訳は「持続可能性」。地球を持続可能にするのはもちろんのこと、人々の生活、そして幸せを持続可能な形に変えるのも、サステナブルな取り組みだ。「サステナビリティ重視が流行しているから取り組んでいるのではなく、これまでにも人生を豊かにするための製品を提供して、サステナビリティに貢献してきた、というメッセージを込めて製品を展示している」と担当者は語り、ヤマハ発動機にとってサステナブルな取り組みが、一朝一夕に行われているものではなく、創業当初から脈々と受け継がれていることを示した。
経営戦略本部長の青田氏が経営者たちにメッセージ
また、SB'25の2日目に行われた「Day2 Plenaries」では、ヤマハ発動機の執行役員で経営戦略本部長を務める青田元氏が登壇し、同社の歴史と未来をつなぐ中で見えるサステナビリティについて語った。
青田氏は、ヤマハ発動機によるサステナビリティの事例をいくつかピックアップ。社員の中から自発的に始まった「ビーチクリーン運動」や、ゴルフカートを用いて地方の地域交通課題解決に取り組む動き、さらには、船外機の販売に付随して漁の方法や販路の確保方法など“ビジネス”の手法までを支援する取り組みなどを紹介した。多岐にわたる取り組みを見せる同社だが、青田氏によれば「経済的価値を生んで初めて、社会的価値が創出できる」とのこと。「目的と手段が入れ替わらないよう、事業としての経済的価値を基盤として社会的価値創造を考えている」とする。
また講演の最後には、経営者、今後就職を目指す学生や求職者、サステナビリティ担当者に向け、メッセージを送った。経営者に対しては、「サステナビリティ担当者の意見を“リスクマネジメント”の視点から聞くのではなく、未来をつくるための意見を一度俯瞰して捉えるよう心掛けてほしい」、学生・求職者には、「面接に臨む際には、『経営者がどんなサステナビリティ方針を掲げ、どんな取り組みを進めたのか』を聞いてほしい。これで、企業が取り組む本当の想いや姿勢が見えてくる」とコメント。そしてサステナビリティ担当者に向けては「一人では何も成し遂げられない。だからこそこの場にいる多くの人と一丸になっていかなければならない」と強い言葉を残した。
長期ビジョンとして「ART for Human Possibilities」に続く形で、「人はもっと幸せになれる」と打ち出したヤマハ発動機。そこには、“感動創造企業”として楽しさや豊かさを提供してきた同社が信じる、モビリティの可能性が込められている。創業から紡がれてきた同社のサステナビリティは、これからどんな進化を遂げるのだろうか。