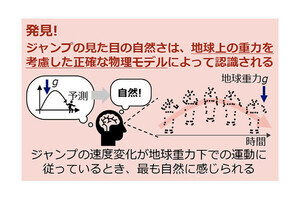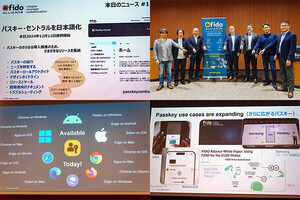北海道大学(北大)と中京大学の両者は3月27日、割引などの“強調表示”された動画広告内に付随する条件など、極めて小さな文字サイズで表示されることが多い「打ち消し表示」が、仮にその文字サイズを拡大したとしても、安定した視線停留や記憶を必ずしも保証しないことを明らかにしたと共同で発表した。
同成果は、北大大学院 文学研究院の河原純一郎教授、中京大 心理学部の伊藤資浩任期制講師の共同研究チームによるもの。詳細は、日本心理学会が刊行する心理学を扱う学術誌「心理学研究」に掲載された。
現代社会の日常生活においては、動画広告を目にする機会が急増しており、もはや見ない日はないといえるほどとなっている。そうした動画広告には、有益な情報が含まれるものもある一方で、商品やサービスの訴求点に対する留意事項が目立たない形で示されることも少なくない。例えば、「通常価格から30%割引」といった魅力的な取引条件を示す強調表示に対し、「割引は会員限定」のように付随する条件や補足事項を伴う場合などがこれにあたり、このような記載は“打ち消し表示”と呼ばれる。本来、テレビCMも含めた動画広告は、時間的な制約がある場合でもその内容を適切に消費者に伝える必要がある。しかし実際にはそうした打ち消し表示が十分に認識されず、消費者が広告内容を誤認した結果、トラブルが増加しているという現状がある。
広告内容の誤認の要因として、打ち消し表示の文字サイズが小さいことに起因する可能性が考えられる。動画広告に関する実態調査によれば、打ち消し表示は強調表示の2~3割未満の文字サイズ(文字幅で約0.50度)で表示されており、視認性が低いことが明らかになっている。また動画広告では、通常は強調表示などに対応する音声が呈示されるため、視聴者の注意は強調表示か所に集中しやすくなり、結果として打ち消し表示への注意が向きにくくなることも考えられるとする。
そこで研究チームは今回、56名の実験参加者の協力を得て、打ち消し表示の文字サイズの拡大が視認性の向上につながり、ひいては打ち消し表示の意識的な想起や再認にどのような影響を与えるのかを検証。加えて、動画広告視聴中の視線計測を実施し、一般的な打ち消し表示の文字サイズである30ptと、拡大した80ptでの比較も行われた。
実験では、消費者庁のWebサイトで公開されている2種類の動画広告が用いられた。具体的には、就職活動用のスーツと、スマートフォンの広告で、日常的な視聴に近い状況を作るため、これら2つの異なる広告を組み合わせ、計60秒(各15秒)の動画が作成された。対象となる2つの広告に含まれる打ち消し表示の文字サイズを調整し、広告の後半部分において2秒間表示。参加者には商品を実際に購入するつもりで動画広告を視聴してもらい、視聴中の参加者の視線の動きは視線計測装置を用いて記録された。そして視聴後、参加者は2種類の動画広告それぞれについて、思い出せる内容を記述する再生課題に取り組んだ。
各動画広告と文字サイズ条件ごとの視線停留時間を分析した結果、スーツの広告においては、30ptより80ptで打ち消し表示の方が、視線停留時間が有意に長かったという。この結果は、参加者が拡大された打ち消し表示(80pt)の方をより注視した可能性が示唆されている。しかし、同様の効果はスマートフォンの広告では確認されなかったといい、このことから、文字サイズの拡大が必ずしも打ち消し表示への注視を高めるわけではないことが示唆されたとした。
また、打ち消し表示の文字サイズが拡大しても、再生率への有意な影響は見られなかったとのこと。具体的には、スーツの広告の再生率は14.3~32.1%の範囲であり、スマートフォンの広告では7.1~10.7%だった。これらの結果から、3分の2以上の参加者が打ち消し表示の内容を意識的に思い出すことができなかったことが示唆された。
-

(左)各動画広告における打ち消し表示の表示例。(右)文字サイズごとの打ち消し表示への視線停留時間。打ち消し表示は2秒間呈示され、その間に打ち消し表示へ向けられた視線の累積時間を換算したものが示されている(出所:北大プレスリリースPDF)
今回の研究成果は、文字サイズの拡大が打ち消し表示への安定的な視線誘導や表示内容の記憶を保証するものではなく、文字サイズの拡大による視認性の向上だけでは不十分であることが示された。研究チームはこの結果について、動画広告における打ち消し表示に関する規制策定に対して重要な示唆を与えると考えられるとする。例えば、打ち消し表示を行う際に考慮すべき点として、強調表示との相対的な大きさ、表示場所、背景とのコントラストなどが挙げられるが、現時点ではこれらの点に関する明確な規定は存在せず、消費者にとって有効な打ち消し表示を決定するためには、実際の表示方法を用いて、打ち消し表示への意識的な想起が十分に促されるかどうかを検証する必要があるとしている。